八代古今後撰拾遺後拾遺金葉詞花千載新古今百人一首六歌仙三十六歌仙枕詞動詞光る君へ
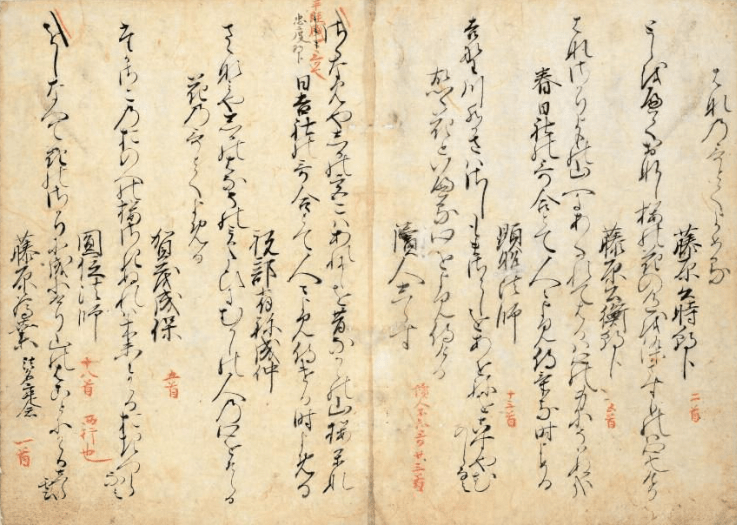
千載和歌集のデータベース
千載和歌集とは
- 七番目の勅撰和歌集であり、後白河院によって撰集が院宣され、撰者は藤原俊成。
- 1188年に完成。
千載和歌集の構成
| 春上 | 春下 | 夏 | 秋上 | 秋下 | 冬 | 離別 | 羈旅 | 哀傷 | 賀 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数 | 76 | 59 | 90 | 76 | 85 | 89 | 22 | 47 | 61 | 35 |
| % | 5.8 | 4.5 | 6.9 | 5.8 | 6.5 | 6.8 | 1.7 | 3.6 | 4.7 | 2.7 |
| 恋一 | 恋二 | 恋三 | 恋四 | 恋五 | 雑上 | 雑中 | 雑下 | 釈教 | 神祇 | |
| 数 | 63 | 76 | 60 | 64 | 55 | 93 | 108 | 42 | 54 | 33 |
| % | 4.8 | 5.8 | 4.6 | 4.9 | 4.2 | 7.2 | 8.3 | 3.2 | 4.1 | 2.5 |
- 巻二十から成り、全1288首、及び、異本歌の2首。
千載和歌集 言の葉データベース
「かな」は原文と同様に濁点を付けておりませんので、例えば「郭公(ほととぎす)」を検索したいときは、「ほとときす」と入力してください。
| 歌番号 | 歌 | よみ人 | 巻 | 種 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | はるのくるあしたのはらをみわたせは霞もけふそたちはしめける はるのくる あしたのはらを みわたせは かすみもけふそ たちはしめける | 源俊頼朝臣 | 一 | 春上 |
| 2 | みむろ山たににや春のたちぬらむ雪のした水いはたたくなり みむろやま たににやはるの たちぬらむ ゆきのしたみつ いはたたくなり | 中納言国信 | 一 | 春上 |
| 3 | 雪ふかきいはのかけ道あとたゆるよし野の里も春はきにけり ゆきふかき いはのかけみち あとたゆる よしののさとも はるはきにけり | 待賢門院堀河 | 一 | 春上 |
| 4 | みちたゆといとひしものを山さとにきゆるはをしきこその雪かな みちたゆと いとひしものを やまさとに きゆるはをしき こそのゆきかな | 前中納言匡房 | 一 | 春上 |
| 5 | 春たては雪のした水うちとけて谷のうくひすいまそ鳴くなる はるたては ゆきのしたみつ うちとけて たにのうくひす いまそなくなる | 藤原顕綱朝臣 | 一 | 春上 |
| 6 | 山さとのかきねに春やしるからんかすまぬさきに鴬のなく やまさとの かきねにはるや しるからむ かすまぬさきに うくひすのなく | 大納言隆国 | 一 | 春上 |
| 7 | 煙かとむろのやしまをみしほとにやかても空のかすみぬるかな けふりかと むろのやしまを みしほとに やかてもそらの かすみぬるかな | 源俊頼朝臣 | 一 | 春上 |
| 8 | かすみしく春のしほちをみわたせはみとりをわくるおきつしら浪 かすみしく はるのしほちを みわたせは みとりをわくる おきつしらなみ | 摂政前右大臣 | 一 | 春上 |
| 9 | わきも子か袖ふるやまも春きてそ霞のころもたちわたりける わきもこか そてふるやまも はるきてそ かすみのころも たちわたりける | 前中納言匡房 | 一 | 春上 |
| 10 | 春くれはすきのしるしもみえぬかな霞そたてるみわの山もと はるくれは すきのしるしも みえぬかな かすみそたてる みわのやまもと | 刑部卿頼輔 | 一 | 春上 |
| 11 | みわたせはそことしるしの杉もなし霞のうちやみわの山もと みわたせは そことしるしの すきもなし かすみのうちや みわのやまもと | 左兵衛督隆房 | 一 | 春上 |
| 12 | ときはなる松もや春をしりぬらんはつねをいはふ人にひかれて ときはなる まつもやはるを しりぬらむ はつねをいはふ ひとにひかれて | 待賢門院堀河 | 一 | 春上 |
| 13 | うらやまし雪のした草かきわけてたれをとふひのわかななるらん うらやまし ゆきのしたくさ かきわけて たれをとふひの わかななるらむ | 治部卿通俊 | 一 | 春上 |
| 14 | かすか野の雪をわかなにつみそへてけふさへ袖のしほれぬるかな かすかのの ゆきをわかなに つみそへて けふさへそての しをれぬるかな | 源俊頼朝臣 | 一 | 春上 |
| 15 | さきそむる梅のたちえにふる雪のかさなるかすをとへとこそおもへ さきそむる うめのたちえに ふるゆきの かさなるかすを とへとこそおもへ | 権中納言俊忠 | 一 | 春上 |
| 16 | むめかえに心もゆきてかさなるをしらてや人のとへといふらん うめかえに こころもゆきて かさなるを しらてやひとの とへといふらむ | 源俊頼朝臣 | 一 | 春上 |
| 17 | むめかえにふりつむ雪は鴬のはかせにちるも花かとそみる うめかえに ふりつむゆきは うくひすの はかせにちるも はなかとそみる | 左京大夫顕輔 | 一 | 春上 |
| 18 | かをる香のたえせぬ春はむめの花ふきくる風やのとけかるらん かをるかの たえせぬはるは うめのはな ふきくるかせや のとけかるらむ | 久我前太政大臣 | 一 | 春上 |
| 19 | いまよりはむめさくやとは心せんまたぬにきます人も有りけり いまよりは うめさくやとは こころせむ またぬにきます ひともありけり | 大納言師頼 | 一 | 春上 |
| 20 | にほひもてわかはそわかむ梅のはなそれともみえぬ春のよの月 にほひもて わかはそわかむ うめのはな それともみえぬ はるのよのつき | 前中納言匡房 | 一 | 春上 |
| 21 | むめの花をりてかさしにさしつれは衣におつる雪かとそみる うめのはな をりてかさしに さしつれは ころもにおつる ゆきかとそみる | 大炊御門右大臣 | 一 | 春上 |
| 22 | むめかかにおとろかれつつ春のよのやみこそ人はあくからしけれ うめかかに おとろかれつつ はるのよの やみこそひとは あくからしけれ | 和泉式部 | 一 | 春上 |
| 23 | さ夜ふけて風やふくらん花のかのにほふここちのそらにするかな さよふけて かせやふくらむ はなのかの にほふここちの そらにするかな | 藤原道信朝臣 | 一 | 春上 |
| 24 | はるの夜はのきはのむめをもる月のひかりもかをる心ちこそすれ はるのよは のきはのうめを もるつきの ひかりもかをる ここちこそすれ | 皇太后宮大夫俊成 | 一 | 春上 |
| 25 | 春のよはふきまふ風のうつり香を木ことにむめとおもひけるかな はるのよは ふきまふかせの うつりかを きことにうめと おもひけるかな | 崇徳院御製 | 一 | 春上 |
| 26 | むめかかはおのかかきねをあくかれてまやのあたりにひまもとむなり うめかかは おのかかきねを あくかれて まやのあたりに ひまもとむなり | 源俊頼朝臣 | 一 | 春上 |
| 27 | むめかかにこゑうつりせは鴬のなく一えたはをらましものを うめかかに こゑうつりせは うくひすの なくひとえたは をらましものを | 右大臣 | 一 | 春上 |
| 28 | 梅かえの花にこつたふうくひすのこゑさへにほふ春の曙 うめかえの はなにこつたふ うくひすの こゑさへにほふ はるのあけほの | 仁和寺法親王(守覚) | 一 | 春上 |
| 29 | 風わたるのきはのむめに鴬のなきてこつたふ春のあけほの かせわたる のきはのうめに うくひすの なきてこつたふ はるのあけほの | 権大納言実家 | 一 | 春上 |
| 30 | むかしよりちららむやとのむめの花わくる心は色にみゆらん むかしより ちらさぬやとの うめのはな わくるこころは いろにみゆらむ | 大納言定房 | 一 | 春上 |
| 31 | よも山にこのめ春さめふりぬれはかそいろはとや花のたのまん よもやまに このめはるさめ ふりぬれは かそいろはとや はなのたのまむ | 前中納言匡房 | 一 | 春上 |
| 32 | はるさめのふりそめしよりかたをかのすそ野の原そあさみとりなる はるさめの ふりそめしより かたをかの すそののはらそ あさみとりなる | 藤原基俊 | 一 | 春上 |
| 33 | つれつれとふれは涙の南なるを春の物とや人はみるらん つれつれと ふれはなみたの あめなるを はるのものとや ひとはみるらむ | 和泉式部 | 一 | 春上 |
| 34 | み山木のかけののしたの下わらひもえいつれともしる人もなし みやまきの かけののしたの したわらひ もえいつれとも しるひともなし | 藤原基俊 | 一 | 春上 |
| 35 | みこもりにあしのわかはやもえぬらん玉江のぬまをあさる春こま みこもりに あしのわかはや もえぬらむ たまえのぬまを あさるはるこま | 藤原清輔朝臣 | 一 | 春上 |
| 36 | 春くれはたのむのかりもいまはとてかへる雲ちにおもひたつなり はるくれは たのむのかりも いまはとて かへるくもちに おもひたつなり | 源俊頼朝臣 | 一 | 春上 |
| 37 | なかむれはかすめるそらのうき雲とひとつになりぬかへるかりかね なかむれは かすめるそらの うきくもと ひとつになりぬ かへるかりかね | 左近中将良経 | 一 | 春上 |
| 38 | あまつそらひとつにみゆるこしの海の浪をわけてもかへる雁かね あまつそら ひとつにみゆる こしのうみの なみをわけても かへるかりかね | 前右京権大夫頼政 | 一 | 春上 |
| 39 | かへるかりいく雲ゐともしらねとも心はかりをたくへてそやる かへるかり いくくもゐとも しらねとも こころはかりを たくへてそやる | 祝部宿禰成仲 | 一 | 春上 |
| 40 | 春はなほはなのにほひもさもあらはあれたた身にしむは曙のそら はるはなほ はなのにほひも さもあらはあれ たたみにしむは あけほののそら | 藤原季通朝臣 | 一 | 春上 |
| 41 | あさゆふに花まつころはおもひねの夢のうちにそさきはしめける あさゆふに はなまつころは おもひねの ゆめのうちにそ さきはしめける | 崇徳院御製 | 一 | 春上 |
| 42 | いつかたに花さきぬらんとおもふよりよもの山辺にちる心かな いつかたに はなさきぬらむと おもふより よものやまへに ちるこころかな | 待賢門院堀川 | 一 | 春上 |
| 43 | 山さくらたつぬときくにさそはれぬ老のこころのあくかるるかな やまさくら たつぬときくに さそはれぬ おいのこころの あくかるるかな | 京極前太政大臣 | 一 | 春上 |
| 44 | かけきよき花のかかみとみゆるかなのとかにすめるしら川の水 かけきよき はなのかかみと みゆるかな のとかにすめる しらかはのみつ | 花園左おほいまうちきみ | 一 | 春上 |
| 45 | よろつ代の花のためしやけふならんむかしもかかる春しなけれは よろつよの はなのためしや けふならむ むかしもかかる はるしなけれは | 徳大寺左大臣(于時左兵衛督) | 一 | 春上 |
| 46 | たつねつる花のあたりになりにけりにほふにしるし春の山かせ たつねつる はなのあたりに なりにけり にほふにしるし はるのやまかせ | 崇徳院御製 | 一 | 春上 |
| 47 | かへるさをいそかぬほとの道ならはのとかにみねの花はみてまし かへるさを いそかぬほとの みちならは のとかにみねの はなはみてまし | 法性寺入道前太政大臣 | 一 | 春上 |
| 48 | 山さくらにほふあたりの春かすみ風をはよそにたちへたてなん やまさくら にほふあたりの はるかすみ かせをはよそに たちへたてなむ | 中納言女王 | 一 | 春上 |
| 49 | 花ゆゑにかからぬ山そなかりける心ははるのかすみならねと はなゆゑに かからぬやまそ なかりける こころははるの かすみならねと | 藤原顕綱朝臣 | 一 | 春上 |
| 50 | さくら花おほくの春にあひぬれと昨日けふをやためしにはせん さくらはな おほくのはるに あひぬれと きのふけふをや ためしにはせむ | 京極前太政大臣 | 一 | 春上 |
| 51 | はなさかりはるの山へをみわたせはそらさヘにほふ心ちこそすれ はなさかり はるのやまへを みわたせは そらさへにほふ ここちこそすれ | 後二条関白内大臣 | 一 | 春上 |
| 52 | さきにほふ花のあたりは春なからたえせぬやとのみゆきとそみる さきにほふ はなのあたりは はるなから たえせぬやとの みゆきとそみる | 右衛門督基忠 | 一 | 春上 |
| 53 | たつねきてたをるさくらのあキふに花のたもとのぬれぬ日そなき たつねきて たをるさくらの あさつゆに はなのたもとの ぬれぬひそなき | 中院右のおほいまうちきみ | 一 | 春上 |
| 54 | かりにたにいとふ心やなからましちらぬ花さくこの世なりせは かりにたに いとふこころや なからまし ちらぬはなさく このよなりせは | 右大臣 | 一 | 春上 |
| 55 | みな人の心にそむるさくら花いくしほ年にいろまさるらん みなひとの こころにそむる さくらはな いくしほとしに いろまさるらむ | 前左衛門督公光 | 一 | 春上 |
| 56 | かつらきやたかまの山のさくら花雲井のよそにみてや過きなん かつらきや たかまのやまの さくらはな くもゐのよそに みてやすきなむ | 左京大夫顕輔 | 一 | 春上 |
| 57 | 山さくらかすみこめたるありかをはつらきものから風そしらする やまさくら かすみこめたる ありかをは つらきものから かせそしらする | 前参議教長 | 一 | 春上 |
| 58 | 神かきのみむろの山は春きてそ花のしらゆふかけてみえける かみかきの みむろのやまは はるきてそ はなのしらゆふ かけてみえける | 藤原清輔朝臣 | 一 | 春上 |
| 59 | よもすから花のにほひをおもひやる心やみねにたひねしつらん よもすから はなのにほひを おもひやる こころやみねに たひねしつらむ | 仁和寺後入道法親王(覚性) | 一 | 春上 |
| 60 | さきぬやとしらぬ山ちにたつねいるわれをは花のしをるなりけり さきぬやと しらぬやまちに たつねいる われをははなの しをるなりけり | 摂政前右大臣 | 一 | 春上 |
| 61 | くれはてぬかへさはおくれ山さくらたかためにきてまとふとかしる くれはてぬ かへさはおくれ やまさくら たかためにきて まとふとかしる | 源俊頼朝臣 | 一 | 春上 |
| 62 | 花ゆゑにしらぬ山路はなけれともまとふは春の心なりけり はなゆゑに しらぬやまちは なけれとも まとふははるの こころなりけり | 道因法師俗名(敦頼) | 一 | 春上 |
| 63 | としをへておなしさくらの花の色をそめます物は心なりけり としをへて おなしさくらの はなのいろを そめますものは こころなりけり | 藤原公時朝臣 | 一 | 春上 |
| 64 | 花さかりよもの山へにあくかれて春は心のみにそはぬかな はなさかり よものやまへに あくかれて はるはこころの みにそはぬかな | 藤原公衡朝臣 | 一 | 春上 |
| 65 | よし野川みかさはさしもまさらしをあをねをこすや花のしら浪 よしのかは みかさはさしも まさらしを あをねをこすや はなのしらなみ | 顕昭法師 | 一 | 春上 |
| 66 | ささ浪やしかのみやこはあれにしをむかしなからの山さくらかな ささなみや しかのみやこは あれにしを むかしなからの やまさくらかな | 読人知らず | 一 | 春上 |
| 67 | ささ浪や志賀の花そのみるたひにむかしの人の心をそしる ささなみや しかのはなその みるたひに むかしのひとの こころをそしる | 祝部宿禰成仲 | 一 | 春上 |
| 68 | たかさこのをのへの桜さきぬれはこすゑにかくるおきつ白浪 たかさこの をのへのさくら さきぬれは こすゑにかくる おきつしらなみ | 賀茂成保 | 一 | 春上 |
| 69 | おしなへて花のさかりに成りにけり山のはことにかかるしら雲 おしなへて はなのさかりに なりにけり やまのはことに かかるしらくも | 西行法師 | 一 | 春上 |
| 70 | 芳野やまはなのさかりになりぬれはたたぬ時なきみねのしら雲 よしのやま はなのさかりに なりぬれは たたぬときなき みねのしらくも | 藤原為業(法名寂念) | 一 | 春上 |
| 71 | 春をへてにほひをそふる山さくら花はおいこそさかりなりけれ はるをへて にほひをそふる やまさくら はなはおいこそ さかりなりけれ | 源仲正 | 一 | 春上 |
| 72 | しら雲とみねのさくらはみゆれとも月のひかりはへたてさりけり しらくもと みねのさくらは みゆれとも つきのひかりは へたてさりけり | 待賢門院堀河 | 一 | 春上 |
| 73 | 花の色にひかりさしそふはるの夜そこのまの月はみるへかりける はなのいろに ひかりさしそふ はるのよそ このまのつきは みるへかりける | 上西門院兵衛 | 一 | 春上 |
| 74 | をはつせの花のさかりをみわたせは霞にまかふみねのしら雲 をはつせの はなのさかりを みわたせは かすみにまかふ みねのしらくも | 太宰大弐重家 | 一 | 春上 |
| 75 | ささ浪やなからの山のみねつつきみせはや人に花のさかりを ささなみや なからのやまの みねつつき みせはやひとに はなのさかりを | 藤原範綱 | 一 | 春上 |
| 76 | 御よしのの花のさかりをけふみれはこしのしらねに春かせそふく みよしのの はなのさかりを けふみれは こしのしらねに はるかせそふく | 皇太后宮大夫俊成(法名釈河) | 一 | 春上 |
| 77 | さきしよりちるまてみれは木のもとに花も日かすもつもりぬるかな さきしより ちるまてみれは このもとに はなもひかすも つもりぬるかな | 白河院御製 | 二 | 春下 |
| 78 | いけ水にみきはのさくらちりしきて浪の花こそさかりなりけれ いけみつに みきはのさくら ちりしきて なみのはなこそ さかりなりけれ | 院御製 | 二 | 春下 |
| 79 | しら雲とみねにはみえてさくら花ちれはふもとの雪にそ有りける しらくもと みねにはみえて さくらはな ちれはふもとの ゆきにそありける | 大宮前のおほきおほいまうちきみ | 二 | 春下 |
| 80 | よし野やま花はなかはにちりにけりたえたえのこるみねのしら雲 よしのやま はなはなかはに ちりにけり たえたえのこる みねのしらくも | 藤原季通朝臣 | 二 | 春下 |
| 81 | 山さくらをしむこころのいくたひかちる木のもとにゆきかかるらん やまさくら をしむこころの いくたひか ちるこのもとに ゆきかかるらむ | 内侍周防 | 二 | 春下 |
| 82 | はるさめにちる花みれはかきくらしみそれし空の心ちこそすれ はるさめに ちるはなみれは かきくらし みそれしそらの ここちこそすれ | 大納言長家 | 二 | 春下 |
| 83 | ふめはをしふまてはゆかんかたもなし心つくしの山さくらかな ふめはをし ふまてはゆかむ かたもなし こころつくしの やまさくらかな | 上東門院赤染衛門 | 二 | 春下 |
| 84 | 山さくらちちに心のくたくるはちる花ことにそふにや有るらん やまさくら ちちにこころの くたくるは ちるはなことに そふにやあるらむ | 前中納言匡房 | 二 | 春下 |
| 85 | はなのちる木のしたかけはおのつからそめぬさくらの衣をそきる はなのちる このしたかけは おのつから そめぬさくらの ころもをそきる | 藤原仲実朝臣 | 二 | 春下 |
| 86 | 春をへて花ちらましやおく山のかせをさくらの心とおもはは はるをへて はなちらましや おくやまの かせをさくらの こころとおもはは | 藤原基俊 | 二 | 春下 |
| 87 | あらしふくしかの山辺のさくら花ちれは雲井にささ浪そたつ あらしふく しかのやまへの さくらはな ちれはくもゐに ささなみそたつ | 右兵衛督公行 | 二 | 春下 |
| 88 | 春かせに志賀の山こえ花ちれはみねにそうらの浪はたちける はるかせに しかのやまこえ はなちれは みねにそうらの なみはたちける | 前参議親隆 | 二 | 春下 |
| 89 | さくらさくひらの山かせ吹くままに花になりゆくしかのうら浪 さくらさく ひらのやまかせ ふくままに はなになりゆく しかのうらなみ | 左近中将良経 | 二 | 春下 |
| 90 | ちりかかる花のにしきはきたれともかへらむことそわすられにける ちりかかる はなのにしきは きたれとも かへらむことそ わすられにける | 右近大将実房 | 二 | 春下 |
| 91 | あかなくに袖につつめはちる花をうれしとおもふになりぬへきかな あかなくに そてにつつめは ちるはなを うれしとおもふに なりぬへきかな | 権大納言実国 | 二 | 春下 |
| 92 | さくら花うき身にかふるためしあらはいきてちるをはをしまさらまし さくらはな うきみにかふる ためしあらは いきてちるをは をしまさらまし | 権中納言通親 | 二 | 春下 |
| 93 | みよしのの山した風やはらふらむこすゑにかへる花のしら雪 みよしのの やましたかせや はらふらむ こすゑにかへる はなのしらゆき | 俊恵法師 | 二 | 春下 |
| 94 | ひとえたはをりてかへらむ山さくら風にのみやはちらしはつへき ひとえたは をりてかへらむ やまさくら かせにのみやは ちらしはつへき | 源有房 | 二 | 春下 |
| 95 | ちる花を身にかふはかりおもへともかなはてとしの老いにけるかな ちるはなを みにかふはかり おもへとも かなはてとしの おいにけるかな | 遣因法師 | 二 | 春下 |
| 96 | あかなくにちりぬる花のおもかけや風にしられぬさくらなるらん あかなくに ちりぬるはなの おもかけや かせにしられぬ さくらなるらむ | 賀盛法師 | 二 | 春下 |
| 97 | 山さくらちるをみてこそおもひしれたつねぬ人は心ありけり やまさくら ちるをみてこそ おもひしれ たつねぬひとは こころありけり | 源仲綱 | 二 | 春下 |
| 98 | よそにてそきくへかりけるさくら花めのまへにてもちらしつるかな よそにてそ きくへかりける さくらはな めのまへにても ちらしつるかな | 道命法師 | 二 | 春下 |
| 99 | さくらちる水のおもにはせきとむる花のしからみかくへかりけり さくらちる みつのおもには せきとむる はなのしからみ かくへかりけり | 能因法師 | 二 | 春下 |
| 100 | 山かせにちりつむ花のなかれすはいかてしらまし谷のした水 やまかせに ちりつむはなの なかれすは いかてしらまし たにのしたみつ | 花薗左大臣 | 二 | 春下 |
| 101 | 花のみなちりてののちそ山さとのはらはぬ庭はみるへかりける はなのみな ちりてののちそ やまさとの はらはぬにはは みるへかりける | 前大納言俊実 | 二 | 春下 |
| 102 | ふるさとは花こそいととしのはるれちりぬるのちはとふ人もなし ふるさとは はなこそいとと しのはるれ ちりぬるのちは とふひともなし | 藤原基俊 | 二 | 春下 |
| 103 | 吹くかせをなこそのせきとおもへともみちもせにちる山桜かな ふくかせを なこそのせきと おもへとも みちもせにちる やまさくらかな | 源義家朝臣 | 二 | 春下 |
| 104 | したさゆるひむろの山のおそさくらきえのこりける雪かとそみる したさゆる ひむろのやまの おそさくら きえのこりける ゆきかとそみる | 源仲正 | 二 | 春下 |
| 105 | かかみ山ひかりは花のみせけれはちりつみてこそさひしかりけれ かかみやま ひかりははなの みせけれは ちりつみてこそ さひしかりけれ | 前参議親隆 | 二 | 春下 |
| 106 | 心なきわか身なれとも津の国のなにはの春にたへすも有るかな こころなき わかみなれとも つのくにの なにはのはるに たへすもあるかな | 藤原季通朝臣 | 二 | 春下 |
| 107 | おもふことちえにやしけきよふこ鳥しのたのもりのかたに鳴くなり おもふこと ちえにやしけき よふことり しのたのもりの かたになくなり | 前中納言匡房 | 二 | 春下 |
| 108 | こよひねてつみてかへらむすみれ草をののしはふは露しけくとも こよひねて つみてかへらむ すみれくさ をののしはふは つゆしけくとも | 中納言国信 | 二 | 春下 |
| 109 | ききすなくいはたのをののつほすみれしめさすはかり成りにけるかな ききすなく いはたのをのの つほすみれ しめさすはかり なりにけるかな | 修埋大夫顕季 | 二 | 春下 |
| 110 | 道とほみいる野の原のつほすみれ春のかたみにつみてかへらん みちとほみ いるののはらの つほすみれ はるのかたみに つみてかへらむ | 源顕国 | 二 | 春下 |
| 111 | はるふかみ井ての河水かけそははいくへかみえむ山ふきのはな はるふかみ ゐてのかはみつ かけそはは いくへかみえむ やまふきのはな | 前中納言匡房 | 二 | 春下 |
| 112 | 山ふきのはなさきにけりかはつなくゐてのさと人いまや問はまし やまふきの はなさきにけり かはつなく ゐてのさとひと いまやとはまし | 藤原基俊 | 二 | 春下 |
| 113 | ここのへにやへ山ふきをうつしてはゐてのかはつの心をそくむ ここのへに やへやまふきを うつしては ゐてのかはつの こころをそくむ | 二条太皇大后宮肥後 | 二 | 春下 |
| 114 | よし野川きしのやまふきさきぬれはそこにそふかき色はみえける よしのかは きしのやまふき さきぬれは そこにそふかき いろはみえける | 藤原範綱 | 二 | 春下 |
| 115 | くちなしの色にそすめる山ふきの花のしたゆくゐ手のかはみつ くちなしの いろにそすめる やまふきの はなのしたゆく ゐてのかはみつ | 藤原定経 | 二 | 春下 |
| 116 | いかなれは春をかさねてみつれともやへにのみさく山吹のはな いかなれは はるをかさねて みつれとも やへにのみさく やまふきのはな | 惟宗広言 | 二 | 春下 |
| 117 | やまふきの花のつまとはきかねともうつろふなへに鳴くかはつかな やまふきの はなのつまとは きかねとも うつろふなへに なくかはつかな | 藤原清輔朝臣 | 二 | 春下 |
| 118 | いつかたににほひますらむふちの花はると夏とのきしをへたてて いつかたに にほひますらむ ふちのはな はるとなつとの きしをへたてて | 康資王母 | 二 | 春下 |
| 119 | ここのへにさけるをみれはふちの花こきむらさきの雲そたちける ここのへに さけるをみれは ふちのはな こきむらさきの くもそたちける | 中納言祐家 | 二 | 春下 |
| 120 | としふれとかはらぬ松をたのみてやかかりそめけんいけの藤なみ としふれと かはらぬまつを たのみてや かかりそめけむ いけのふちなみ | 大炊御門右大臣 | 二 | 春下 |
| 121 | われもまた春とともにやかへらましあすはかりをはここにくらして われもまた はるとともにや かへらまし あすはかりをは ここにくらして | 二条院御製 | 二 | 春下 |
| 122 | 花はねに鳥はふるすにかへるなり春のとまりをしる人そなき はなはねに とりはふるすに かへるなり はるのとまりを しるひとそなき | 崇徳院御製 | 二 | 春下 |
| 123 | いのちあらは又もあひなむ春なれとしのひかたくてくらすけふかな いのちあらは またもあひみむ はるなれと しのひかたくて くらすけふかな | 中務卿具平のみこ | 二 | 春下 |
| 124 | なかむれはおもひやるへきかたそなき春のかきりの夕くれのそら なかむれは おもひやるへき かたそなき はるのかきりの ゆふくれのそら | 式子内親王 | 二 | 春下 |
| 125 | くれてゆく春はのこりもなきものををしむ心のつきせさるらん くれてゆく はるはのこりも なきものを をしむこころの つきせさるらむ | 大納言隆季 | 二 | 春下 |
| 126 | いり日さす山のはさヘそうらめしきくれすは春のかへらましやは いりひさす やまのはさへそ うらめしき くれすははるの かへらましやは | 久我内のおほいまうちきみ | 二 | 春下 |
| 127 | いくかへりけふにわか身のあひぬらんをしきは春のすくるのみかは いくかへり けふにわかみの あひぬらむ をしきははるの すくるのみかは | 藤原定成 | 二 | 春下 |
| 128 | 身のうさも花みしほとはわすられき春のわかれをなけくのみかは みのうさも はなみしほとは わすられき はるのわかれを なけくのみかは | 源仲綱 | 二 | 春下 |
| 129 | いつかたと春のゆくへはしらねともをしむ心のさきにたつらん いつかたと はるのゆくへは しらねとも をしむこころの さきにたつらむ | 藤原経家朝臣 | 二 | 春下 |
| 130 | もろともにおなしみやこは出てしかとつひには春にわかれぬるかな もろともに おなしみやこは いてしかと つひにははるに わかれぬるかな | 琳賢法師 | 二 | 春下 |
| 131 | 花はみなよものあらしにさそはれてひとりや春のけふはゆくらん はなはみな よものあらしに さそはれて ひとりやはるの けふはゆくらむ | 法印静賢 | 二 | 春下 |
| 132 | はなのはるかさなるかひそなかりけるちらぬ日かすのそははこそあらめ はなのはる かさなるかひそ なかりける ちらぬひかすの そははこそあらめ | 権大僧都範玄 | 二 | 春下 |
| 133 | をしめともかひもなきさに春くれて浪とともにそたちわかれぬる をしめとも かひもなきさに はるくれて なみとともにそ たちわかれぬる | 前大僧正覚忠 | 二 | 春下 |
| 134 | つねよりもけふのくるるををしむかないまいくたひの春としらねは つねよりも けふのくるるを をしむかな いまいくたひの はるとしらねは | 前中納言匡房 | 二 | 春下 |
| 135 | けふくれぬはなのちりしもかくそありし二たひ春は物をおもふよ けふくれぬ はなのちりしも かくそありし ふたたひはるは ものをおもふよ | 河内 | 二 | 春下 |
| 136 | 夏ころもはなのたもとにぬきかへて春のかたみもとまらさりけり なつころも はなのたもとに ぬきかへて はるのかたみも とまらさりけり | 前中納言匡房 | 三 | 夏 |
| 137 | けふかふるせみの羽ころもきてみれはたもとに夏はたつにそ有りける けふかふる せみのはころも きてみれは たもとになつは たつにそありける | 藤原基俊 | 三 | 夏 |
| 138 | あかてゆく春のわかれにいにしへの人やうつきといひはしめけん あかてゆく はるのわかれに いにしへの ひとやうつきと いひはしめけむ | 藤原実清朝臣 | 三 | 夏 |
| 139 | むらむらにさけるかきねの卯のはなはこのまの月の心ちこそすれ むらむらに さけるかきねの うのはなは このまのつきの ここちこそすれ | 左京大夫顕輔 | 三 | 夏 |
| 140 | ゆふつくよほのめく影もうの花のさけるわたりはさやけかりけり ゆふつくよ ほのめくかけも うのはなの さけるわたりは さやけかりけり | 右近大将実房 | 三 | 夏 |
| 141 | 玉川とおとにききしは卯花を露のかきれる名にこそ有りけれ たまかはと おとにききしは うのはなを つゆのかされる なにこそありけれ | 仁和寺後入道法親王(覚性) | 三 | 夏 |
| 142 | みてすくる人しなけれは卯のはなのさけるかきねや白川の関 みてすくる ひとしなけれは うのはなの さけるかきねや しらかはのせき | 藤原季通朝臣 | 三 | 夏 |
| 143 | 卯のはなのよそめなりけり山さとのかきねはかりにふれるしら雪 うのはなの よそめなりけり やまさとの かきねはかりに ふれるしらゆき | 賀茂政平 | 三 | 夏 |
| 144 | うの花のかきねとのみやおもはまししつのふせやに煙たたすは うのはなの かきねとのみや おもはまし しつのふせやに けふりたたすは | 藤原敦経朝臣 | 三 | 夏 |
| 145 | やきすてしふるののを野のまくすはら玉まくはかり成りにけるかな やきすてし ふるののをのの まくすはら たままくはかり なりにけるかな | 藤原定通 | 三 | 夏 |
| 146 | あふひ草てる日は神のこころかはかけさすかたにまつなひくらん あふひくさ てるひはかみの こころかは かけさすかたに まつなひくらむ | 藤原基俊 | 三 | 夏 |
| 147 | 神山のふもとになれしあふひ草ひきわかれても年そへにける かみやまの ふもとになれし あふひくさ ひきわかれても としそへにける | 前斎院式子内親王 | 三 | 夏 |
| 148 | ほとときすまつはひさしき夏のよをねぬにあけぬと誰かいひけん ほとときす まつはひさしき なつのよを ねぬにあけぬと たれかいひけむ | 按察使公通 | 三 | 夏 |
| 149 | ふたこゑときかてややまむ時鳥まつにねぬ夜のかすはつもりて ふたこゑと きかてややまむ ほとときす まつにねぬよの かすはつもりて | 藤原道経 | 三 | 夏 |
| 150 | ほとときすしのふるころは山ひこのこたふる声もほのかにそする ほとときす しのふるころは やまひこの こたふるこゑも ほのかにそする | 賀茂重保 | 三 | 夏 |
| 151 | あやしきはまつ人からかほとときすなかぬにさへもぬるる袖かな あやしきは まつひとからか ほとときす なかぬにさへも ぬるるそてかな | 道命法師 | 三 | 夏 |
| 152 | ねさめするたよりにきけは郭公つらき人をも待つへかりけり ねさめする たよりにきけは ほとときす つらきひとをも まつへかりけり | 康資王母 | 三 | 夏 |
| 153 | ほとときす又もやなくとまたれつつきく夜しもこそねられさりけれ ほとときす またもやなくと またれつつ きくよしもこそ ねられさりけれ | 刑部卿頼輔母 | 三 | 夏 |
| 154 | またてきく人にとははや郭公さてもはつねやうれしかるらん またてきく ひとにとははや ほとときす さてもはつねや うれしかるらむ | 覚盛法師 | 三 | 夏 |
| 155 | たつねてもきくへきものを時鳥人たのめなる夜はの一声 たつねても きくへきものを ほとときす ひとたのめなる よはのひとこゑ | 前参議教長 | 三 | 夏 |
| 156 | おもひやる心もつきぬほとときす雲のいくへの外になくらん おもひやる こころもつきぬ ほとときす くものいくへの ほかになくらむ | 権大納言実家 | 三 | 夏 |
| 157 | ほとときすなほはつこゑをしのふ山ゆふゐる雲のそこに鳴くなり ほとときす なほはつこゑを しのふやま ゆふゐるくもの そこになくなり | 仁和寺法親王(守覚) | 三 | 夏 |
| 158 | かさこしをゆふこえくれはほとときすふもとの雲のそこに鳴くなり かさこしを ゆふこえくれは ほとときす ふもとのくもの そこになくなり | 藤原清輔朝臣 | 三 | 夏 |
| 159 | ひとこゑはさやかに鳴きてほとときす雲ちはるかにとほさかるなり ひとこゑは さやかになきて ほとときす くもちはるかに とほさかるなり | 前右京権大夫頼政 | 三 | 夏 |
| 160 | おもふことなき身なりせはほとときす夢にきく夜もあらましものを おもふこと なきみなりせは ほとときす ゆめにきくよも あらましものを | 摂政前右大臣 | 三 | 夏 |
| 161 | ほとときす鳴きつるかたをなかむれはたたあり明の月そのこれる ほとときす なきつるかたを なかむれは たたありあけの つきそのこれる | 右のおほいまうちきみ | 三 | 夏 |
| 162 | なこりなくすきぬなるかなほとときすこそかたらひしやととしらすや なこりなく すきぬなるかな ほとときす こそかたらひし やととしらすや | 権大納言実国 | 三 | 夏 |
| 163 | 夕つくよいるさの山のこかくれにほのかにもなくほとときすかな ゆふつくよ いるさのやまの こかくれに ほのかにもなく ほとときすかな | 権大納言宗家 | 三 | 夏 |
| 164 | ほとときすききもわかれぬ一こゑによものそらをもなかめつるかな ほとときす ききもわかれぬ ひとこゑに よものそらをも なかめつるかな | 前左衡門督公光 | 三 | 夏 |
| 165 | すきぬるか夜はのねさめの時鳥こゑはまくらにある心ちして すきぬるか よはのねさめの ほとときす こゑはまくらに あるここちして | 皇太后宮大夫俊成 | 三 | 夏 |
| 166 | よをかさねねぬよりほかにほとときすいかに待ちてか二こゑはきく よをかさね ねぬよりほかに ほとときす いかにまちてか ひとこゑはきく | 道因法師 | 三 | 夏 |
| 167 | 心をそつくしはてつるほとときすほのめくよひの村雨のそら こころをそ つくしはてつる ほとときす ほのめくよひの むらさめのそら | 権中納言長方 | 三 | 夏 |
| 168 | みやこ人ひきなつくしそあやめ草たひねのとこの枕はかりは みやこひと ひきなつくしそ あやめくさ たひねのとこの まくらはかりは | 前中納言雅頼 | 三 | 夏 |
| 169 | さみたれにぬれぬれひかむあやめ草ぬまのいはかき浪もこそこせ さみたれに ぬれぬれひかむ あやめくさ ぬまのいはかき なみもこそこせ | 摂政前右大臣 | 三 | 夏 |
| 170 | のきちかくけふしもきなく郭公ねをやあやめにそへてふくらん のきちかく けふしもきなく ほとときす ねをやあやめに そへてふくらむ | 内大臣 | 三 | 夏 |
| 171 | たたならぬ花たちはなのにほひかなよそふる袖はたれとなけれと たたならぬ はなたちはなの にほひかな よそふるそては たれとなけれと | 枇杷殿皇太后宮五節 | 三 | 夏 |
| 172 | 風にちるはなたちはなに袖しめてわかおもふいもか手枕にせん かせにちる はなたちはなに そてしめて わかおもふいもか たまくらにせむ | 藤原基俊 | 三 | 夏 |
| 173 | うき雲のいさよふよひの村雨におひ風しるくにほふたちはな うきくもの いさよふよひの むらさめに おひかせしるく にほふたちはな | 藤原家基 | 三 | 夏 |
| 174 | わかやとの花たちはなにふく風をたか里よりとたれなかむらん わかやとの はなたちはなに ふくかせを たかさとよりと たれなかむらむ | 左大弁親宗 | 三 | 夏 |
| 175 | をりしもあれ花たちはなのかをるかなむかしをみつる夢の枕に をりしもあれ はなたちはなの かをるかな むかしをみつる ゆめのまくらに | 藤原公衡朝臣 | 三 | 夏 |
| 176 | 五月雨にはなたちはなのかをる夜は月すむ秋もさもあらはあれ さみたれに はなたちはなの かをるよは つきすむあきも さもあらはあれ | 崇徳院御製 | 三 | 夏 |
| 177 | さみたれにおもひこそやれいにしへの草のいほりの夜はのさひしさ さみたれに おもひこそやれ いにしへの くさのいほりの よはのさひしさ | 延久三親王輔仁 | 三 | 夏 |
| 178 | いととしくしつのいほりのいふせきに卯のはなくたし五月雨そする いととしく しつのいほりの いふせきに うのはなくたし さみたれそふる | 藤原基俊 | 三 | 夏 |
| 179 | おほつかないつかはるへきわひ人のおもふ心やさみたれの空 おほつかな いつかはるへき わひひとの おもふこころや さみたれのそら | 源俊頼朝臣 | 三 | 夏 |
| 180 | 五月雨にあささはぬまの花かつみかつみるままにかくれゆくかな さみたれに あささはぬまの はなかつみ かつみるままに かくれゆくかな | 藤原顕仲朝臣 | 三 | 夏 |
| 181 | さみたれの日かすへぬれはかりつみししつやのこすけくちやしぬらん さみたれの ひかすへぬれは かりつみし しつやのこすけ くちやしぬらむ | 左京大夫顕輔 | 三 | 夏 |
| 182 | 五月雨にみつのみつかさまさるらしみをのしるしもみえすなりゆく さみたれに みつのみつかさ まさるらし みをのしるしも みえすなりゆく | 前参議親隆 | 三 | 夏 |
| 183 | さみたれはたくもの煙うちしめりしほたれまさるすまのうら人 さみたれは たくものけふり うちしめり しほたれまさる すまのうらひと | 皇太后宮大夫俊成 | 三 | 夏 |
| 184 | 時しもあれ水のみこもをかりあけてほさてくたしつ五月雨のそら ときしもあれ みつのみこもを かりあけて ほさてくたしつ さみたれのそら | 藤原清輔朝臣 | 三 | 夏 |
| 185 | さみたれはあまのもしほ木くちにけりうらへに煙たえてほとへぬ さみたれは あまのもしほき くちにけり うらへにけふり たえてほとへぬ | 待賢門院安芸 | 三 | 夏 |
| 186 | 五月雨にむろの八島をみわたせは煙はなみのうへよりそたつ さみたれに むろのやしまを みわたせは けふりはなみの うへよりそたつ | 源行頼朝臣 | 三 | 夏 |
| 187 | さみたれはとまのしつくに袖ぬれてあなしほとけの浪のうきねや さみたれは とまのしつくに そてぬれて あなしほとけの なみのうきねや | 源仲正 | 三 | 夏 |
| 188 | 五月雨の雲のはれまに月さえて山ほとときす空に鳴くなり さみたれの くものはれまに つきさえて やまほとときす そらになくなり | 賀茂成保 | 三 | 夏 |
| 189 | をちかへりぬるともきなけ郭公いまいくかかはさみたれのそら をちかへり ぬるともきなけ ほとときす いまいくかかは さみたれのそら | 按察使資賢 | 三 | 夏 |
| 190 | あふさかの山ほとときすなのるなりせきもる神やそらにとふらん あふさかの やまほとときす なのるなり せきもるかみや そらにとふらむ | 中納言師時 | 三 | 夏 |
| 191 | いにしへを恋ひつつひとりこえくれはなきあふ山のほとときすかな いにしへを こひつつひとり こえくれは なきあふやまの ほとときすかな | 律師慶暹 | 三 | 夏 |
| 192 | なとてかくおもひそめけん時鳥ゆきのみやまの法のすゑかは なとてかく おもひそめけむ ほとときす ゆきのみやまの のりのすゑかは | 源俊頼朝臣 | 三 | 夏 |
| 193 | 五月やみふたむら山のほとときす嶺つつきなくこゑをきくかな さつきやみ ふたむらやまの ほとときす みねつつきなく こゑをきくかな | 権中納言俊忠 | 三 | 夏 |
| 194 | ともしするみやきか原のした露にしのふもちすりかわくよそなき ともしする みやきかはらの したつゆに しのふもちすり かわくよそなき | 前中納言匡房 | 三 | 夏 |
| 195 | 五月やみさやまの嶺にともす火は雲のたえまのほしかとそみる さつきやみ さやまのみねに ともすひは くものたえまの ほしかとそみる | 修埋大夫顕季 | 三 | 夏 |
| 196 | さつきやみしけきは山にたつしかはともしにのみそ人にしらるる さつきやみ しけきはやまに たつしかは ともしにのみそ ひとにしらるる | 藤原顕綱朝臣 | 三 | 夏 |
| 197 | ともしするほくしの松もきえなくにと山の雲のあけわたるらん ともしする ほくしのまつも きえなくに とやまのくもの あけわたるらむ | 大蔵卿行宗 | 三 | 夏 |
| 198 | ともしするほくしの松ももえつきてかへるにまよふしもつやみかな ともしする ほくしのまつも もえつきて かへるにまよふ しもつやみかな | 源仲正 | 三 | 夏 |
| 199 | 山ふかみほくしのまつはつきぬれとしかにおもひをなほかくるかな やまふかみ ほくしのまつは つきぬれと しかにおもひを なほかくるかな | 読人知らず | 三 | 夏 |
| 200 | ともしするほくしをまつとおもへはやあひみてしかの身をはかふらん ともしする ほくしをまつと おもへはや あひみてしかの みをはかふらむ | 賀茂重保 | 三 | 夏 |
| 201 | むかしわかあつめしものをおもひいててみなれかほにもくる蛍かな むかしわか あつめしものを おもひいてて みなれかほにも くるほたるかな | 藤原季通朝臣 | 三 | 夏 |
| 202 | あはれにもみさをにもゆる蛍かなこゑたてつへきこの世とおもふに あはれにも みさをにもゆる ほたるかな こゑたてつへき このよとおもふに | 源俊頼朝臣 | 三 | 夏 |
| 203 | あさりせし水のみさひにとちられてひしのうきはにかはつなくなり あさりせし みつのみさひに とちられて ひしのうきはに かはつなくなり | 源俊頼朝臣 | 三 | 夏 |
| 204 | 夏ふかみ玉えにしけるあしの葉のそよくや船のかよふなるらん なつふかみ たまえにしける あしのはの そよくやふねの かよふなるらむ | 法性寺入道前太政大臣 | 三 | 夏 |
| 205 | はやせ川みをさかのはるうかひ舟まつこの世にもいかかくるしき はやせかは みをさかのほる うかひふね まつこのよにも いかかくるしき | 崇徳院御製 | 三 | 夏 |
| 206 | みるかなほこの世の物とおほえぬはからなてしこの花にそ有りける みるかなほ このよのものと おほえぬは からなてしこの はなにそありける | 和泉式部 | 三 | 夏 |
| 207 | とこ夏のはなもわすれて秋かせを松のかけにてけふは暮れぬる とこなつの はなもわすれて あきかせを まつのかけにて けふはくれぬる | 中務卿具平親王 | 三 | 夏 |
| 208 | 春あきものちのかたみはなきものをひむろそ冬のなこりなりける はるあきも のちのかたみは なきものを ひむろそふゆの なこりなりける | 仁和寺後入道法親王(覚性) | 三 | 夏 |
| 209 | あたりさへすすしかりけりひむろ山まかせし水のこほるのみかは あたりさへ すすしかりけり ひむろやま まかせしみつの こほるのみかは | 大炊御門右大臣 | 三 | 夏 |
| 210 | 山かけやいはもるし水おとさえて夏のほかなるひくらしのこゑ やまかけや いはもるしみつ おとさへて なつのほかなる ひくらしのこゑ | 法印慈円 | 三 | 夏 |
| 211 | 夕されは玉ゐるかすもみえねともせきのを川のおとそすすしき ゆふされは たまゐるかすも みえねとも せきのをかはの おとそすすしき | 藤原道経 | 三 | 夏 |
| 212 | いはまもるし水をやとにせきとめてほかより夏をすくしつるかな いはまもる しみつをやとに せきとめて ほかよりなつを すくしつるかな | 俊恵法師 | 三 | 夏 |
| 213 | さらぬたにひかりすすしき夏の夜の月をし水にやとしてそみる さらぬたに ひかりすすしき なつのよの つきをしみつに やとしてそみる | 顕昭法師 | 三 | 夏 |
| 214 | せきとむる山した水にみかくれてすみけるものを秋のけしきは せきとむる やましたみつに みかくれて すみけるものを あきのけしきは | 法眼実快 | 三 | 夏 |
| 215 | われなからほとなき夜はやをしからむなほ山のはにあり明の月 われなから ほとなきよはや をしからむ なほやまのはに ありあけのつき | 藤原経家朝臣 | 三 | 夏 |
| 216 | 夏のよの月のひかりはさしなからいかにあけぬるあまの戸ならん なつのよの つきのひかりは さしなから いかにあけぬる あまのとならむ | 祝部宿禰成仲 | 三 | 夏 |
| 217 | 夕たちのまたはれやらぬ雲まよりおなし空ともみえぬ月かな ゆふたちの またはれやらぬ くもまより おなしそらとも みえぬつきかな | 俊恵法師 | 三 | 夏 |
| 218 | 小萩はらまた花さかぬみやきののしかやこよひの月になくらん こはきはら またはなさかぬ みやきのの しかやこよひの つきになくらむ | 藤原敦仲 | 三 | 夏 |
| 219 | 夏ころもすそのの原をわけゆけはおりたかへたる萩か花すり なつころも すそののはらを わけゆけは をりたかへたる はきかはなすり | 顕昭法師 | 三 | 夏 |
| 220 | あきかせは浪とともにやこえぬらんまたきすすしきすゑの松山 あきかせは なみとともにや こえぬらむ またきすすしき すゑのまつやま | 藤原親盛 | 三 | 夏 |
| 221 | いはたたく谷の水のみおとつれて夏にしられぬみ山へのさと いはたたく たにのみつのみ おとつれて なつにしられぬ みやまへのさと | 前参議教長 | 三 | 夏 |
| 222 | いはまよりおちくるたきのしら糸はむすはてみるもすすしかりけり いはまより おちくるたきの しらいとは むすはてみるも すすしかりけり | 藤原盛方朝臣 | 三 | 夏 |
| 223 | けふくれはあさのたちえにゆふかけて夏みな月のみそきをそする けふくれは あさのたちえに ゆふかけて なつみなつきの みそきをそする | 藤原季通朝臣 | 三 | 夏 |
| 224 | いつとてもをしくやはあらぬとし月をみそきにすつる夏のくれかな いつとても をしくやはあらぬ としつきを みそきにすつる なつのくれかな | 皇太后宮大夫俊成 | 三 | 夏 |
| 225 | みそきする川せにさよやふけぬらんかへるたもとに秋かせそふく みそきする かはせにさよや ふけぬらむ かへるたもとに あきかせそふく | 読人知らず | 三 | 夏 |
| 226 | あききぬとききつるからにわかやとの荻のはかせの吹きかはるらん あききぬと ききつるからに わかやとの をきのはかせの ふきかはるらむ | 侍従乳母 | 四 | 秋上 |
| 227 | あさちふの露けくもあるか秋きぬとめにはさやかにみえけるものを あさちふの つゆけくもあるか あききぬと めにはさやかに みえけるものを | 仁和寺法親王(守覚) | 四 | 秋上 |
| 228 | 秋のくるけしきのもりのした風にたちそふ物はあはれなりけり あきのくる けしきのもりの したかせに たちそふものは あはれなりけり | 待賢門院堀川 | 四 | 秋上 |
| 229 | やへむくらさしこもりにしよもきふにいかてか秋のわけてきつらん やへむくら さしこもりにし よもきふに いかてかあきの わけてきつらむ | 皇太后宮大夫俊成 | 四 | 秋上 |
| 230 | 秋はきぬとしもなかはにすきぬとや荻ふくかせのおとろかすらん あきはきぬ としもなかはに すきぬとや をきふくかせの おとろかすらむ | 寂然法師 | 四 | 秋上 |
| 231 | この葉たに色つくほとはあるものを秋かせふけはちる涙かな このはたに いろつくほとは あるものを あきかせふけは ちるなみたかな | 読人知らず | 四 | 秋上 |
| 232 | 神山の松ふくかせもけふよりは色はかはらておとそ身にしむ かみやまの まつふくかせも けふよりは いろはかはらて おとそみにしむ | 賀茂重政 | 四 | 秋上 |
| 233 | 物ことにあきのけしきはしるけれとまつ身にしむは荻のうは風 ものことに あきのけしきは しるけれと まつみにしむは をきのうはかせ | 大蔵卿行宗 | 四 | 秋上 |
| 234 | あきかせや涙もよほすつまならむおとつれしより袖のかわかぬ あきかせや なみたもよほす つまならむ おとつれしより そてのかわかぬ | 源俊頼朝臣 | 四 | 秋上 |
| 235 | たなはたの心のうちやいかならむまちこしけふの夕くれのそら たなはたの こころのうちや いかならむ まちこしけふの ゆふくれのそら | 摂政前右大臣 | 四 | 秋上 |
| 236 | たなはたのあまつひれふく秋かせにやそのふなつをみふねいつらし たなはたの あまつひれふく あきかせに やそのふなつを みふねいつらし | 大納言隆季 | 四 | 秋上 |
| 237 | たなはたのあまのはころもかさねてもあかぬ契やなほむすふらん たなはたの あまのはころも かさねても あかぬちきりや なほむすふらむ | 二条太皇太后宮肥後 | 四 | 秋上 |
| 238 | こひこひてこよひはかりやたなはたの枕にちりのつもらさるらん こひこひて こよひはかりや たなはたの まくらにちりの つもらさるらむ | 河内 | 四 | 秋上 |
| 239 | 七夕のあまのかはらのいはまくらかはしもはてすあけぬこの夜は たなはたの あまのかはらの いはまくら かはしもはてす あけぬこのよは | 源俊頼朝臣 | 四 | 秋上 |
| 240 | たなはたに花そめころもぬきかせはあか月露のかへすなりけり たなはたに はなそめころも ぬきかせは あかつきつゆの かくすなりけり | 崇徳院御製 | 四 | 秋上 |
| 241 | あまの川心をくみておもふにも袖こそぬるれ暁のそら あまのかは こころをくみて おもふにも そてこそぬるれ あかつきのそら | 土御門右のおほいまうちきみ | 四 | 秋上 |
| 242 | 秋くれはおもひみたるるかるかやのした葉や人の心なるらん あきくれは おもひみたるる かるかやの したはやひとの こころなるらむ | 大納言師頼 | 四 | 秋上 |
| 243 | おしなへて草はのうへをふく風にまつしたをるる野へのかるかや おしなへて くさはのうへを ふくかせに まつしたをるる のへのかるかや | 延久三親王家甲斐 | 四 | 秋上 |
| 244 | ふみしたきあさゆくしかやすきつらむしとろにみゆる野ちのかるかや ふみしたき あさゆくしかや すきつらむ しとろにみゆる のちのかるかや | 藤原道経 | 四 | 秋上 |
| 245 | 秋きぬとかせもつけてし山さとになほほのめかす花すすきかな あききぬと かせもつけてし やまさとに なほほのめかす はなすすきかな | 法印静賢 | 四 | 秋上 |
| 246 | いかなれはうははをわたる秋かせにしたをれすらむ野へのかるかや いかなれは うははをわたる あきかせに したをれすらむ のへのかるかや | 読人知らず | 四 | 秋上 |
| 247 | 人もかなみせもきかせも萩の花さく夕かけのひくらしのこゑ ひともかな みせもきかせも はきのはな さくゆふかけの ひくらしのこゑ | 和泉式部 | 四 | 秋上 |
| 248 | あき山のふもとをこむる家ゐにはすそ野のはきそまかきなりける あきやまの ふもとをこむる いへゐには すそののはきそ まかきなりける | 藤原伊家 | 四 | 秋上 |
| 249 | 宮城ののはきやをしかのつまならん花さきしより声の色なる みやきのの はきやをしかの つまならむ はなさきしより こゑのいろなる | 藤原基俊 | 四 | 秋上 |
| 250 | 心をはちくさの色にそむれとも袖にうつるは萩かはなすり こころをは ちくさのいろに そむれとも そてにうつるは はきかはなすり | 長覚法師 | 四 | 秋上 |
| 251 | 露しけきあしたのはらのをみなへしひとえたをらん袖はぬるとも つゆしけき あしたのはらの をみなへし ひとえたをらむ そてはぬるとも | 大納言師順 | 四 | 秋上 |
| 252 | をみなへしなひくをみれは秋かせの吹きくるすゑもなつかしきかな をみなへし なひくをみれは あきかせの ふきくるすゑも なつかしきかな | 前中納言雅兼 | 四 | 秋上 |
| 253 | 女郎花涙に露やおきそふるたをれはいとと袖のしをるる をみなへし なみたにつゆや おきそふる たをれはいとと そてのしをるる | 前左衛門督公光 | 四 | 秋上 |
| 254 | ふく風にをれふしぬれはをみなへしまかきそ花の枕なりける ふくかせに をれふしぬれは をみなへし まかきそはなの まくらなりける | 藤原行家 | 四 | 秋上 |
| 255 | 夕されはかやかしけみになきかはすむしのねをさへわけつつそ行く ゆふされは かやかしけみに なきかはす むしのねをさへ わけつつそゆく | 藤原盛方朝臣 | 四 | 秋上 |
| 256 | さまさまに心そとまるみやき野の花のいろいろむしのこゑこゑ さまさまに こころそとまる みやきのの はなのいろいろ むしのこゑこゑ | 源俊頼朝臣 | 四 | 秋上 |
| 257 | 秋くれはやとにとまるをたひねにて野へこそつねのすみかなりけれ あきくれは やとにとまるを たひねにて のへこそつねの すみかなりけれ | 源俊頼朝臣 | 四 | 秋上 |
| 258 | 野わきするのへのけしきをみる時は心なき人あらしとそおもふ のわきする のへのけしきを みるときは こころなきひと あらしとそおもふ | 藤原季通朝臣 | 四 | 秋上 |
| 259 | 夕されは野へのあきかせ身にしみてうつら鳴くなりふか草のさと ゆふされは のへのあきかせ みにしみて うつらなくなり ふかくさのさと | 皇太后宮大夫俊成 | 四 | 秋上 |
| 260 | なにとなく物そかなしきすかはらやふしみのさとの秋の夕くれ なにとなく ものそかなしき すかはらや ふしみのさとの あきのゆふくれ | 源俊頼朝臣 | 四 | 秋上 |
| 261 | さまさまの花をはやとにうつしうゑつしかのねさそへ野への秋風 さまさまの はなをはやとに うつしうゑつ しかのねさそへ のへのあきかせ | 摂政前右大臣 | 四 | 秋上 |
| 262 | 秋のののちくさの色にうつろへは花そかへりて露をそめける あきののの ちくさのいろに うつろへは はなそかへりて つゆをそめける | 仁和寺法親王(守覚) | 四 | 秋上 |
| 263 | 草木まて秋のあはれをしのへはや野にも山にもつゆこはるらん くさきまて あきのあはれを しのへはや のにもやまにも つゆこほるらむ | 法印慈円 | 四 | 秋上 |
| 264 | はかなさをわか身のうへによそふれはたもとにかかる秋の夕露 はかなさを わかみのうへに よそふれは たもとにかかる あきのゆふつゆ | 待賢門院堀河 | 四 | 秋上 |
| 265 | たつたひめかさしの玉のををよわみみたれにけりとみゆるしら露 たつたひめ かさしのたまの ををよわみ みたれにけりと みゆるしらつゆ | 藤原清輔朝臣 | 四 | 秋上 |
| 266 | 夕まくれをきふくかせのおときけはたもとよりこそ露はこはるれ ゆふまくれ をきふくかせの おときけは たもとよりこそ つゆはこほるれ | 藤原季経朝臣 | 四 | 秋上 |
| 267 | おほかたの露にはなにのなるならむたもとにおくは涙なりけり おほかたの つゆにはなにの なるならむ たもとにおくは なみたなりけり | 西行法師 | 四 | 秋上 |
| 268 | 花すすきまねくはさかとしりなからととまる物は心なりけり はなすすき まねくはさかと しりなから ととまるものは こころなりけり | 道命法師 | 四 | 秋上 |
| 269 | 時しもあれ秋ふるさとにきてみれは庭は野へともなりにけるかな ときしもあれ あきふるさとに きてみれは にははのへとも なりにけるかな | 前大納言公任 | 四 | 秋上 |
| 270 | やとかれていくかもあらぬにしかのなく秋ののへともなりにけるかな やとかれて いくかもあらぬに しかのなく あきののへとも なりにけるかな | 小弁 | 四 | 秋上 |
| 271 | いまはしもほにいてぬらむ東路のいはたのをののしののをすすき いまはしも ほにいてぬらむ あつまちの いはたのをのの しののをすすき | 藤原伊家 | 四 | 秋上 |
| 272 | 夕されはをののあさちふ玉ちりて心くたくる風のおとかな ゆふされは をののあさちふ たまちりて こころくたくる かせのおとかな | 摂政前右大臣 | 四 | 秋上 |
| 273 | ときはなるあをはの山も秋くれは色こそかへねさひしかりけり ときはなる あをはのやまも あきくれは いろこそかへね さひしかりけり | 前大僧正覚忠 | 四 | 秋上 |
| 274 | 秋のよの心をつくすはしめとてほのかにみゆる夕つくよかな あきのよの こころをつくす はしめとて ほのかにみゆる ゆふつくよかな | 権大納言実家 | 四 | 秋上 |
| 275 | あきの月たかねの雲のあなたにてはれゆく空のくるるまちけり あきのつき たかねのくもの あなたにて はれゆくそらの くるるまちけり | 法性寺入道前太政大臣 | 四 | 秋上 |
| 276 | こからしの雲ふきはらふたかねよりさえても月のすみのほるかな こからしの くもふきはらふ たかねより さえてもつきの すみのほるかな | 源俊頼朝臣 | 四 | 秋上 |
| 277 | いつこにも月はわかしをいかなれはさやけかるらむさらしなのやま いつこにも つきはわかしを いかなれは さやけかるらむ さらしなのやま | 隆源法師 | 四 | 秋上 |
| 278 | 出てぬより月みよとこそさえにけれをはすて山のゆふくれの空 いてぬより つきみよとこそ さえにけれ をはすてやまの ゆふくれのそら | 藤原隆信朝臣 | 四 | 秋上 |
| 279 | くまもなきみそらに秋の月すめは庭には冬のこほりをそしく くまもなき みそらにあきの つきすめは にはにはふゆの こほりをそしく | 前中納言雅頼 | 四 | 秋上 |
| 280 | 月みれははるかにおもふさらしなの山も心のうちにそありける つきみれは はるかにおもふ さらしなの やまもこころの うちにそありける | 右のおほいまうちきみ | 四 | 秋上 |
| 281 | あすもこむ野ちの玉川はきこえて色なる浪に月やとりけり あすもこむ のちのたまかは はきこえて いろなるなみに つきやとりけり | 源俊頼朝臣 | 四 | 秋上 |
| 282 | 玉よするうらわの風にそらはれてひかりをかはす秋のよの月 たまよする うらわのかせに そらはれて ひかりをかはす あきのよのつき | 崇徳院御製 | 四 | 秋上 |
| 283 | さよふけてふしのたかねにすむ月は煙はかりやくもりなるへき さよふけて ふしのたかねに すむつきは けふりはかりや くもりなるへき | 大炊御門右大臣 | 四 | 秋上 |
| 284 | 石はしるみつのしら玉かすみえてきよたき川にすめる月影 いしはしる みつのしらたま かすみえて きよたきかはに すめるつきかけ | 皇太后宮大夫俊成 | 四 | 秋上 |
| 285 | しほかまのうらふくかせに霧はれてやそ島かけてすめる月かけ しほかまの うらふくかせに きりはれて やそしまかけて すめるつきかけ | 藤原清輔朝臣 | 四 | 秋上 |
| 286 | おもひくまなくてもとしのへぬるかなものいひかはせ秋のよの月 おもひくま なくてもとしの へぬるかな ものいひかはせ あきのよのつき | 源俊頼朝臣 | 四 | 秋上 |
| 287 | 山のはにますみのかかみかけたりとみゆるは月のいつるなりけり やまのはに ますみのかかみ かけたりと みゆるはつきの いつるなりけり | 藤原基俊 | 四 | 秋上 |
| 288 | 秋のよやあまのかはせはこほるらむ月のひかりのさえまさるかな あきのよや あまのかはせは こほるらむ つきのひかりの さえまさるかな | 藤原道経 | 四 | 秋上 |
| 289 | とほさかるおとはせねとも月きよみ氷とみゆるしかのうら浪 とほさかる おとはせねとも つききよみ こほりとみゆる しかのうらなみ | 太宰大弐重家 | 四 | 秋上 |
| 290 | つねよりも身にそしみける秋の野に月すむ夜はの荻のうはかせ つねよりも みにそしみける あきののに つきすむよはの をきのうはかせ | 右衛門督頼実 | 四 | 秋上 |
| 291 | なかめやる心のはてそなかりけるあかしのおきにすめる月影 なかめやる こころのはてそ なかりける あかしのおきに すめるつきかけ | 俊恵法師 | 四 | 秋上 |
| 292 | やほかゆくはまのまさこをしきかへて玉になしつる秋のよの月 やほかゆく はまのまさこを しきかへて たまになしつる あきのよのつき | 権中納言長方 | 四 | 秋上 |
| 293 | いしまゆくみたらし川のおとさえて月やむすはぬこほりなるらん いしまゆく みたらしかはの おとさえて つきやむすはぬ こほりなるらむ | 藤原公時朝臣 | 四 | 秋上 |
| 294 | 月かけはきえぬこほりとみえなからささ浪よするしかのからさき つきかけは きえぬこほりと みえなから ささなみよする しかのからさき | 藤原顕家朝臣 | 四 | 秋上 |
| 295 | てる月のかけさえぬれはあさちはら雪のしたにもむしはなきけり てるつきの かけさえぬれは あさちはら ゆきのしたにも むしはなきけり | 頼円法師 | 四 | 秋上 |
| 296 | あさちはらはすゑにむすふ露ことにひかりをわけてやとる月かけ あさちはら はすゑにむすふ つゆことに ひかりをわけて やとるつきかけ | 藤原親盛 | 四 | 秋上 |
| 297 | ふけにけるわかよの秋そあはれなるかたふく月は又もいてなん ふけにける わかよのあきそ あはれなる かたふくつきは またもいてなむ | 藤原清輔朝臣 | 四 | 秋上 |
| 298 | 身のうさの秋はわするる物ならはなみたくもらて月はみてまし みのうさの あきはわするる ものならは なみたくもらて つきはみてまし | 刑部卿頼輔 | 四 | 秋上 |
| 299 | おほかたの秋のあはれをおもひやれ月に心はあくかれぬとも おほかたの あきのあはれを おもひやれ つきにこころは あくかれぬとも | 紫式部 | 四 | 秋上 |
| 300 | たくひなくつらしとそおもふ秋のよの月をのこしてあくるしののめ たくひなく つらしとそおもふ あきのよの つきをのこして あくるしののめ | 前大納言成通 | 四 | 秋上 |
| 301 | てる月のたひねのとこやしもとゆふかつらき山のたに川のみつ てるつきの たひねのとこや しもとゆふ かつらきやまの たにかはのみつ | 源俊頼朝臣 | 四 | 秋上 |
| 302 | はるかなるもろこしまてもゆく物は秋のねさめの心なりけり はるかなる もろこしまても ゆくものは あきのねさめの こころなりけり | 大弐三位 | 五 | 秋下 |
| 303 | 山さとはさひしかりけりこからしのふく夕くれのひくらしのこゑ やまさとは さひしかりけり こからしの ふくゆふくれの ひくらしのこゑ | 藤原仲実朝臣 | 五 | 秋下 |
| 304 | 秋のよは松をはらはぬ風たにもかなしきことのねをたてすやは あきのよは まつをはらはぬ かせたにも かなしきことの ねをたてすやは | 藤原季通朝臣 | 五 | 秋下 |
| 305 | 露さむみうらかれもてく秋ののにさひしくもある風のおとかな つゆさむみ うらかれもてく あきののに さひしくもある かせのおとかな | 藤原時昌 | 五 | 秋下 |
| 306 | 夕くれはをのの萩はらふく風にさひしくもあるか鹿のなくなる ゆふされは をののはきはら ふくかせに さひしくもあるか しかのなくなる | 藤原正家朝臣 | 五 | 秋下 |
| 307 | みむろやまおろすあらしのさひしきにつまよふしかの声たくふなり みむろやま おろすあらしの さひしきに つまとふしかの こゑたくふなり | 二条太皇大后宮肥後 | 五 | 秋下 |
| 308 | そまかたにみちやまとへるさをしかのつまとふ声のしけくも有るかな そまかたに みちやまとへる さをしかの つまとふこゑの しけくもあるかな | 大納言公実 | 五 | 秋下 |
| 309 | 秋のよはおなしをのへになくしかのふけゆくままにちかくなるかな あきのよは おなしをのへに なくしかの ふけゆくままに ちかくなるかな | 輔仁のみこ | 五 | 秋下 |
| 310 | さをしかのなくねは野へにきこゆれとなみたはとこの物にそ有りける さをしかの なくねはのへに きこゆれと なみたはとこの ものにそありける | 源俊頼朝臣 | 五 | 秋下 |
| 311 | さらぬたにゆふへさひしき山里の露のまかきにをしか鳴くなり さらぬたに ゆふへさひしき やまさとの きりのまかきに をしかなくなり | 待賢門院堀河 | 五 | 秋下 |
| 312 | みなと川うきねのとこにきこゆなりいく田のおくのさをしかのこゑ みなとかは うきねのとこに きこゆなり いくたのおくの さをしかのこゑ | 刑部卿範兼 | 五 | 秋下 |
| 313 | うきねするゐなのみなとにきこゆなりしかのねおろすみねの松かせ うきねする ゐなのみなとに きこゆなり しかのねおろす みねのまつかせ | 藤原隆信朝臣 | 五 | 秋下 |
| 314 | 夜をこめてあかしのせとをこきいつれははるかにおくるさをしかのこゑ よをこめて あかしのせとを こきいつれは はるかにおくる さをしかのこゑ | 俊恵法師 | 五 | 秋下 |
| 315 | みなと川夜ふねこきいつるおひかせに鹿のこゑさへせとわたるなり みなとかは よふねこきいつる おひかせに しかのこゑさへ せとわたるなり | 道因法師 | 五 | 秋下 |
| 316 | 宮城ののこはきかはらをゆくほとは鹿のねをさへわけてきくかな みやきのの こはきかはらを ゆくほとは しかのねをさへ わけてきくかな | 覚延法師 | 五 | 秋下 |
| 317 | さをしかのつまよふこゑもいかなれや夕はわきてかなしかるらん さをしかの つまよふこゑも いかなれや ゆふへはわきて かなしかるらむ | 左京大夫修範 | 五 | 秋下 |
| 318 | きくままにかたしく袖のぬるるかなしかのこゑには露やそふらん きくままに かたしくそての ぬるるかな しかのこゑには つゆやそふらむ | 右京大夫季能 | 五 | 秋下 |
| 319 | 山さとのあかつきかたのしかのねは夜はのあはれのかきりなりけり やまさとの あかつきかたの しかのねは よはのあはれの かきりなりけり | 法印慈円 | 五 | 秋下 |
| 320 | よそにたに身にしむくれのしかのねにいかなる妻かつれなかるらん よそにたに みにしむくれの しかのねを いかなるつまか つれなかるらむ | 俊恵法師 | 五 | 秋下 |
| 321 | 夕まくれさてもや秋はかなしきと鹿のねきかぬ人にとははや ゆふまくれ さてもやあきは かなしきと しかのねきかぬ ひとにとははや | 道因法師 | 五 | 秋下 |
| 322 | つねよりも秋のゆふへをあはれとはしかのねにてやおもひそめけん つねよりも あきのゆふへを あはれとは しかのねにてや おもひそめけむ | 賀茂政平 | 五 | 秋下 |
| 323 | さひしさをなににたとへんをしかなくみ山のさとのあけかたのそら さひしさを なににたとへむ をしかなく みやまのさとの あけかたのそら | 惟宗広言 | 五 | 秋下 |
| 324 | いかはかり露けかるらんさをしかのつまこひかぬるをのの草ふし いかはかり つゆけかるらむ さをしかの つまこひかぬる をののくさふし | 長覚法師 | 五 | 秋下 |
| 325 | をのへより門田にかよふ秋かせにいなはをわたるさをしかのこゑ をのへより かとたにかよふ あきかせに いなはをわたる さをしかのこゑ | 寂蓮法師 | 五 | 秋下 |
| 326 | おとろかすおとこそよるのを山田は人なきよりもさひしかりけれ おとろかす おとこそよるの をやまたは ひとなきよりも さひしかりけれ | 読人知らず | 五 | 秋下 |
| 327 | わか門のおくてのひたにおとろきてむろのかり田にしきそたつなる わかかとの おくてのひたに おとろきて むろのかりたに しきそたつなる | 源兼昌 | 五 | 秋下 |
| 328 | むしのねはあさちかもとにうつもれて秋はすゑはの色にそ有りける むしのねは あさちかもとに うつもれて あきはすゑはの いろにそありける | 寂蓮法師 | 五 | 秋下 |
| 329 | 秋のよのあはれはたれもしるものをわれのみとなくきりきりすかな あきのよの あはれはたれも しるものを われのみとなく きりきりすかな | 藤原兼宗朝臣 | 五 | 秋下 |
| 330 | さまさまのあさちかはらのむしのねをあはれひとつにききそなしつる さまさまの あさちかはらの むしのねを あはれひとつに ききそなしつる | 左近中将良経 | 五 | 秋下 |
| 331 | 夜をかさねこゑよわりゆくむしのねに秋のくれぬるほとをしるかな よをかさね こゑよわりゆく むしのねに あきのくれぬる ほとをしるかな | 大炊御門右大臣 | 五 | 秋下 |
| 332 | 秋ふかくなりにけらしなきりきりすゆかのあたりにこゑきこゆなり あきふかく なりにけらしな きりきりす ゆかのあたりに こゑきこゆなり | 花山院御製 | 五 | 秋下 |
| 333 | さりともとおもふこころもむしのねもよわりはてぬる秋のくれかな さりともと おもふこころも むしのねも よわりはてぬる あきのくれかな | 皇太后宮大夫俊成 | 五 | 秋下 |
| 334 | むしのねもまれになりゆくあたし野にひとり秋なる月のかけかな むしのねも まれになりゆく あたしのに ひとりあきなる つきのかけかな | (仁和寺)道性法親王 | 五 | 秋下 |
| 335 | 草も木もあきのすゑははみえゆくに月こそ色もかはらさりけれ くさもきも あきのすゑはは みえゆくに つきこそいろも かはらさりけれ | 式子内親王 | 五 | 秋下 |
| 336 | すむ水にさやけき影のうつれはやこよひの月の名になかるらん すむみつに さやけきかけの うつれはや こよひのつきの なになかるらむ | 大宮右大臣 | 五 | 秋下 |
| 337 | 秋の月ちちに心をくたききてこよひ一よにたへすも有るかな あきのつき ちちにこころを くたききて こよひひとよに たへすもあるかな | 読人知らず | 五 | 秋下 |
| 338 | さよふけてきぬたのおとそたゆむなる月をみつつや衣うつらん さよふけて きぬたのおとそ たゆむなる つきをみつつや ころもうつらむ | 仁和寺後入道法親王(覚性) | 五 | 秋下 |
| 339 | 恋ひつつやいもかうつらむから衣きぬたのおとのそらになるまて こひつつや いもかうつらむ からころも きぬたのおとの そらになるまて | 大納言公実 | 五 | 秋下 |
| 340 | 松かせのおとたに秋はさひしきに衣うつなり玉川のさと まつかせの おとたにあきは さひしきに ころもうつなり たまかはのさと | 源俊頼朝臣 | 五 | 秋下 |
| 341 | たかためにいかにうてはかから衣ちたひやちたひ声のうらむる たかために いかにうてはか からころも ちたひやちたひ こゑのうらむる | 藤原基俊 | 五 | 秋下 |
| 342 | 衣うつおとをきくにそしられぬる里とほからぬ草枕とは ころもうつ おとをきくにそ しられぬる さととほからぬ くさまくらとは | 俊盛法師 | 五 | 秋下 |
| 343 | 夕きりや秋のあはれをこめつらむわけいる袖に露のおきそふ ゆふきりや あきのあはれを こめつらむ わけいるそてに つゆのおきそふ | 法橋宗円 | 五 | 秋下 |
| 344 | 秋ふかみたそかれ時のふちはかまにほふはなのる心ちこそすれ あきふかみ たそかれときの ふちはかま にほふはなのる ここちこそすれ | 崇徳院御製 | 五 | 秋下 |
| 345 | いかにしていはまもみえぬ夕暮にとなせのいかたおちてきつらん いかにして いはまもみえぬ ゆふきりに となせのいかた おちてきつらむ | 前参犠親隆 | 五 | 秋下 |
| 346 | けさみれはさなから霜をいたたきておきなさひゆく白菊の花 けさみれは さなからしもを いたたきて おきなさひゆく しらきくのはな | 藤原基俊 | 五 | 秋下 |
| 347 | しら菊のはにおく露にやとらすは花とそみましてらす月影 しらきくの はにおくつゆに やとらすは はなとそみまし てらすつきかけ | 内のおほいまうちきみ | 五 | 秋下 |
| 348 | 雪ならはまかきにのみはつもらしとおもひとくにそ白菊の花 ゆきならは まかきにのみは つもらしと おもひとくにそ しらきくのはな | 前大僧正行慶 | 五 | 秋下 |
| 349 | 朝な朝な籬のきくのうつろへは露さへ色のかはり行くかな あさなあさな まかきのきくの うつろへは つゆさへいろの かはりゆくかな | 祐盛法師 | 五 | 秋下 |
| 350 | さえわたる光を霜にまかへてや月にうつろふ白きくのはな さえわたる ひかりをしもに まかへてや つきにうつろふ しらきくのはな | 藤原家隆 | 五 | 秋下 |
| 351 | ことことにかなしかりけりむへしこそ秋の心をうれへといひけれ ことことに かなしかりけり うへしこそ あきのこころを うれへといひけれ | 藤原季通朝臣 | 五 | 秋下 |
| 352 | 秋にあへすさこそはくすの色つかめあなうらめしの風のけしきや あきにあへす さこそはくすの いろつかめ あなうらめしの かせのけしきや | 藤原基俊 | 五 | 秋下 |
| 353 | はつ時雨ふるほともなくしもとゆふかつらき山は色つきにけり はつしくれ ふるほともなく しもとゆふ かつらきやまは いろつきにけり | 仁和寺後入道法親王(覚性) | 五 | 秋下 |
| 354 | むら雲の時雨れてそむる紅葉ははうすくこくこそ色にみえけれ むらくもの しくれてそむる もみちはは うすくこくこそ いろにみえけれ | 覚延法師 | 五 | 秋下 |
| 355 | しくれ行くよものこすゑの色よりも秋は夕のかはるなりけり しくれゆく よものこすゑの いろよりも あきはゆふへの かはるなりけり | 藤原定家 | 五 | 秋下 |
| 356 | おほろけの色とや人のおもふらむをくらの山をてらす紅葉は おほろけの いろとやひとの おもふらむ をくらのやまを てらすもみちは | 道命法師 | 五 | 秋下 |
| 357 | 君みんと心やしけんたつたひめ紅葉の錦いろをつくせり きみみむと こころやしけむ たつたひめ もみちのにしき いろをつくせり | 小弁 | 五 | 秋下 |
| 358 | 故郷にとふ人あらはもみちはのちりなん後をまてとこたへよ ふるさとに とふひとあらは もみちはの ちりなむのちを まてとこたへよ | 素意法師 | 五 | 秋下 |
| 359 | 山ひめにちへのにしきをたむけてもちる紅葉はをいかてととめん やまひめに ちへのにしきを たむけても ちるもみちはを いかてととめむ | 左京大夫顕輔 | 五 | 秋下 |
| 360 | 紅葉はに月の光をさしそへてこれやあかちの錦なるらん もみちはに つきのひかりを さしそへて これやあかちの にしきなるらむ | 院御製 | 五 | 秋下 |
| 361 | 山おろしにうらつたひする紅葉かないかかはすへきすまのせきもり やまおろしに うらつたひする もみちかな いかかはすへき すまのせきもり | 右大臣 | 五 | 秋下 |
| 362 | 清見かた関にとまらてゆく船は嵐のさそふこのはなりけり きよみかた せきにとまらて ゆくふねは あらしのさそふ このはなりけり | 右近大将実房 | 五 | 秋下 |
| 363 | もみちはをせきもる神にたむけおきてあふ坂山をすくる木からし もみちはを せきもるかみに たむけおきて あふさかやまを すくるこからし | 権中納言実守 | 五 | 秋下 |
| 364 | 紅葉はのみなくれなゐにちりしけは名のみなりけり白川の関 もみちはの みなくれなゐに ちりしけは なのみなりけり しらかはのせき | 左大弁親宗 | 五 | 秋下 |
| 365 | みやこにはまた青葉にてみしかとももみちちりしく白川のせき みやこには またあをはにて みしかとも もみちちりしく しらかはのせき | 前右京権大夫頼政 | 五 | 秋下 |
| 366 | ささ波やひらのたかねの山おろしもみちをうみの物となしつる ささなみや ひらのたかねの やまおろし もみちをうみの ものとなしつる | 刑部卿範兼 | 五 | 秋下 |
| 367 | たつた山松のむらたちなかりせはいつくかのこるみとりならまし たつたやま まつのむらたち なかりせは いつくかのこる みとりならまし | 藤原清輔朝臣 | 五 | 秋下 |
| 368 | 秋といへはいはたのをののははそ原時雨もまたす紅葉しにけり あきといへは いはたのをのの ははそはら しくれもまたす もみちしにけり | 覚盛法師 | 五 | 秋下 |
| 369 | 庭のおもにちりてつもれる紅葉はは九重にしく錦なりけり にはのおもに ちりてつもれる もみちはは ここのへにしく にしきなりけり | 藤原公重朝臣 | 五 | 秋下 |
| 370 | けふみれは嵐の山はおほゐ川もみち吹きおろす名にこそ有りけれ けふみれは あらしのやまは おほゐかは もみちふきおろす なにこそありけれ | 俊恵法師 | 五 | 秋下 |
| 371 | おほゐかはなかれておつる紅葉かなさそふは峰の嵐のみかは おほゐかは なかれておつる もみちかな さそふはみねの あらしのみかは | 道因法師 | 五 | 秋下 |
| 372 | 今そしる手向の山はもみち葉のぬさとちりかふ名こそ有りけれ いまそしる たむけのやまは もみちはの ぬさとちりかふ なにこそありけれ | 藤原清輔朝臣 | 五 | 秋下 |
| 373 | たつた山ふもとの里はとほけれと嵐のつてに紅葉をそみる たつたやま ふもとのさとは とほけれと あらしのつてに もみちをそみる | 祝部成仲 | 五 | 秋下 |
| 374 | 吹きみたるははそか原をみわたせは色なき風も紅葉しにけり ふきみたる ははそかはらを みわたせは いろなきかせも もみちしにけり | 賀茂成保 | 五 | 秋下 |
| 375 | 色かへぬ松ふく風のおとはしてちるはははそのもみちなりけり いろかへぬ まつふくかせの おとはして ちるはははその もみちなりけり | 藤原朝仲 | 五 | 秋下 |
| 376 | ふるさとの庭はこのはに色かへてかはらの松そみとりなりける ふるさとの にははこのはに いろかへて かはらぬまつそ みとりなりける | 惟宗広言 | 五 | 秋下 |
| 377 | ちりつもる木のはも風にさそはれて庭にも秋のくれにけるかな ちりつもる このはもかせに さそはれて にはにもあきの くれにけるかな | 法橋慈弁 | 五 | 秋下 |
| 378 | 秋の田にもみちちりける山さとをこともおろかにおもひけるかな あきのたに もみちちりける やまさとを こともおろかに おもひけるかな | 源俊頼朝臣 | 五 | 秋下 |
| 379 | ちりかかる谷のを川の色つくはこのはや水の時雨なるらん ちりかかる たにのをかはの いろつくは このはやみつの しくれなるらむ | 摂政前右大臣 | 五 | 秋下 |
| 380 | くれてゆく秋をは水やさそふらむ紅葉なかれぬ山河そなき くれてゆく あきをはみつや さそふらむ もみちなかれぬ やまかはそなき | 後三条内大臣 | 五 | 秋下 |
| 381 | 紅葉はのちり行くかたをたつぬれは秋も嵐のこゑのみそする もみちはの ちりゆくかたを たつぬれは あきもあらしの こゑのみそする | 崇徳院御製 | 五 | 秋下 |
| 382 | さらぬたに心ほそきを山さとのかねさへ秋のくれをつくなり さらぬたに こころほそきを やまさとの かねさへあきの くれをつくなり | 前大僧正覚忠 | 五 | 秋下 |
| 383 | からにしきぬさにたちもて行く秋もけふやたむけの山ちこゆらん からにしき ぬさにたちもて ゆくあきも けふやたむけの やまちこゆらむ | 瞻西上人 | 五 | 秋下 |
| 384 | あけぬともなほ秋風はおとつれて野へのけしきよおもかはりすな あけぬとも なほあきかせは おとつれて のへのけしきよ おもかはりすな | 源俊頼朝臣 | 五 | 秋下 |
| 385 | たつた山ちるもみちはをきてみれは秋はふもとにかへるなりけり たつたやま ちるもみちはを きてみれは あきはふもとに かへるなりけり | 前中納言匡房 | 五 | 秋下 |
| 386 | こよひまて秋はかきれとさためける神代もさらにうらめしきかな こよひまて あきはかきれと さためける かみよもさらに うらめしきかな | 花薗左大臣家小大進 | 五 | 秋下 |
| 387 | 昨日こそ秋はくれしかいつのまにいはまの水のうすこほるらん きのふこそ あきはくれしか いつのまに いはまのみつの うすこほるらむ | 大納言公実 | 六 | 冬 |
| 388 | いかはかりあきのなこりをなかめましけさはこのはに嵐ふかすは いかはかり あきのなこりを なかめまし けさはこのはに あらしふかすは | 源俊頼朝臣 | 六 | 冬 |
| 389 | いつみ川水のみわたのふしつけにしはまのこほる冬はきにけり いつみかは みつのみわたの ふしつけに しはまもこほる ふゆはきにけり | 藤原仲実朝臣 | 六 | 冬 |
| 390 | ひまもなくちるもみちはにうつもれて庭のけしきも冬こもりけり ひまもなく ちるもみちはに うつもれて にはのけしきも ふゆこもりけり | 崇徳院御製 | 六 | 冬 |
| 391 | さまさまの草葉もいまは霜かれぬ野へより冬やたちてきつらん さまさまの くさはもいまは しもかれぬ のへよりふゆや たちてきつらむ | 大炊御門右大臣 | 六 | 冬 |
| 392 | すむ水を心なしとはたれかいふこほりそ冬のはしめをもしる すむみつを こころなしとは たれかいふ こほりそふゆの はしめをもしる | 大納言隆季 | 六 | 冬 |
| 393 | 秋のうちはあはれしらせし風のおとのはけしさそふる冬はきにけり あきのうちは あはれしらせし かせのおとの はけしさそふる ふゆはきにけり | 前参議教長 | 六 | 冬 |
| 394 | わきも子かうはものすそのみつなみにけさこそ冬はたちはしめけれ わきもこか うはものすその みつなみに けさこそふゆは たちはしめけれ | 花薗左大臣家小大進 | 六 | 冬 |
| 395 | いつのまにかけひの水のこほるらむさこそ嵐のおとのかはらめ いつのまに かけひのみつの こほるらむ さこそあらしの おとのかはらめ | 藤原孝善 | 六 | 冬 |
| 396 | と山ふく貴のかせのおときけはまたきに冬のおくそしらるる とやまふく あらしのかせの おときけは またきにふゆの おくそしらるる | 和泉式部 | 六 | 冬 |
| 397 | はつ霜やおきはしむらん暁のかねのおとこそほのきこゆなれ はつしもや おきはしむらむ あかつきの かねのおとこそ ほのきこゆなれ | 大炊御門右大臣 | 六 | 冬 |
| 398 | たかさこのをのへのかねのおとすなり暁かけて霜やおくらん たかさこの をのへのかねの おとすなり あかつきかけて しもやおくらむ | 前中納言匡房 | 六 | 冬 |
| 399 | ひさきおふるをののあさちにおく霜のしろきをみれは夜やふけぬらん ひさきおふる をののあさちに おくしもの しろきをみれは よやふけぬらむ | 藤原基俊 | 六 | 冬 |
| 400 | 冬きては一よふたよを玉ささのはわけの霜のところせきまて ふゆきては ひとよふたよを たまささの はわけのしもの ところせきまて | 藤原定家 | 六 | 冬 |
| 401 | 霜さえてかれ行くをののをかへなるならのひろはに時雨ふるなり しもさえて かれゆくをのの をかへなる ならのひろはに しくれふるなり | 藤原基俊 | 六 | 冬 |
| 402 | ねさめしてたれかきくらん此ころのこのはにかかる夜半のしくれを ねさめして たれかきくらむ このころの このはにかかる よはのしくれを | 馬内侍 | 六 | 冬 |
| 403 | おとにさへたもとをぬらす時雨かなまきのいたやの夜はのねさめに おとにさへ たもとをぬらす しくれかな まきのいたやの よはのねさめに | 源定信(法名道舜) | 六 | 冬 |
| 404 | まはらなるまきのいたやにおとはしてもらぬ時雨やこのはなるらん まはらなる まきのいたやに おとはして もらぬしくれや このはなるらむ | 皇太后宮大夫俊成 | 六 | 冬 |
| 405 | 木葉ちるとはかりききてやみなましもらて時雨の山めくりせは このはちる とはかりききて やみなまし もらてしくれの やまめくりせは | 仁和寺後入道法親王(覚性) | 六 | 冬 |
| 406 | ひとりねの涙やそらにかよふらむ時雨にくもるあり明の月 ひとりねの なみたやそらに かよふらむ しくれにくもる ありあけのつき | 摂政前右大臣 | 六 | 冬 |
| 407 | うたたねは夢やうつつにかよふらむさめてもおなし時雨をそきく うたたねは ゆめやうつつに かよふらむ さめてもおなし しくれをそきく | 藤原隆信朝臣 | 六 | 冬 |
| 408 | 山めくる雲のしたにや成りぬらんすそ野の原にしくれすくなり やまめくる くものしたにや なりぬらむ すそののはらに しくれすくなり | 前右京権大夫頼政 | 六 | 冬 |
| 409 | 時雨れゆくをちのと山のみねつつきうつりもあへす雲かくるらん しくれゆく をちのとやまの みねつつき うつりもあへす くもかくるらむ | 源師光 | 六 | 冬 |
| 410 | あらしふくひらのたかねのねわたしにあはれしくるる神無月かな あらしふく ひらのたかねの ねわたしに あはれしくるる かみなつきかな | 道因法師 | 六 | 冬 |
| 411 | み山辺の時雨れてわたるかすことにかことかましき玉かしはかな みやまへの しくれてわたる かすことに かことかましき たまかしはかな | 中納言国信 | 六 | 冬 |
| 412 | このはのみちるかとおもひし時雨には涙もたへぬ物にそ有りける このはのみ ちるかとおもひし しくれには なみたもたへぬ ものにそありける | 源俊頼朝臣 | 六 | 冬 |
| 413 | ふりはへて人もとひこぬ山さとは時雨はかりそすきかてにする ふりはへて ひともとひこぬ やまさとは しくれはかりそ すきかてにする | 二条太皇大后宮肥後 | 六 | 冬 |
| 414 | 時雨れつるまやののきはのほとなきにやかてさしいる月のかけかな しくれつる まやののきはの ほとなきに やかてさしいる つきのかけかな | 藤原定家 | 六 | 冬 |
| 415 | 玉つさに涙のかかる心ちしてしくるるそらに雁のなくなる たまつさに なみたのかかる ここちして しくるるそらに かりのなくなる | 読人知らず | 六 | 冬 |
| 416 | みねこえにならのはつたひおとつれてやかて軒はに時雨きにけり みねこえに ならのはつたひ おとつれて やかてのきはに しくれきにけり | 源仲頼 | 六 | 冬 |
| 417 | 暁のねさめにすくる時雨こそもらても人の袖ぬらしけれ あかつきの ねさめにすくる しくれこそ もらてもひとの そてぬらしけれ | 紀康宗 | 六 | 冬 |
| 418 | ちりはててのちさへ風をいとふかなもみちをふけるみ山へのさと ちりはてて のちさへかせを いとふかな もみちをふける みやまへのさと | 藤原盛雅 | 六 | 冬 |
| 419 | 都たにさひしさまさる木からしにみねの松かせおもひこそやれ みやこたに さひしさまさる こからしに みねのまつかせ おもひこそやれ | 中納言定頼女 | 六 | 冬 |
| 420 | あさほらけうちの河霧たえたえにあらはれわたるせせの網代木 あさほらけ うちのかはきり たえたえに あらはれわたる せせのあしろき | 中納言定頼 | 六 | 冬 |
| 421 | やかたをのましろのたかを引きすゑてうたのとたちをかりくらしつる やかたをの ましろのたかを ひきすゑて うたのとたちを かりくらしつる | 藤原仲実朝臣 | 六 | 冬 |
| 422 | ふる雪にゆくへも見えすはし鷹のをふさのすすのおとはかりして ふるゆきに ゆくへもみえす はしたかの をふさのすすの おとはかりして | 隆源法師 | 六 | 冬 |
| 423 | 夕まくれ山かたつきてたつ鳥のはおとにたかをあはせつるかな ゆふまくれ やまかたつきて たつとりの はおとにたかを あはせつるかな | 源俊頼朝臣 | 六 | 冬 |
| 424 | いもかりとさほの川へをわかゆけはさよかふけぬる千鳥なくなり いもかりと さほのかはへを わかゆけは さよかふけぬる ちとりなくなり | 藤原長能 | 六 | 冬 |
| 425 | すまのせき有明のそらになく千鳥かたふく月はなれもかなしき すまのせき ありあけのそらに なくちとり かたふくつきは なれもかなしき | 皇太后宮大夫俊成 | 六 | 冬 |
| 426 | いはこゆるあら磯なみにたつ千とり心ならてやうらつたふらん いはこゆる あらいそなみに たつちとり こころならすや うらつたふらむ | 道因法師 | 六 | 冬 |
| 427 | 霜さえてさ夜もなかゐのうらさむみ明けやらすとや千鳥鳴くらん しもさえて さよもなかゐの うらさむみ あけやらすとや ちとりなくらむ | 法印静賢 | 六 | 冬 |
| 428 | しもかれのなにはのあしのほのほのとあくる湊に千とり鳴くなり しもかれの なにはのあしの ほのほのと あくるみなとに ちとりなくなり | 賀茂成保 | 六 | 冬 |
| 429 | かたみにやうはけの霜をはらふらむともねのをしのもろこゑになく かたみにや うはけのしもを はらふらむ ともねのをしの もろこゑになく | 源親房 | 六 | 冬 |
| 430 | 水鳥をみつのうへとやよそにみむ我もうきたる世をすくしつつ みつとりを みつのうへとや よそにみむ われもうきたる よをすくしつつ | 紫式部 | 六 | 冬 |
| 431 | みつ鳥の玉ものとこのうき枕ふかきおもひはたれかまされる みつとりの たまものとこの うきまくら ふかきおもひは たれかまされる | 前中納言匡房 | 六 | 冬 |
| 432 | このころのをしのうきねそあはれなるうはけの霜よ下のこほりよ このころの をしのうきねそ あはれなる うはけのしもよ したのこほりよ | 崇徳院御製 | 六 | 冬 |
| 433 | なにはかたいりえをめくるあしかもの玉ものふねにうきねすらしも なにはかた いりえをめくる あしかもの たまものふねに うきねすらしも | 左京大夫顕輔 | 六 | 冬 |
| 434 | をし鳥のうきねのとこやあれぬらんつららゐにけりこやの池水 をしとりの うきねのとこや あれぬらむ つららゐにけり こやのいけみつ | 権中納言経房 | 六 | 冬 |
| 435 | かものゐるいりえのあしは霜かれておのれのみこそあをはなりけれ かものゐる いりえのあしは しもかれて おのれのみこそ あをはなりけれ | 道因法師 | 六 | 冬 |
| 436 | おく霜をはらひかねてやしをれふすかつみかしたにをしのなくらん おくしもを はらひかねてや しをれふす かつみかしたに をしのなくらむ | 賀茂重保 | 六 | 冬 |
| 437 | あしかものすたく入えの月かけはこほりそ浪のかすにくたくる あしかもの すたくいりえの つきかけは こほりそなみの かすにくたくる | 前左衛門督公光 | 六 | 冬 |
| 438 | 夜をかさねむすふ氷のしたにさヘ心ふかくもやとる月かな よをかさね むすふこほりの したにさへ こころふかくも やとるつきかな | 平実重 | 六 | 冬 |
| 439 | いつくにか月はひかりをととむらんやとりし水も氷ゐにけり いつくにか つきはひかりを ととむらむ やとりしみつも こほりゐにけり | 左大弁親宗 | 六 | 冬 |
| 440 | 冬くれはゆくてに人はくまねともこほりそむすふ山の井の水 ふゆくれは ゆくてにひとは くまねとも こほりそむすふ やまのゐのみつ | 藤原成家朝臣 | 六 | 冬 |
| 441 | 月のすむそらには雲もなかりけりうつりし水はこほりへたてて つきのすむ そらにはくもも なかりけり うつりしみつは こほりへたてて | 道因法師 | 六 | 冬 |
| 442 | つららゐてみかける影のみゆるかなまことにいまや玉川の水 つららゐて みかけるかけの みゆるかな まことにいまや たまかはのみつ | 崇徳院御製 | 六 | 冬 |
| 443 | 月さゆる氷のうへにあられふり心くたくる玉川のさと つきさゆる こほりのうへに あられふり こころくたくる たまかはのさと | 皇太后宮大夫俊成 | 六 | 冬 |
| 444 | さゆる夜のまきのいたやのひとりねに心くたけと霰ふるなり さゆるよの まきのいたやの ひとりねに こころくたけと あられふるなり | 左近中将良経 | 六 | 冬 |
| 445 | 朝戸あけてみるそさひしきかた岡のならのひろはにふれるしらゆき あさとあけて みるそさひしき かたをかの ならのひろはに ふれるしらゆき | 大納言経信 | 六 | 冬 |
| 446 | 夜をこめて谷の戸ほそに風さむみかねてそしるきみねのはつ雪 よをこめて たにのとほそに かせさむみ かねてそしるき みねのはつゆき | 崇徳院御製 | 六 | 冬 |
| 447 | さえわたるよはのけしきにみやまへの雪のふかさを空にしるかな さえわたる よはのけしきに みやまへの ゆきのふかさを そらにしるかな | 藤原季通朝臣 | 六 | 冬 |
| 448 | きゆるをや都の人はをしむらんけさ山さとにはらふしら雪 きゆるをや みやこのひとは をしむらむ けさやまさとに はらふしらゆき | 藤原清輔朝臣 | 六 | 冬 |
| 449 | 霜かれのまかきのうちの雪みれはきくよりのちの花も有りけり しもかれの まかきのうちの ゆきみれは きくよりのちの はなもありけり | 藤原資隆朝臣 | 六 | 冬 |
| 450 | たとへてもいはむかたなし月かけにうす雲かけてふれるしら雪 たとへても いはむかたなし つきかけに うすくもかけて ふれるしらゆき | 仁和寺後入道法親王(覚性) | 六 | 冬 |
| 451 | み山ちはかつふる雪にうつもれていかてかこまのあとをたつねん みやまちは かつふるゆきに うつもれて いかてかこまの あとをたつねむ | 前参議教長 | 六 | 冬 |
| 452 | おしなへて山のしら雪つもれともしるきはこしのたかねなりけり おしなへて やまのしらゆき つもれとも しるきはこしの たかねなりけり | 治部卿通俊 | 六 | 冬 |
| 453 | と山にはしはのしたはもちりはててをちのたかねに雪ふりにけり とやまには しはのしたはも ちりはてて をちのたかねに ゆきふりにけり | 藤原顕綱朝臣 | 六 | 冬 |
| 454 | 雪ふれは谷のかけはしうつもれて梢そ冬の山ちなりける ゆきふれは たにのかけはし うつもれて こすゑそふゆの やまちなりける | 源俊頼朝臣 | 六 | 冬 |
| 455 | 雪つもるみねにふふきやわたるらむこしのみそらにまよふしら雲 ゆきつもる みねにふふきや わたるらむ こしのみそらに まよふしらくも | 二条院御製 | 六 | 冬 |
| 456 | 浪かけはみきはの雪もきえなまし心ありてもこほる池かな なみかけは みきはのゆきも きえなまし こころありても こほるいけかな | 仁和寺法親王(守覚) | 六 | 冬 |
| 457 | 山さとのかきねは雪にうつもれて野へとひとつに成りにけるかな やまさとの かきねはゆきに うつもれて のへとひとつに なりにけるかな | 右のおほいまうちきみ | 六 | 冬 |
| 458 | あともたえしをりも雪にうつもれてかへる山ちにまとひぬるかな あともたえ しをりもゆきに うつもれて かへるやまちに まとひぬるかな | 右近大将実房 | 六 | 冬 |
| 459 | こえかねていまそこし路をかへる山雪ふる時の名にこそ有りけれ こえかねて いまそこしちを かへるやま ゆきふるときの なにこそありけれ | 前右京権大夫頼政 | 六 | 冬 |
| 460 | 浪まよりみえしけしきそかはりぬる雪ふりにけり松かうら島 なみまより みえしけしきそ かはりぬる ゆきふりにけり まつかうらしま | 顕昭法師 | 六 | 冬 |
| 461 | ふふきするなからの山をみわたせはをのへをこゆるしかのうらなみ ふふきする なからのやまを みわたせは をのへをこゆる しかのうらなみ | 藤原良清 | 六 | 冬 |
| 462 | ふる雪にのきはの竹もうつもれて友こそなけれ冬の山さと ふるゆきに のきはのたけも うつもれて ともこそなけれ ふゆのやまさと | 読人不知 | 六 | 冬 |
| 463 | こまのあとはかつふる雪にうつもれておくるる人や道まとふらん こまのあとは かつふるゆきに うつもれて おくるるひとや みちまとふらむ | 西住法師 | 六 | 冬 |
| 464 | くれ竹のをれふすおとのなかりせは夜ふかき雪をいかてしらまし くれたけの をれふすおとの なかりせは よふかきゆきを いかてしらまし | 坂上明兼 | 六 | 冬 |
| 465 | ましはかるをののほそ道あとたえてふかくも雪のなりにけるかな ましはかる をののほそみち あとたえて ふかくもゆきの なりにけるかな | 藤原為季 | 六 | 冬 |
| 466 | 雪ふれは木木のこすゑにさきそむるえたよりほかの花もちりけり ゆきふれは ききのこすゑに さきそむる えたよりほかの はなもちりけり | 俊恵法師 | 六 | 冬 |
| 467 | ふるままに跡たえぬれはすすか山雪こそせきのとさしなりけれ ふるままに あとたえぬれは すすかやま ゆきこそせきの とさしなりけれ | 内大臣 | 六 | 冬 |
| 468 | 山さとのかきねの梅はさきにけりかはかりこそは春もにほはめ やまさとの かきねのうめは さきにけり かはかりこそは はるもにほはめ | 天台座主明快 | 六 | 冬 |
| 469 | かきくらしこし路もみえすふる雪にいかてかとしのかへり行くらん かきくらし こしちもみえす ふるゆきに いかてかとしの かへりゆくらむ | 前大納言実長 | 六 | 冬 |
| 470 | さりともとなけきなけきてすくしつるとしもこよひにくれはてにけり さりともと なけきなけきて すくしつる としもこよひに くれはてにけり | 前左衛門督公光 | 六 | 冬 |
| 471 | あはれにもくれゆくとしのひかすかなかへらむことは夜のまとおもふに あはれにも くれゆくとしの ひかすかな かへらむことは よのまとおもふに | 相模 | 六 | 冬 |
| 472 | かすならぬ身にはつもらぬとしならはけふのくれをもなけかさらまし かすならぬ みにはつもらぬ としならは けふのくれをも なけかさらまし | 惟宗広言 | 六 | 冬 |
| 473 | をしめともはかなくくれてゆく年のしのふむかしにかへらましかは をしめとも はかなくくれて ゆくとしの しのふむかしに かへらましかは | 源光行 | 六 | 冬 |
| 474 | 一とせははかなき夢のここちしてくれぬるけふそおとろかれける ひととせは はかなきゆめの ここちして くれぬるけふそ おとろかれける | 前律師俊宗 | 六 | 冬 |
| 475 | みやこにておくりむかふといそきしをしらてや年のけふはくれなん みやこにて おくりむかふと いそきしを しりてやとしの けふはくれなむ | 民部卿親範 | 六 | 冬 |
| 476 | むかしみし心はかりをしるへにておもひそおくるいきの松原 むかしみし こころはかりを しるへにて おもひそおくる いきのまつはら | 藤原実方朝臣 | 七 | 離別 |
| 477 | わかれよりまさりてをしき命かなきみに二たひあはむとおもへは わかれより まさりてをしき いのちかな きみにふたたひ あはむとおもへは | 前太納言公任 | 七 | 離別 |
| 478 | なきよわるまかきの虫もとめかたき秋のわかれやかなしかるらん なきよわる まかきのむしも とめかたき あきのわかれや かなしかるらむ | 紫式部 | 七 | 離別 |
| 479 | かへりこむほともさためぬわかれちは都のてふりおもひいてにせよ かへりこむ ほともさためぬ わかれちは みやこのてふり おもひいてにせよ | 大納言公実 | 七 | 離別 |
| 480 | 行すゑをまつへき身こそおいにけれ別はみちのとほきのみかは ゆくすゑを まつへきみこそ おいにけれ わかれはみちの とほきのみかは | 前中納言匡房 | 七 | 離別 |
| 481 | わするなよかへる山ちにあとたえて日かすは雪のふりつもるとも わするなよ かへるやまちに あとたえて ひかすはゆきの ふりつもるとも | 源俊頼朝臣 | 七 | 離別 |
| 482 | かへりこむほとをはいつといひおかし定なき身は人たのめなり かへりこむ ほとをはいつと いひおかし さためなきみは ひとたのめなり | 大僧正行尊 | 七 | 離別 |
| 483 | たのむれと心かはりてかへりこはこれそやかての別なるへき たのむれと こころかはりて かへりこは これそやかての わかれなるへき | 左京大夫顕輔 | 七 | 離別 |
| 484 | かきりあらむ道こそあらめこの世にて別るへしとはおもはさりしを かきりあらむ みちこそあらめ このよにて わかるへしとは おもはさりしを | 上西門院兵衛 | 七 | 離別 |
| 485 | 行くきみをととめまほしくおもふかな我も恋しき都なれとも ゆくきみを ととめまほしく おもふかな われもこひしき みやこなれとも | 藤原経衡 | 七 | 離別 |
| 486 | 年へたる人の心をおもひやれ君たにこふる花の都を としへたる ひとのこころを おもひやれ きみたにこふる はなのみやこを | 太宰大弐資通 | 七 | 離別 |
| 487 | もろともに行人もなき別ちに涙はかりそとまらさりける もろともに ゆくひともなき わかれちに なみたはかりそ とまらさりける | 道命法師 | 七 | 離別 |
| 488 | なからへてあるへき身としおもはねはわするなとたにえこそちきらね なからへて あるへきみとし おもはねは わするなとたに えこそちきらね | 天台座主源心 | 七 | 離別 |
| 489 | あはれとしおもはむ人は別れしを心は身よりほかのものかは あはれとし おもはむひとは わかれしを こころはみより ほかのものかは | 読人不知 | 七 | 離別 |
| 490 | 別れてもおなしみやこにありしかはいとこのたひの心ちやはせし わかれても おなしみやこに ありしかは いとこのたひの ここちやはせし | 和泉式部 | 七 | 離別 |
| 491 | しのへともこのわかれちをおもふにはから紅の涙こそふれ しのへとも このわかれちを おもふには からくれなゐの なみたこそふれ | 成尋法師母 | 七 | 離別 |
| 492 | 心をもきみをもやとにととめおきて涙とともにいつるたひかな こころをも きみをもやとに ととめおきて なみたとともに いつるたひかな | 僧都覚雅 | 七 | 離別 |
| 493 | まてといひてたのめし秋もすきぬれは帰る山ちの名そかひもなき まてといひて たのめしあきも すきぬれは かへるやまちの なそかひもなき | 西住法師 | 七 | 離別 |
| 494 | をしへおくかたみをふかくしのはなん身はあを海の浪になかれぬ をしへおく かたみをふかく しのはなむ みはあをうみの なみになかれぬ | 入道前太政大臣 | 七 | 離別 |
| 495 | あらすのみなりゆくたひの別ちにてなれしことのねこそかはらね あらすのみ なりゆくたひの わかれちに てなれしことの ねこそかはらね | 右大臣 | 七 | 離別 |
| 496 | わするなよをはすて山の月みても都をいつるあり明のそら わするなよ をはすてやまの つきみても みやこをいつる ありあけのそら | 右衛門督頼実 | 七 | 離別 |
| 497 | わかれても心へたつなたひころもいくへかさなる山ちなりとも わかれても こころへたつな たひころも いくへかさなる やまちなりとも | 藤原定家 | 七 | 離別 |
| 498 | 有明の月もしみつにやとりけりこよひはこえしあふ坂のせき ありあけの つきもしみつに やとりけり こよひはこえし あふさかのせき | 藤原範永朝臣 | 八 | 羈旅 |
| 499 | はりまちやすまのせきやのいたひさし月もれとてやまはらなるらん はりまちや すまのせきやの いたひさし つきもれとてや まはらなるらむ | 中納言師俊 | 八 | 羈旅 |
| 500 | あたら夜をいせのはま荻をりしきていも恋しらにみつる月かな あたらよを いせのはまをき をりしきて いもこひしらに みつるつきかな | 藤原基俊 | 八 | 羈旅 |
| 501 | 浪のうへにあり明の月をみましやはすまのせきやにとまらさりせは なみのうへに ありあけのつきを みましやは すまのせきやに とまらさりせは | 中納言国信 | 八 | 羈旅 |
| 502 | よなよなのたひねのとこに風さえてはつ雪ふれるさやの中山 よなよなの たひねのとこに かせさえて はつゆきふれる さやのなかやま | 八条前太政大臣 | 八 | 羈旅 |
| 503 | 水のうへにうきねをしてそおもひしるかかれはをしも鳴くにそ有りける みつのうへに うきねをしてそ おもひしる かかれはをしも なくにそありける | 和泉式部 | 八 | 羈旅 |
| 504 | おもふことなくてそみましよさの海のあまのはしたて都なりせは おもふこと なくてそみまし よさのうみの あまのはしたて みやこなりせは | 赤染衛門 | 八 | 羈旅 |
| 505 | 宮木ひくあつさの杣をかきわけてなにはのうらをとほさかりぬる みやきひく あつさのそまを かきわけて なにはのうらを とほさかりぬる | 能因法師 | 八 | 羈旅 |
| 506 | すみのえにまつらむとのみなけきつつ心つくしにとしをふるかな すみのえに まつらむとのみ なけきつつ こころつくしに としをふるかな | 津守有基 | 八 | 羈旅 |
| 507 | わかれゆく都のかたの恋しきにいさむすひみむ忘井の水 わかれゆく みやこのかたの こひしきに いさむすひみむ わすれゐのみつ | 斎宮甲斐 | 八 | 羈旅 |
| 508 | さ夜ふかき雲ゐに雁もおとすなりわれひとりやは旅の空なる さよふかき くもゐのかりも おとすなり われひとりやは たひのそらなる | 源雅光 | 八 | 羈旅 |
| 509 | かり衣そての涙にやとる夜は月もたひねの心ちこそすれ かりころも そてのなみたに やとるよは つきもたひねの ここちこそすれ | 崇徳院御製 | 八 | 羈旅 |
| 510 | 松かねの枕もなにかあたならむ玉のゆかとてつねのとこかは まつかねの まくらもなにか あたならむ たまのゆかとて つねのとこかは | 崇徳院御製 | 八 | 羈旅 |
| 511 | 花さきし野へのけしきも,かれぬこれにてそしる旅の日かすは はなさきし のへのけしきも しもかれぬ これにてそしる たひのひかすは | 大炊御門右大臣 | 八 | 羈旅 |
| 512 | さらしなやをはすて山に月みると都にたれかわれをしるらん さらしなや をはすてやまに つきみると みやこにたれか われをしるらむ | 藤原季通朝臣 | 八 | 羈旅 |
| 513 | 道すから心もそらになかめやるみやこの山の雲かくれぬる みちすから こころもそらに なかめやる みやこのやまの くもかくれぬる | 待賢門院堀川 | 八 | 羈旅 |
| 514 | ささのはをゆふ暮なからをりしけは玉ちるたひのくさ枕かな ささのはを ゆふつゆなから をりしけは たまちるたひの くさまくらかな | 同院安芸 | 八 | 羈旅 |
| 515 | うらつたふいそのとまやのかち枕ききもならはぬ浪のおとかな うらつたふ いそのとまやの かちまくら ききもならはぬ なみのおとかな | 皇太后宮大夫俊成 | 八 | 羈旅 |
| 516 | わたのはらはるかに浪をへたてきて都にいてし月をみるかな わたのはら はるかになみを へたてきて みやこにいてし つきをみるかな | 西行法師 | 八 | 羈旅 |
| 517 | さためなきうき世の中としりぬれはいつこも旅の心ちこそすれ さためなき うきよのなかと しりぬれは いつこもたひの ここちこそすれ | 高野法親王(覚法) | 八 | 羈旅 |
| 518 | おほつかないかになるみのはてならむ行へもしらぬたひのかなしさ おほつかな いかになるみの はてならむ ゆくへもしらぬ たひのかなしさ | 前中納言師仲 | 八 | 羈旅 |
| 519 | 日をへつつゆくにはるけき道なれとすゑをみやことおもはましかは ひをへつつ ゆくにはるけき みちなれと すゑをみやこと おもはましかは | 左京大夫修範 | 八 | 羈旅 |
| 520 | かくはかりあはれならしをしくるとも磯の松かねまくらならすは かくはかり あはれならしを しくるとも いそのまつかね まくらならすは | 読人不知 | 八 | 羈旅 |
| 521 | 月みれはまつ都こそこひしけれまつらんとおもふ人はなけれと つきみれは まつみやここそ こひしけれ まつらむとおもふ ひとはなけれと | 道因法師 | 八 | 羈旅 |
| 522 | あふさかの関には人もなかりけりいはまの水のもるにまかせて あふさかの せきにはひとも なかりけり いはまのみつの もるにまかせて | 祝部成仲 | 八 | 羈旅 |
| 523 | こえて行くともやなからむあふ坂のせきのし水のかけはなれなは こえてゆく ともやなからむ あふさかの せきのしみつの かけはなれなは | 大納言定房 | 八 | 羈旅 |
| 524 | たひ衣あさたつをのの露しけみしほりもあへすしのふもちすり たひころも あさたつをのの つゆしけみ しほりもあへす しのふもちすり | 前大僧正覚忠 | 八 | 羈旅 |
| 525 | 風のおとにわきそかねまし松かねのまくらにもらぬ時雨なりせは かせのおとに わきそかねまし まつかねの まくらにもらぬ しくれなりせは | 右近大将実房 | 八 | 羈旅 |
| 526 | もしほ草しきつのうらのねさめには時雨にのみや袖はぬれける もしほくさ しきつのうらの ねさめには しくれにのみや そてはぬれける | 俊恵法師 | 八 | 羈旅 |
| 527 | 玉もふくいそやかしたにもる時雨たひねのそてもしほたれよとや たまもふく いそやかしたに もるしくれ たひねのそても しほたれよとや | 源仲綱 | 八 | 羈旅 |
| 528 | 草枕おなしたひねの袖にまた夜はのしくれもやとはかりけり くさまくら おなしたひねの そてにまた よはのしくれも やとはかりけり | 太皇太后宮小侍従 | 八 | 羈旅 |
| 529 | はるはるとつもりのおきをこきゆけはきしの松かせとほさかるなり はるはると つもりのおきを こきゆけは きしのまつかせ とほさかるなり | 摂政前右大臣 | 八 | 羈旅 |
| 530 | わたのはらしほちはるかにみわたせは雲と浪とはひとつなりけり わたのはら しほちはるかに みわたせは くもとなみとは ひとつなりけり | 刑部卿頼輔 | 八 | 羈旅 |
| 531 | あはれなる野しまかさきのいほりかな露おく袖に浪もかけけり あはれなる のしまかさきの いほりかな つゆおくそてに なみもかけけり | 皇太后宮大夫俊成 | 八 | 羈旅 |
| 532 | よしさらは磯のとまやに旅ねせん浪かけすとてぬれぬ袖かは よしさらは いそのとまやに たひねせむ なみかけすとて ぬれぬそてかは | 仁和寺法親王(守覚) | 八 | 羈旅 |
| 533 | たひのよに又たひねして草まくらゆめのうちにも夢をみるかな たひのよに またたひねして くさまくら ゆめのうちにも ゆめをみるかな | 法印慈円 | 八 | 羈旅 |
| 534 | 草まくらかりねの夢にいくたひかなれし都にゆきかへるらん くさまくら かりねのゆめに いくたひか なれしみやこに ゆきかへるらむ | 左兵衛督隆房 | 八 | 羈旅 |
| 535 | いつもかく有あけの月のあけかたは物やかなしきすまの関守 いつもかく ありあけのつきの あけかたは ものやかなしき すまのせきもり | 法眼兼覚 | 八 | 羈旅 |
| 536 | たひねするすまのうらちのさよ千とりこゑこそ袖の浪はかけけれ たひねする すまのうらちの さよちとり こゑこそそての なみはかけけれ | 藤原家隆 | 八 | 羈旅 |
| 537 | かくしつつつひにとまらむよもきふのおもひしらるる草枕かな かくしつつ つひにとまらむ よもきふの おもひしらるる くさまくらかな | 円玄法師 | 八 | 羈旅 |
| 538 | たひねするこのした露の袖にまた時雨ふるなりさよの中山 たひねする このしたつゆの そてにまた しくれふるなり さよのなかやま | 律師覚弁 | 八 | 羈旅 |
| 539 | たひねするいほりをすくるむら時雨なこりまてこそ袖はぬれけれ たひねする いほりをすくる むらしくれ なこりまてこそ そてはぬれけれ | 藤原資忠 | 八 | 羈旅 |
| 540 | あられもるふはのせきやにたひねして夢をもえこそとほささりけれ あられもる ふはのせきやに たひねして ゆめをもえこそ とほささりけれ | 大中臣親守 | 八 | 羈旅 |
| 541 | かくはかりうき身のほともわすられて猶恋しきは都なりけり かくはかり うきみのほとも わすられて なほこひしきは みやこなりけり | 平康頼(法名性照) | 八 | 羈旅 |
| 542 | さつまかたおきの小島にわれありとおやにはつけよやへのしほかせ さつまかた おきのこしまに われありと おやにはつけよ やへのしほかせ | 平康頼(法名性照) | 八 | 羈旅 |
| 543 | あつまちも年もすゑにや成りぬらん雪ふりにけり白川のせき あつまちも としもすゑにや なりぬらむ ゆきふりにけり しらかはのせき | 僧都印性 | 八 | 羈旅 |
| 544 | いはねふみ嶺のしひしはをりしきて雲にやとかるゆふくれのそら いはねふみ みねのしひしは をりしきて くもにやとかる ゆふくれのそら | 寂蓮法師 | 八 | 羈旅 |
| 545 | 春くれはちりにし花もさきにけりあはれ別のかからましかは はるくれは ちりにしはなも さきにけり あはれわかれの かからましかは | 中務卿具平親王 | 九 | 哀傷 |
| 546 | 行きかへり春やあはれとおもふらん契りし人の又もあはねは ゆきかへり はるやあはれと おもふらむ ちりにしひとの またもあはねは | 大納言公任 | 九 | 哀傷 |
| 547 | うゑおきし人のかたみとみぬたにもやとのさくらをたれかをしまぬ うゑおきし ひとのかたみと みぬたにも やとのさくらを たれかをしまぬ | 藤原範永朝臣 | 九 | 哀傷 |
| 548 | をしきかなかたみにきたるふち衣たた此ころにくちはてぬへし をしきかな かたみにきたる ふちころも たたこのころに くちはてぬへし | 和泉式部 | 九 | 哀傷 |
| 549 | くちなしのそのにやわか身入りにけんおもふことをもいはてやみぬる くちなしの そのにやわかみ いりにけむ おもふことをも いはてやみぬる | 藤原道信朝臣 | 九 | 哀傷 |
| 550 | おもひかねきのふのそらをなかむれはそれかとみゆる雲たにもなし おもひかね きのふのそらを なかむれは それかとみゆる くもたにもなし | 藤原頼孝 | 九 | 哀傷 |
| 551 | うつつとも夢ともえこそわきはてねいつれの時をいつれとかせん うつつとも ゆめともえこそ わきはてね いつれのときを いつれとかせむ | 花山院御製 | 九 | 哀傷 |
| 552 | さくら花みるにもかなし中中にことしの春はさかすそあらまし さくらはな みるにもかなし なかなかに ことしのはるは さかすそあらまし | 源道済 | 九 | 哀傷 |
| 553 | おくれしとおもへとしなぬわかみかなひとりやしらぬ道をゆくらん おくれしと おもへとしなぬ わかみかな ひとりやしらぬ みちをゆくらむ | 道命法師 | 九 | 哀傷 |
| 554 | おいらくの命のあまりなかくして君に二たひわかれぬるかな おいらくの いのちのあまり なかくして きみにふたたひ わかれぬるかな | 藤原長能 | 九 | 哀傷 |
| 555 | 一こゑも君につけなんほとときすこの五月雨はやみにまとふと ひとこゑも きみにつけなむ ほとときす このさみたれは やみにまとふと | 上東門院 | 九 | 哀傷 |
| 556 | あやめ草なみたの玉にぬきかへてをりならぬねを猶そかけつる あやめくさ なみたのたまに ぬきかへて をりならぬねを なほそかけつる | 弁乳母 | 九 | 哀傷 |
| 557 | 玉ぬきしあやめのくさはありなからよとのはあれん物とやはみし たまぬきし あやめのくさは ありなから よとのはあれむ ものとやはみし | 江侍従 | 九 | 哀傷 |
| 558 | かなしさをかつはおもひもなくさめよたれもつひにはとまるへきかは かなしさを かつはおもひも なくさめよ たれもつひには とまるへきかは | 大弐三位 | 九 | 哀傷 |
| 559 | たれもみなとまるへきにはあらねともおくるるほとは猶そかなしき たれもみな とまるへきには あらねとも おくるるほとは なほそかなしき | 大納言長家 | 九 | 哀傷 |
| 560 | おほかたにさやけからぬか月かけは涙くもらぬ人にみせはや おほかたに さやけからぬか つきかけは なみたくもらぬ ひとにみせはや | 承香殿女御 | 九 | 哀傷 |
| 561 | かなしさにそへても物のかなしきはわかれのうちの別なりけり かなしさに そへてもものの かなしきは わかれのうちの わかれなりけり | 小弁命帰 | 九 | 哀傷 |
| 562 | うきもののさすかにをしきことしかなとほさかりなん君か別に うきものの さすかにをしき ことしかな とほさかりなむ きみかわかれに | 前中宮宣旨 | 九 | 哀傷 |
| 563 | かなしさはいととそまさる別れにしことしもけふをかき、りとおもへは かなしさは いととそまさる わかれにし ことしもけふを かきりとおもへは | 大納言長家 | 九 | 哀傷 |
| 564 | いつかたの雲ちとしらはたつねましつらはなれけん雁かゆくへを いつかたの くもちとしらは たつねまし つらはなれけむ かりかゆくへを | 紫式部 | 九 | 哀傷 |
| 565 | としをへて君かみなれしますかかみむかしの影はとまらさりけり としをへて きみかみなれし ますかかみ むかしのかけは とまらさりけり | 藤原道信朝臣 | 九 | 哀傷 |
| 566 | つねよりもまたぬれそひしたもとかなむかしをかけておちし涙に つねよりも またぬれそひし たもとかな むかしをかけて おちしなみたに | 赤染衛門 | 九 | 哀傷 |
| 567 | うつつともおもひわかれてすくるまにみしよの夢をなにかたりけん うつつとも おもひわかれて すくるまに みしよのゆめを なにかたりけむ | 上東門院 | 九 | 哀傷 |
| 568 | みやこへとおもふにつけてかなしきはたれかはいまは我をまつらん みやこへと おもふにつけて かなしきは たれかはいまは われをまつらむ | 源実基朝臣 | 九 | 哀傷 |
| 569 | もろともに春の花をはみしものを人におくるる秋そかなしき もろともに はるのはなをは みしものを ひとにおくるる あきそかなしき | 平雅康 | 九 | 哀傷 |
| 570 | 花とみし人はほとなくちりにけりわかみも風をまつとしらなん はなとみし ひとはほとなく ちりにけり わかみもかせを まつとしらなむ | 前中納言匡房 | 九 | 哀傷 |
| 571 | かわくまもなきすみそめのたもとかなくちなはなにをかたみにもせん かわくよも なきすみそめの たもとかな くちなはなにを かたみにもせむ | 藤原顕綱朝臣 | 九 | 哀傷 |
| 572 | すみそめのたもとにかかるねをみれはあやめもしらぬ涙なりけり すみそめの たもとにかかる ねをみれは あやめもしらぬ なみたなりけり | 権中納言俊忠 | 九 | 哀傷 |
| 573 | あやめ草うきねをみても涙のみかくらん袖をおもひこそやれ あやめくさ うきねをみても なみたのみ かからむそてを おもひこそやれ | 中納言国信 | 九 | 哀傷 |
| 574 | おもひやれむなしきとこをうちはらひむかしをしのふ袖のしつくを おもひやれ むなしきとこを うちはらひ むかしをしのふ そてのしつくを | 藤原基俊 | 九 | 哀傷 |
| 575 | むねにみつおもひをたにもはるかさて煙とならむことそかなしき むねにみつ おもひをたにも はるかさて けふりとならむ ことそかなしき | 贈皇太后★子 | 九 | 哀傷 |
| 576 | もろともに有明の月をみしものをいかなるやみに君まとふらん もろともに ありあけのつきを みしものを いかなるやみに きみまとふらむ | 藤原有信朝臣 | 九 | 哀傷 |
| 577 | うちならすかねのおとにやなかき夜もあけぬなりとはおもひしるらん うちならす かねのおとにや なかきよも あけぬなりとは おもひしるらむ | 慶範法師 | 九 | 哀傷 |
| 578 | かきりありて人はかたかたわかるとも涙をたにもととめてしかな かきりありて ひとはかたかた わかるとも なみたをたにも ととめてしかな | 崇徳院御製 | 九 | 哀傷 |
| 579 | ちりちりにわかるるけふのかなしさに涙しもこそとまらさりけれ ちりちりに わかるるけふの かなしさに なみたしもこそ とまらさりけれ | 上西門院兵衛 | 九 | 哀傷 |
| 580 | かなしさをこれよりけにやおもはましかねてならはぬ別なりせは かなしさを これよりけにや おもはまし かねてならはぬ わかれなりせは | 静厳法師 | 九 | 哀傷 |
| 581 | すみ染の色はいつれもかはらぬをぬれぬや君か衣なるらん すみそめの いろはいつれも かはらぬを ぬれぬやきみか ころもなるらむ | 天台座主勝範 | 九 | 哀傷 |
| 582 | つねよりもむつましきかなほとときすしての山ちのともとおもへは つねよりも むつましきかな ほとときす してのやまちの ともとおもへは | 鳥羽院御製 | 九 | 哀傷 |
| 583 | 心さしふかくそめてしふちころもきつる日かすのあさくもあるかな こころさし ふかくそめてし ふちころも きつるひかすの あさくもあるかな | 久我内のおほいまうちきみ | 九 | 哀傷 |
| 584 | たくひなくうきことみえしやとなれとそもわかるるはかなしかりけり たくひなく うきことみえし やとなれと そもわかるるは かなしかりけり | 大宮前おほきおほいまうち君 | 九 | 哀傷 |
| 585 | かそふれはむかしかたりに成りにけり別はいまの心ちすれとも かそふれは むかしかたりに なりにけり わかれはいまの ここちすれとも | 花薗左大臣の室 | 九 | 哀傷 |
| 586 | たなはたにことしはかさぬしひしはの袖しもことに露けかりけり たなはたに ことしはかさぬ しひしはの そてしもことに つゆけかりけり | 大納言実家 | 九 | 哀傷 |
| 587 | しひしはの露けき袖は七夕もかさぬにつけてあはれとやみん しひしはの つゆけきそては たなはたも かさぬにつけて あはれとやみむ | 三位(右大臣母) | 九 | 哀傷 |
| 588 | 故郷にけふこさりせはほとときすたれかむかしを恋ひてなかまし ふるさとに けふこさりせは ほとときす たれとむかしを こひてなかまし | 仁和寺後入道法親王(覚性) | 九 | 哀傷 |
| 589 | つねにみし君かみゆきをけふとへはかへらぬたひときくそかなしき つねにみし きみかみゆきを けふとへは かへらぬたひと きくそかなしき | 法印澄憲 | 九 | 哀傷 |
| 590 | をしへおくそのことのはをみるたひに又とふかたのなきそかなしき をしへおく そのことのはを みるたひに またとふかたの なきそかなしき | 右大臣 | 九 | 哀傷 |
| 591 | とりへ山おもひやるこそかなしけれひとりやこけの下にくちなん とりへやま おもひやるこそ かなしけれ ひとりやこけの したにくちなむ | 民部卿成範 | 九 | 哀傷 |
| 592 | かきり有りて二重はきねはふち衣なみたはかりをかさねつるかな かきりありて ふたへはきねは ふちころも なみたはかりを かさねつるかな | 藤原貞憲朝臣 | 九 | 哀傷 |
| 593 | 三とせまてなれしは夢の心ちしてけふそうつつの別なりける みとせまて なれしはゆめの ここちして けふそうつつの わかれなりける | 右京大夫季能 | 九 | 哀傷 |
| 594 | いりぬるかあかぬ別のかなしさをおもひしれとや山のはの月 いりぬるか あかぬわかれの かなしさを おもひしれとや やまのはのつき | 僧都印性 | 九 | 哀傷 |
| 595 | 野へみれはむかしのあとやたれならむその世もしらぬ苔のしたかな のへみれは むかしのあとや たれならむ そのよもしらぬ こけのしたかな | 左京大夫修範 | 九 | 哀傷 |
| 596 | なにことのふかき思ひにいつみ川そこの玉もとしつみはてけん なにことの ふかきおもひに いつみかは そこのたまもと しつみはてけむ | 僧都範玄 | 九 | 哀傷 |
| 597 | おもひきやけふうちならすかねのおとにつたへしふえのねをそへんとは おもひきや けふうちならす かねのおとに つたへしふえの ねをそへむとは | 法印成清 | 九 | 哀傷 |
| 598 | さきたたむことをうしとそおもひしにおくれても又かなしかりけり さきたたむ ことをうしとそ おもひしに おくれてもまた かなしかりけり | 静縁法師 | 九 | 哀傷 |
| 599 | まつらむとおもははいかにいそかましあとをみにたにまとふ心を まつらむと おもははいかに いそかまし あとをみにたに まとふこころを | 藤原親盛 | 九 | 哀傷 |
| 600 | 山のはにたなひく雲やゆくへなくなりし煙のかたみなるらん やまのはに たなひくくもや ゆくへなく なりしけふりの かたみなるらむ | 覚蓮法師(俗名隆行) | 九 | 哀傷 |
| 601 | 年をへてむかしをしのふ心のみうきにつけてもふかくさのさと としをへて むかしをしのふ こころのみ うきにつけても ふかくさのさと | 法眼長真 | 九 | 哀傷 |
| 602 | たらちめやとまりて我ををしまましかはるにかはる命なりせは たらちめや とまりてわれを をしままし かはるにかはる いのちなりせは | 顕昭法師 | 九 | 哀傷 |
| 603 | もろともになかめなかめて秋の月ひとりにならむことそかなしき もろともに なかめなかめて あきのつき ひとりにならむ ことそかなしき | 西行法師 | 九 | 哀傷 |
| 604 | みたれすとをはりきくこそうれしけれさても別はなくさまねとも みたれすと をはりきくこそ うれしけれ さてもわかれは なくさまねとも | 寂然法師 | 九 | 哀傷 |
| 605 | この世にて又あふましきかなしさにすすめし人そ心みたれし このよにて またあふましき かなしさに すすめしひとそ こころみたれし | 西行法師 | 九 | 哀傷 |
| 606 | いく千代とかきらさりけるくれ竹や君かよはひのたくひなるらん いくちよと かきらさりける くれたけや きみかよはひの たくひなるらむ | 院御製 | 十 | 賀 |
| 607 | うゑてみる籬の竹のふしことにこもれる千代は君そかそへん うゑてみる まかきのたけの ふしことに こもれるちよは きみそかそへむ | 後三条内大臣 | 十 | 賀 |
| 608 | わか友と君かみかきのくれ竹は千代にいく世のかけをそふらん わかともと きみかみかきの くれたけは ちよにいくよの かけをそふらむ | 皇太后宮大夫俊成 | 十 | 賀 |
| 609 | 君か代はあまのかこ山いつる日のてらむかきりはつきしとそ思ふ きみかよは あまのかこやま いつるひの てらむかきりは つきしとそおもふ | 大宮前太政大臣 | 十 | 賀 |
| 610 | 君かためみたらし川を若水にむすふや千代のはしめなるらん きみかため みたらしかはを わかみつに むすふやちよの はしめなるらむ | 源俊頼朝臣 | 十 | 賀 |
| 611 | 千とせまてをりてみるへきさくら花こすゑはるかにさきそめにけり ちとせまて をりてみるへき さくらはな こすゑはるかに さきそめにけり | 堀河院御製 | 十 | 賀 |
| 612 | ほりうゑしわかきのむめにさく花は年もかきらぬにほひなりけり ほりうゑし わかきのうめに さくはなは としもかきらぬ にほひなりけり | 大納言忠教 | 十 | 賀 |
| 613 | 千とせすむ池のみきはのやへさくらかけさヘそこにかさねてそみる ちとせすむ いけのみきはの やへさくら かけさへそこに かさねてそみる | 権中納言俊忠 | 十 | 賀 |
| 614 | 神代よりひさしかれとやうこきなきいはねに松のたねをまきけん かみよより ひさしかれとや うこきなき いはねにまつの たねをまきけむ | 源俊頼朝臣 | 十 | 賀 |
| 615 | おちたきつやそうち川のはやきせにいはこす浪は千代の数かも おちたきつ やそうちかはの はやきせに いはこすなみは ちよのかすかも | 源俊頼朝臣 | 十 | 賀 |
| 616 | ちはやふるいつきの宮のありす川松とともにそかけはすむへき ちはやふる いつきのみやの ありすかは まつとともにそ かけはすむへき | 京極前太政大臣 | 十 | 賀 |
| 617 | 行すゑをまつそひさしき君かへん千よのはしめの子日とおもへは ゆくすゑを まつそひさしき きみかへむ ちよのはしめの ねのひとおもへは | 二条太皇大后宮肥後 | 十 | 賀 |
| 618 | おく山のやつをのつはき君か代にいくたひかけをかへんとすらん おくやまの やつをのつはき きみかよに いくたひかけを かへむとすらむ | 藤原基俊 | 十 | 賀 |
| 619 | 君か代をなか月にしもしら菊のさくや千とせのしるしなるらん きみかよを なかつきにしも しらきくの さくやちとせの しるしなるらむ | 法性寺入道前太政大臣 | 十 | 賀 |
| 620 | やへきくのにほふにしるし君か代は千とせの秋をかさぬへしとは やへきくの にほひにしるし きみかよは ちとせのあきを かさぬへしとは | 花薗左大臣 | 十 | 賀 |
| 621 | ちはやふる神代のことも人ならは問はましものをしらきくのはな ちはやふる かみよのことも ひとならは とはましものを しらきくのはな | 八条前太政大臣 | 十 | 賀 |
| 622 | ふく風も木木のえたをはならさねと山はやちよのこゑそきこゆる ふくかせも ききのえたをは ならさねと やまはやちよの こゑそきこゆる | 崇徳院御製 | 十 | 賀 |
| 623 | 千代ふへきはしめの春としりかほにけしきことなる花さくらかな ちよふへき はしめのはると しりかほに けしきことなる はなさくらかな | 左大臣 | 十 | 賀 |
| 624 | しら雲にはねうちつけてとふたつのはるかに千代のおもほゆるかな しらくもに はねうちつけて とふたつの はるかにちよの おもほゆるかな | 二条院御製 | 十 | 賀 |
| 625 | うこきなくなほ万代そたのむへきはこやの山のみねの松かけ うこきなく なほよろつよそ たのむへき はこやのやまの みねのまつかけ | 式子内親王 | 十 | 賀 |
| 626 | ももちたひうらしまの子はかへるともはこやの山はときはなるへし ももちたひ うらしまのこは かへるとも はこやのやまは ときはなるへし | 皇太后宮大夫俊成 | 十 | 賀 |
| 627 | いく千代とかきらぬたつのこゑすなり雲井のちかきやとのしるしに いくちよと かきらぬたつの こゑすなり くもゐのちかき やとのしるしに | 大炊御門右大臣 | 十 | 賀 |
| 628 | 千とせふるをのへの小松うつしうゑて万代まてのともとこそみめ ちとせふる をのへのこまつ うつしうゑて よろつよまての ともとこそみめ | 入道前関白太政大臣 | 十 | 賀 |
| 629 | 万代もすむへきやとにうゑつれは松こそ君かかけをたのまめ よろつよも すむへきやとに うゑつれは まつこそきみか かけをたのまめ | 源通能朝臣 | 十 | 賀 |
| 630 | ふえのねの万代まてときこえしを山もこたふる心ちせしかな ふえのねの よろつよまてと きこえしを やまもこたふる ここちせしかな | 右おほいまうちきみ | 十 | 賀 |
| 631 | むれてゐるたつのけしきにしるきかな千とせすむへきやとの池水 むれてゐる たつのけしきに しるきかな ちとせすむへき やとのいけみつ | 修埋大夫顕季 | 十 | 賀 |
| 632 | みつかきのかつらをうつすやとなれは月みむことそひさしかるへき みつかきの かつらをうつす やとなれは つきみむことそ ひさしかるへき | 賀茂成助 | 十 | 賀 |
| 633 | 君か代にくらへていはは松山のまつのはかすはすくなかりけり きみかよに くらへていはは まつやまの まつのはかすは すくなかりけり | 藤原孝善 | 十 | 賀 |
| 634 | 千代とのみおなしことをそしらふなるなかたの山のみねの松かせ ちよとのみ おなしことをそ しらふなる なかたのやまの みねのまつかせ | 善滋為政 | 十 | 賀 |
| 635 | ちはやふる神田のさとのいねなれは月日とともにひさしかるへし ちはやふる かみたのさとの いねなれは つきひとともに ひさしかるへし | 前中納言匡房 | 十 | 賀 |
| 636 | すへらきのすゑさかゆへきしるしにはこたかくそなるわか松のもり すめらきの すゑさかゆへき しるしには こたかくそなる わかまつのもり | 宮内卿永範 | 十 | 賀 |
| 637 | 君か代のかすにはしかしかきりなきちさかのうらのまさこなりとも きみかよの かすにはしかし かきりなき ちさかのうらの まさこなりとも | 参議俊憲 | 十 | 賀 |
| 638 | あめつちのきはめもしらぬ御代なれは雲田のむらのいねをこそつけ あめつちの きはめもしらぬ みよなれは くもたのむらの いねをこそつけ | 刑部卿範兼 | 十 | 賀 |
| 639 | 霜ふれとさかえこそませ君か代にあふさか山のせきの杉もり しもふれと さかえこそませ きみかよに あふさかやまの せきのすきもり | 宮内卿永範 | 十 | 賀 |
| 640 | ときはなるみかみの山のすきむらややほ万代のしるしなるらん ときはなる みかみのやまの すきむらや やほよろつよの しるしなるらむ | 藤原季経朝臣 | 十 | 賀 |
| 641 | なにはえのもにうつもるる玉かしはあらはれてたに人をこひはや なにはえの もにうつもるる たまかしは あらはれてたに ひとをこひはや | 源俊頼朝臣 | 十一 | 恋一 |
| 642 | またしらぬ人をはしめてこふるかなおもふ心よみちしるへせよ またしらぬ ひとをはしめて こふるかな おもぬこころよ みちしるへせよ | 前太后宮肥後 | 十一 | 恋一 |
| 643 | わりなしやおもふ心の色ならはこれそそれともいはましものを わりなしや おもふこころの いろならは これそそれとも いはましものを | 河内 | 十一 | 恋一 |
| 644 | おもふよりいつしかぬるるたもとかな涙そ恋のしるへなりける おもふより いつしかぬるる たもとかな なみたそこひの しるへなりける | 後二条関白家筑前 | 十一 | 恋一 |
| 645 | もくつ火のいそまをわくるいさり船ほのかなりしにおもひそめてき もくつひの いそまをわくる いさりふね ほのかなりしに おもひそめてき | 藤原長能 | 十一 | 恋一 |
| 646 | いかにせんおもひを人にそめなから色に出てしとしのふ心を いかにせむ おもひをひとに そめなから いろにいてしと しのふこころを | 延久三親王(輔仁) | 十一 | 恋一 |
| 647 | ひとめみし人はたれともしら雲のうはのそらなる恋もするかな ひとめみし ひとはたれとも しらくもの うはのそらなる こひもするかな | 徳大寺左大臣 | 十一 | 恋一 |
| 648 | つつめとも涙にそてのあらはれて恋すと人にしられぬるかな つつめとも なみたにそての あらはれて こひすとひとに しられぬるかな | 中院右大臣 | 十一 | 恋一 |
| 649 | つつめともたへぬ思ひになりぬれは問はすかたりのせまほしきかな つつめとも たへぬおもひに なりぬれは とはすかたりの せまほしきかな | 大納言成通 | 十一 | 恋一 |
| 650 | おほかたの恋する人にききなれてよのつねのとや君おもふらん おほかたの こひするひとに ききなれて よのつねのとや きみおもふらむ | 大炊御門右大臣 | 十一 | 恋一 |
| 651 | 思へともいはての山に年をへてくちやはてなん谷の埋木 おもへとも いはてのやまに としをへて くちやはてなむ たにのうもれき | 左京大夫顕輔 | 十一 | 恋一 |
| 652 | たかさこのをのへの松にふくかせのおとにのみやはききわたるへき たかさこの をのへのまつに ふくかせの おとにのみやは ききわたるへき | 左京大夫顕輔 | 十一 | 恋一 |
| 653 | あらいそのいはにくたくる浪なれやつれなき人にかくる心は あらいその いはにくたくる なみなれや つれなきひとに かくるこころは | 待賢門院堀河 | 十一 | 恋一 |
| 654 | いはまゆく山のした水せきわひてもらす心のほとをしらなん いはまゆく やましたみつを せきわひて もらすこころの ほとをしらなむ | 上西門院兵衛 | 十一 | 恋一 |
| 655 | みこもりにいはてふるやのしのふ草しのふとたにもしらせてしかな みこもりに いはてふるやの しのふくさ しのふとたにも しらせてしかな | 藤原基俊 | 十一 | 恋一 |
| 656 | おもふこといはまにまきし松のたね千代とちきらむ今はねさせよ おもふこと いはまにまきし まつのたね ちよとちきらむ いまはねさせよ | 藤原長能 | 十一 | 恋一 |
| 657 | おほつかなうるまの島の人なれやわかことのはをしらぬかほなる おほつかな うるまのしまの ひとなれや わかことのはを しらぬかほなる | 前大納言公任 | 十一 | 恋一 |
| 658 | 人しれす物おもふころの袖みれは雨も涙もわかれさりけり ひとしれす ものおもふころの そてみれは あめもなみたも わかれさりけり | 堀河右大臣 | 十一 | 恋一 |
| 659 | たちしよりはれすも物を思ふかななき名や野への霞なるらん たちしより はれすもものを おもふかな なきなやのへの かすみなるらむ | 源俊頼朝臣 | 十一 | 恋一 |
| 660 | なけきあまりしらせそめつることのはも思ふはかりはいはれさりけり なけきあまり しらせそめつる ことのはも おもふはかりは いはれさりけり | 源明賢朝臣 | 十一 | 恋一 |
| 661 | 人しれぬこのはのしたのむもれ水おもふ心をかきなかさはや ひとしれぬ このはのしたの うもれみつ おもふこころを かきなかさはや | 右のおほいまうちきみ | 十一 | 恋一 |
| 662 | 恋しともいはぬにぬるるたもとかな心をしるは涙なりけり こひしとも いはぬにぬるる たもとかな こころをしるは なみたなりけり | 久我内大臣 | 十一 | 恋一 |
| 663 | おもへともいはてしのふのすり衣こころのうちにみたれぬるかな おもへとも いはてしのふの すりころも こころのうちに みたれぬるかな | 前右京権大夫頼政 | 十一 | 恋一 |
| 664 | みちのくのしのふもちすりしのひつつ色には出てしみたれもそする みちのくの しのふもちすり しのひつつ いろにはいてし みたれもそする | 寂然法師 | 十一 | 恋一 |
| 665 | なにはめのすくもたく火のしたこかれうへはつれなきわかみなりけり なにはめの すくもたくひの したこかれ うへはつれなき わかみなりけり | 藤原清輔朝臣 | 十一 | 恋一 |
| 666 | こひしなは世のはかなきにいひおきてなきあとまても人にしられし こひしなは よのはかなきに いひおきて なきあとまても ひとにしられし | 刑部卿頼輔 | 十一 | 恋一 |
| 667 | 人しれぬ涙の川のみなかみやいはての山の谷のした水 ひとしれぬ なみたのかはの みなかみや いはてのやまの たにのしたみつ | 顕昭法師 | 十一 | 恋一 |
| 668 | いかにせむみかきかはらにつむせりのねにのみなけとしる人のなき いかにせむ みかきかはらに つむせりの ねにのみなけと しるひとのなき | 読人知らず | 十一 | 恋一 |
| 669 | つれもなき人の心やあふさかのせきちへたつるかすみなるらん つれもなき ひとのこころや あふさかの せきちへたつる かすみなるらむ | 賀茂重保 | 十一 | 恋一 |
| 670 | 涙川うきねのとりとなりぬれと人にはえこそみなれさりけれ なみたかは うきねのとりと なりぬれと ひとにはえこそ みなれさりけれ | 藤原清輔朝臣 | 十一 | 恋一 |
| 671 | わか恋はをはな吹きこす秋かせのおとにはたてしみにはしむとも わかこひは をはなふきこす あきかせの おとにはたてし みにはしむとも | 源通能朝臣 | 十一 | 恋一 |
| 672 | 世をいとふはしとおもひしかよひちにあやなく人を恋ひわたるかな よをいとふ はしとおもひし かよひちに あやなくひとを こひわたるかな | 仁昭法師 | 十一 | 恋一 |
| 673 | たよりあらはあまのつり舟ことつてむ人をみるめにもとめわひぬる たよりあらは あまのつりふね ことつてむ ひとをみるめに もとめわひぬる | 花薗左大臣 | 十一 | 恋一 |
| 674 | またもなくたたひとすちに君思ふ恋ちにまとふ我やなになる またもなく たたひとすちに きみおもふ こひちにまとふ われやなになる | 大宮前太政大臣 | 十一 | 恋一 |
| 675 | 君こふるみはおほそらにあらねとも月日をおほくすくしつるかな きみこふる みはおほそらに あらねとも つきひをおほく すくしつるかな | 前中納言伊房 | 十一 | 恋一 |
| 676 | ことのねにかよひそめぬる心かな松ふく風にあらぬ身なれと ことのねに かよひそめぬる こころかな まつふくかせに あらぬみなれと | 二条院御製 | 十一 | 恋一 |
| 677 | はかなしや枕さためぬうたたねにほのかにまよふ夢のかよひち はかなしや まくらさためぬ うたたねに ほのかにまよふ ゆめのかよひち | 式子内親王 | 十一 | 恋一 |
| 678 | さきにたつ涙とならは人しれす恋ちにまとふ道しるへせよ さきにたつ なみたとならは ひとしれす こひちにまとふ みちしるへせよ | 右大臣 | 十一 | 恋一 |
| 679 | なからへはつらき心もかはるやとさためなき世をたのむはかりそ なからへは つらきこころも かはるやと さためなきよを たのむはかりそ | 刑部卿頼輔 | 十一 | 恋一 |
| 680 | もらさはやしのひはつへき涙かは袖のしからみかくとはかりも もらさはや しのひはつへき なみたかは そてのしからみ かくとはかりは | 源有房 | 十一 | 恋一 |
| 681 | 恋しさをうきみなりとてつつみしはいつまてありし心なるらん こひしさを うきみなりとて つつみしは いつまてありし こころなるらむ | 源師光 | 十一 | 恋一 |
| 682 | たのめとやいなとやいかにいな舟のしはしとまちしほともへにけり たのめとや いなとやいかに いなふねの しはしとまちし ほともへにけり | 藤原惟規 | 十一 | 恋一 |
| 683 | かくはかり色に出てしとしのへともみゆらむものをたへぬけしきは かくはかり いろにいてしと しのへとも みゆらむものを たへぬけしきは | 賢智法師 | 十一 | 恋一 |
| 684 | 人しれすおもふこころはふかみくさ花さきてこそ色にいてけれ ひとしれす おもふこころは ふかみくさ はなさきてこそ いろにいてけれ | 賀茂重保 | 十一 | 恋一 |
| 685 | ひをへつつしけさはまさるおもひ草あふことのはのなとなかるらん ひをへつつ しけさはまさる おもひくさ あふことのはの なとなかるらむ | 津守国光 | 十一 | 恋一 |
| 686 | おつれとものきにしられぬ玉水は恋のなかめのしつくなりけり おつれとも のきにしられぬ たまみつは こひのなかめの しつくなりけり | 大中臣清文 | 十一 | 恋一 |
| 687 | 人しれすおもひそめてし心こそいまは涙の色となりけれ ひとしれす おもひそめてし こころこそ いまはなみたの いろとなりけれ | 源季貞 | 十一 | 恋一 |
| 688 | 色見えぬ心のほとをしらするはたもとをそむる涙なりけり いろみえぬ こころのほとを しらするは たもとをそむる なみたなりけり | 祐盛法師 | 十一 | 恋一 |
| 689 | わかとこはしのふのおくのますけはら露かかりてもしる人のなき わかとこは しのふのおくの ますけはら つゆかかりても しるひとのなき | 大中臣定雅 | 十一 | 恋一 |
| 690 | 君こふる涙しくれとふりぬれはしのふの山も色つきにけり きみこふる なみたしくれと ふりぬれは しのふのやまも いろつきにけり | 祝部宿禰成仲 | 十一 | 恋一 |
| 691 | いかにせむしのふの山のしたもみちしくるるままに色のまさるを いかにせむ しのふのやまの したもみち しくるるままに いろのまさるを | 二条院前皇后宮常陸 | 十一 | 恋一 |
| 692 | いつしかと袖にしくれのそそくかなおもひは冬のはしめならねと いつしかと そてにしくれの そそくかな おもひはふゆの はしめならねと | 賀茂重延 | 十一 | 恋一 |
| 693 | あさましやおさふる袖のしたくくる涙のすゑを人やみつらん あさましや おさふるそての したくくる なみたのすゑを ひとやみつらむ | 前右京権大夫頼政 | 十一 | 恋一 |
| 694 | しのひねのたもとは色にいてにけり心にもにぬわか涙かな しのひねの たもとはいろに いてにけり こころにもにぬ わかなみたかな | 皇嘉門院別当 | 十一 | 恋一 |
| 695 | おなしくはかさねてしほれぬれ衣さてもほすへきなき名ならしを おなしくは かさねてしほれ ぬれころも さてもほすへき なきなならしを | 左兵衛督隆房 | 十一 | 恋一 |
| 696 | なかれてもすすきやするとぬれ衣人はきすともみにはならさし なかれても すすきやすると ぬれころも ひとはきすとも みにはならさし | 読人知らず | 十一 | 恋一 |
| 697 | 人めをはつつむとおもふにせきかねて袖にあまるは涙なりけり ひとめをは つつむとおもふに せきかねて そてにあまるは なみたなりけり | 権大納言宗家 | 十一 | 恋一 |
| 698 | つれなさにいはてたえなんと思ふこそあひみぬさきの別なりけれ つれなさに いはてたえなむと おもふこそ あひみぬさきの わかれなりけれ | 右京大夫季能 | 十一 | 恋一 |
| 699 | よそ人にとはれぬるかな君にこそみせはやと思ふ袖のしつくを よそひとに とはれぬるかな きみにこそ みせはやとおもふ そてのしつくを | 法眼実快 | 十一 | 恋一 |
| 700 | つれなくそ夢にもみゆるさよ衣うらみんとては返しやはせし つれなくそ ゆめにもみゆる さよころも うらみむとては かへしやはせし | 藤原伊綱 | 十一 | 恋一 |
| 701 | おもひいつるそのなくさめもありなましあひみて後のつらさなりせは おもひいつる そのなくさめも ありなまし あひみてのちの つらさなりせは | 藤原季経朝臣 | 十一 | 恋一 |
| 702 | ともしするは山かすそのした露やいるより袖はかくしをるらん ともしする はやまかすその したつゆや いるよりそては かくしをるらむ | 皇太后宮大夫俊成 | 十一 | 恋一 |
| 703 | いかにせんむろのや島にやともかな恋のけふりをそらにまかへん いかにせむ むろのやしまに やともかな こひのけふりを そらにまかへむ | 皇太后宮大夫俊成 | 十一 | 恋一 |
| 704 | おもひあまり人にとははやみなせ川むすはぬ水に袖はぬるやと おもひあまり ひとにとははや みなせかは むすはぬみつに そてはぬるやと | 大納言公実 | 十二 | 恋二 |
| 705 | はかなくも人に心をつくすかなみのためにこそ思ひそめしか はかなくも ひとにこころを つくすかな みのためにこそ おもひそめしか | 花薗左大臣 | 十二 | 恋二 |
| 706 | 恋ひそめし人はかくこそつれなけれわか涙しも色かはるらん こひそめし ひとはかくこそ つれなけれ わかなみたしも いろかはるらむ | 二条太皇太后宮大弐 | 十二 | 恋二 |
| 707 | かかりける涙と人もみるはかりしはらし袖よくちはてねたた かかりける なみたとひとも みるはかり しほらしそてよ くちはてねたた | 前中納言雅兼 | 十二 | 恋二 |
| 708 | うかりける人をはつせの山おろしよはけしかれとはいのらぬものを うかりける ひとをはつせの やまおろしよ はけしかれとは いのらぬものを | 源俊頼朝臣 | 十二 | 恋二 |
| 709 | うれしくはのちの心を神もきけひくしめなはのたえしとそおもふ うれしくは のちのこころを かみもきけ ひくしめなはの たえしとそおもふ | 修埋大夫顕季 | 十二 | 恋二 |
| 710 | むすひおくふしみのさとの草枕とけてやみぬるたひにも有るかな むすひおく ふしみのさとの くさまくら とけてやみぬる たひにもあるかな | 藤原顕仲朝臣 | 十二 | 恋二 |
| 711 | こひこひてかひもなきさにおきつ浪よせてはやかて立ちかへれとや こひこひて かひもなきさに おきつなみ よせてはやかて たちかへれとや | 権中納言俊忠 | 十二 | 恋二 |
| 712 | いかてわれつれなき人に身をかへて恋しきほとを思ひしらせん いかてわれ つれなきひとに みをかへて こひしきほとを おもひしらせむ | 徳大寺左大臣 | 十二 | 恋二 |
| 713 | 玉もかるのしまの浦のあまたにもいとかく袖はぬるるものかは たまもかる のしまのうらの あまたにも いとかくそては ぬるるものかは | 源雅光 | 十二 | 恋二 |
| 714 | あふことをその年月とちきらねは命や恋のかきりなるらん あふことを そのとしつきと ちきらねは いのちやこひの かきりなるらむ | 藤原重基 | 十二 | 恋二 |
| 715 | 恋ひわたる涙の川にみをなけんこの世ならてもあふせありやと こひわたる なみたのかはに みをなけむ このよならても あふせありやと | 藤原宗兼朝臣 | 十二 | 恋二 |
| 716 | みちのくのとつなのはしにくるつなのたえすも人にいひわたるかな みちのくの とつなのはしに くるつなの たえすもひとに いひわたるかな | 前参議親隆 | 十二 | 恋二 |
| 717 | こひわたるけふの涙にくらふれはきのふの袖はぬれしものかは こひわたる けふのなみたに くらふれは きのふのそては ぬれしものかは | 院御製 | 十二 | 恋二 |
| 718 | あさまたき露をさなからささめかるしつか袖たにかくはぬれしを あさまたき つゆをさなから ささめかる しつかそてたに かくはぬれしを | 右おほいまうちきみ | 十二 | 恋二 |
| 719 | しほたるるいせをのあまやわれならんさらはみるめをかるよしもかな しほたるる いせをのあまや われならむ さらはみるめを かるよしもかな | 権大納言実国 | 十二 | 恋二 |
| 720 | よしさらはあふとみつるになくさまんさむるうつつも夢ならぬかは よしさらは あふとみつるに なくさまむ さむるうつつも ゆめならぬかは | 権大納言実家 | 十二 | 恋二 |
| 721 | いかはかりおもふとしりてつらからんあはれ涙の色をみせはや いかはかり おもふとしりて つらからむ あはれなみたの いろをみせはや | 右衛門督頼実 | 十二 | 恋二 |
| 722 | 恋ひしなん命を誰にゆつりおきてつれなき人のはてをみせまし こひしなむ いのちをたれに ゆつりおきて つれなきひとの はてをみせまし | 俊恵法師 | 十二 | 恋二 |
| 723 | せきかぬる涙の川のはやきせはあふよりほかのしからみそなき せきかぬる なみたのかはの はやきせは あふよりほかの しからみそなき | 前右京権大夫頼政 | 十二 | 恋二 |
| 724 | わか恋はとしふるかひもなかりけりうらやましきはうちのはし守 わかこひは としふるかひも なかりけり うらやましきは うちのはしもり | 藤原顕方 | 十二 | 恋二 |
| 725 | なれてのちしなん別のかなしきに命にかへぬあふこともかな なれてのち しなむわかれの かなしきに いのちにかへぬ あふこともかな | 道因法師 | 十二 | 恋二 |
| 726 | にしききの千つかにかきりなかりせは猶こりすまにたてましものを にしききの ちつかにかきり なかりせは なほこりすまに たてましものを | 賀茂重保 | 十二 | 恋二 |
| 727 | いかはかり恋ちはとほき物なれはとしはゆけともあふよなからん いかはかり こひちはとほき ものなれは としはゆけとも あふよなからむ | 前参議教長 | 十二 | 恋二 |
| 728 | なれてのちつらからましにくらふれはなき名はことのかすならぬかな なれてのち つらからましに くらふれは なきなはことの かすならぬかな | 三宮家越後 | 十二 | 恋二 |
| 729 | あひみむとおもひなよりそしら浪のたちけん名たにをしきみきはを あひみむと おもひなよりそ しらなみの たちけむなたに をしきみきはを | 法性寺入道前太政大臣家参川 | 十二 | 恋二 |
| 730 | 恋ひしなんみはをしからすあふことにかへんほとまてと思ふはかりそ こひしなむ みはをしからす あふことに かへむほとまてと おもふはかりそ | 道因法師 | 十二 | 恋二 |
| 731 | いまはさはあひみむまてはかたくとも命とならむことのはもかな いまはさは あひみむまては かたくとも いのちとならむ ことのはもかな | 左京大夫顕輔 | 十二 | 恋二 |
| 732 | 一かたになひくもしほの煙かなつれなき人のかからましかは ひとかたに なひくもしほの けふりかな つれなきひとの かからましかは | 平忠盛朝臣 | 十二 | 恋二 |
| 733 | 恋ひわひぬちぬのますらをならなくにいくたの川にみをやなけまし こひわひぬ ちぬのますらを ならなくに いくたのかはに みをやなけまし | 藤原道経 | 十二 | 恋二 |
| 734 | 命をはあふにかへんとおもひしを恋ひしぬとたにしらせてしかな いのちをは あふにかへむと おもひしを こひしぬとたに しらせてしかな | 寂超法師 | 十二 | 恋二 |
| 735 | こひしとも又つらしともおもひやる心いつれかさきにたつらん こひしとも またつらしとも おもひやる こころいつれか さきにたつらむ | 源師光 | 十二 | 恋二 |
| 736 | あふならぬ恋なくさめのあらはこそつれなしとてもおもひたえなめ あふならぬ こひなくさめの あらはこそ つれなしとても おもひたえなめ | 道因法師 | 十二 | 恋二 |
| 737 | つれなさにいまは思ひもたえなましこの世ひとつの契なりせは つれなさに いまはおもひも たえなまし このよひとつの ちきりなりせは | 顕昭法師 | 十二 | 恋二 |
| 738 | うたたねの夢にあひみて後よりは人もたのめぬくれそまたるる うたたねの ゆめにあひみて のちよりは ひともたのめぬ くれそまたるる | 源慶法師 | 十二 | 恋二 |
| 739 | あはれとも枕はかりやおもふらむ涙たえせぬよはのけしきを あはれとも まくらはかりや おもふらむ なみたたえせぬ よはのけしきを | 朝恵法師 | 十二 | 恋二 |
| 740 | 衣手におつる涙の色なくは露とも人にいはましものを ころもてに おつるなみたの いろなくは つゆともひとに いはましものを | 二条院内侍参川 | 十二 | 恋二 |
| 741 | おもふことしのふにいととそふ物はかすならぬみのなけきなりけり おもふこと しのふにいとと そふものは かすならぬみの なけきなりけり | 殷富門院大輔 | 十二 | 恋二 |
| 742 | 行きかへる心に人のなるれはやあひみぬさきに恋しかるらん ゆきかへる こころにひとの なるれはや あひみぬさきに こひしかるらむ | 摂政前右大臣 | 十二 | 恋二 |
| 743 | あふことをさりともとのみおもふかなふしみのさとの名をたのみつつ あふことを さりともとのみ おもふかな ふしみのさとの なをたのみつつ | 左衛門督家通 | 十二 | 恋二 |
| 744 | なとやかくさもくれかたきおほそらそわかまつことはありとしらすや なとやかく さもくれかたき おほそらそ わかまつことは ありとしらすや | 二条院御製 | 十二 | 恋二 |
| 745 | 袖の色は人のとふまてなりもせよふかきおもひを君したのまは そてのいろは ひとのとふまて なりもせよ ふかきおもひを きみしたのまは | 式子内親王 | 十二 | 恋二 |
| 746 | 秋はをし契はまたるとにかくに心にかかるくれのそらかな あきはをし ちきりはまたる とにかくに こころにかかる くれのそらかな | 左近中将良経 | 十二 | 恋二 |
| 747 | 恋をのみしくるる空のうき雲はくもりもあへす袖ぬらしけり こひをのみ しくるるそらの うきくもは くもりもあへす そてぬらしけり | 藤原成家朝臣 | 十二 | 恋二 |
| 748 | いそかくれかきはやれとももしほ草たちくる浪にあらはれやせん いそかくれ かきはやれとも もしほくさ たちくるなみに あらはれやせむ | 藤原家実 | 十二 | 恋二 |
| 749 | くれにともちきりてたれかかへるらんおもひたえたる曙の空 くれにとも ちきりてたれか かへるらむ おもひたえたる あけほののそら | 藤原家隆 | 十二 | 恋二 |
| 750 | 契りおくそのことのはにみをかへてのちの世にたにあひみてしかな ちきりおく そのことのはに みをかへて のちのよにたに あひみてしかな | 読人知らず | 十二 | 恋二 |
| 751 | 誰ゆゑかあくかれにけん雲まよりみし月かけはひとりならしを たれゆゑか あくかれにけむ くもまより みしつきかけは ひとりならしを | 殷富門院尾張 | 十二 | 恋二 |
| 752 | こえやらて恋ちにまよふあふ坂や世を出てはてぬせきとなるらん こえやらて こひちにまよふ あふさかや よをいてはてぬ せきとなるらむ | 藤原家基 | 十二 | 恋二 |
| 753 | たまくらのうへにみたるるあさねかみしたにとけすと人はしらしな たまくらの うへにみたるる あさねかみ したにとけすと ひとはしらしな | 西住法師 | 十二 | 恋二 |
| 754 | わか袖のしほのみちひるうらならは涙のよらぬをりもあらまし わかそての しほのみちひる うらならは なみたのよらぬ をりもあらまし | 前右京権大夫頼政 | 十二 | 恋二 |
| 755 | しほたるる袖のひるまはありやともあはてのうらのあまにとははや しほたるる そてのひるまは ありやとも あはてのうらの あまにとははや | 法印静賢 | 十二 | 恋二 |
| 756 | おもひきや夢を此世のちきりにてさむる別をなけくへしとは おもひきや ゆめをこのよの ちきりにて さむるわかれを なけくへしとは | 俊恵法師 | 十二 | 恋二 |
| 757 | われゆゑの涙とこれをよそにみはあはれなるへき袖のうへかな われゆゑの なみたとこれを よそにみは あはれなるへき そてのうへかな | 藤原隆信朝臣 | 十二 | 恋二 |
| 758 | あふことのかくかたけれはつれもなき人の心やいは木なるらん あふことの かくかたけれは つれもなき ひとのこころや いはきなるらむ | 賀茂政平 | 十二 | 恋二 |
| 759 | 恋ひしなん涙のはてやわたり川ふかきなかれとならんとすらん こひしなむ なみたのはてや わたりかは ふかきなかれと ならむとすらむ | 源光行 | 十二 | 恋二 |
| 760 | わか袖はしほひにみえぬおきの石の人こそしらねかわくまそなき わかそては しほひにみえぬ おきのいしの ひとこそしらね かわくまそなき | 二条院讃岐 | 十二 | 恋二 |
| 761 | かかりけるなけきはなにのむくいそとしる人あらはとはましものを かかりける なけきはなにの むくひそと しるひとあらは とはましものを | 民部卿成範 | 十二 | 恋二 |
| 762 | 恋ひしなんことそはかなきわたり河あふせありとはきかぬものゆゑ こひしなむ ことそはかなき わたりかは あふせありとは きかぬものゆゑ | 大宰大弐重家 | 十二 | 恋二 |
| 763 | いもかあたりなかるる川のせによらはあわとなりてもきえんとそ思ふ いもかあたり なかるるかはの せによらは あわとなりても きえむとそおもふ | 刑部卿範兼 | 十二 | 恋二 |
| 764 | (ツネフ) はかなしな心つくしに年をへていつともしらぬあふの松原 | 権中納言経房 | 十二 | 恋二 |
| 765 | おもひねの夢たにみえてあけぬれはあはても鳥のねこそつらけれ おもひねの ゆめたにみえて あけぬれは あはてもとりの ねこそつらけれ | 寂蓮法師 | 十二 | 恋二 |
| 766 | よもすから物思ふころはあけやらぬねやのひまさへつれなかりけり よもすから ものおもふころは あけやらぬ ねやのひまさへ つれなかりけり | 俊恵法師 | 十二 | 恋二 |
| 767 | いたつらにしをるる袖をあさ露にかへるたもととおもはましかは いたつらに しをるるそてを あさつゆに かへるたもとと おもはましかは | 俊恵法師 | 十二 | 恋二 |
| 768 | 恋ゆゑはさもあらぬ人そうらめしきわれよそならはとはましものを こひゆゑは さもあらぬひとそ うらめしき われよそならは とはましものを | 菅原是忠 | 十二 | 恋二 |
| 769 | おもひせく心のうちのしからみもたへすなりゆく涙川かな おもひせく こころのうちの しからみも たへすなりゆく なみたかはかな | 藤原親盛 | 十二 | 恋二 |
| 770 | おのつからつらき心もかはるやとまちみむほとの命ともかな おのつから つらきこころも かはるやと まちみむほとの いのちともかな | 静縁法師 | 十二 | 恋二 |
| 771 | わすらるるうき名はさても立ちにけり心のうちはおもひわけとも わすらるる うきなはさても たちにけり こころのうちは おもひわけとも | 大江維順女 | 十二 | 恋二 |
| 772 | よとともにつれなき人を恋くさの露こほれます秋のゆふかせ よとともに つれなきひとを こひくさの つゆこほれます あきのゆふかせ | 藤原顕家朝臣 | 十二 | 恋二 |
| 773 | 恋しさをいかかはすへきおもへともみはかすならす人はつれなし こひしさを いかかはすへき おもへとも みはかすならす ひとはつれなし | 源師光 | 十二 | 恋二 |
| 774 | こひしなは我ゆゑとたにおもひ出てよさこそはつらき心なりとも こひしなは われゆゑとたに おもひいてよ さこそはつらき こころなりとも | 権大納言実国 | 十二 | 恋二 |
| 775 | ひたすらにうらみしもせしさきの世にあふまてこそはちきらさりけめ ひたすらに うらみしもせし さきのよに あふまてこそは ちきらさりけめ | 左衛門督家通 | 十二 | 恋二 |
| 776 | ますかかみ心もうつるものならはさりともいまはあはれとやみん ますかかみ こころもうつる ものならは さりともいまは あはれとやみむ | 藤原公衡朝臣 | 十二 | 恋二 |
| 777 | いましはしそらたのめにもなくさめておもひたえぬるよひの玉つさ いましはし そらたのめにも なくさめて おもひたえぬる よひのたまつさ | 権中納言通親 | 十二 | 恋二 |
| 778 | そま川のあさからすこそ契りしかなとこのくれをひきたかふらん そまかはの あさからすこそ ちきりしか なとこのくれを ひきたかふらむ | 藤原盛方朝臣 | 十二 | 恋二 |
| 779 | おもひきやしちのはしかきかきつめてもも夜もおなしまろねせんとは おもひきや しちのはしかき かきつめて ももよもおなし まろねせむとは | 皇太后宮大夫俊成 | 十二 | 恋二 |
| 780 | ちきりこしことのたかふそたのもしきつらさもかくやかはるとおもへは ちきりこし ことのたかふそ たのもしき つらさもかくや かはるとおもへは | 藤原実方朝臣 | 十三 | 恋三 |
| 781 | しらしかしおもひも出てぬ心にはかくわすられすわれなけくとも しらしかし おもひもいてぬ こころには かくわすられす われなけくとも | 相模 | 十三 | 恋三 |
| 782 | つれもなくなりぬる人の玉つさをうき思出のかたみともせし つれもなく なりぬるひとの たまつさを うきおもひての かたみともせし | 藤原長能 | 十三 | 恋三 |
| 783 | やはらかにぬる夜もなくて別れぬるよよの手枕いつかわすれん やはらかに ぬるよもなくて わかれぬる よよのたまくら いつかわすれむ | 藤原長能 | 十三 | 恋三 |
| 784 | たなはたにかしつとおもひしあふことをそのよなき名のたちにけるかな たなはたに かしつとおもひし あふことを そのよなきなの たちにけるかな | 小大君 | 十三 | 恋三 |
| 785 | うらめしやむすほほれたる下ひものとけぬやなにの心なるらん うらめしや むすほほれたる したひもの とけぬやなにの こころなるらむ | 宇治前太政大臣 | 十三 | 恋三 |
| 786 | したひもは人のこふるにとくなれはたかつらきにかむすほほるらん したひもは ひとのこふるに とくなれは たかつらきにか むすほほるらむ | 弁乳母 | 十三 | 恋三 |
| 787 | ひとりぬるわれにてしりぬ池水につかはぬをしのおもふ心を ひとりぬる われにてしりぬ いけみつに つかはぬをしの おもふこころを | 太納言公実 | 十三 | 恋三 |
| 788 | 恋をのみしつのをたまきくるしきはあはて年ふる思ひなりけり こひをのみ しつのをたまき くるしきは あはてとしふる おもひなりけり | 中納言師時 | 十三 | 恋三 |
| 789 | あさてほすあつまをとめのかやむしろしきしのひてもすくすころかな あさてほす あつまをとめの かやむしろ しきしのひても すくすころかな | 源俊頼朝臣 | 十三 | 恋三 |
| 790 | よとともに行かたもなき心かな恋はみちなき物にそ有りける よとともに ゆくかたもなき こころかな こひはみちなき ものにそありける | 修理大夫顕季 | 十三 | 恋三 |
| 791 | 旅衣涙のいろのしるけれは露にもえこそかこたさりけり たひころも なみたのいろの しるけれは つゆにもえこそ かこたさりけり | 僧都覚雅 | 十三 | 恋三 |
| 792 | みつしほにすゑはをあらふなかれあしの君をそおもふうきみしつみみ みつしほに すゑはをあらふ なかれあしの きみをそおもふ うきみしつみみ | 大納言公実 | 十三 | 恋三 |
| 793 | わか恋はあまのかるもにみたれつつかわく時なき浪のしたくさ わかこひは あまのかるもに みたれつつ かわくときなき なみのしたくさ | 権中納言俊忠 | 十三 | 恋三 |
| 794 | なほさりにみわの杉とはをしへおきてたつぬる時はあはぬ君かな なほさりに みわのすきとは をしへおきて たつぬるときは あはぬきみかな | 藤原時昌 | 十三 | 恋三 |
| 795 | たのめこし野へのみちしは夏ふかしいつくなるらんもすの草くき たのめこし のへのみちしは なつふかし いつくなるらむ もすのくさくき | 皇太后宮大夫俊成 | 十三 | 恋三 |
| 796 | 冬の日を春よりなかくなす物はこひつつくらす心なりけり ふゆのひを はるよりなかく なすものは こひつつくらす こころなりけり | 法性寺入道前太政大臣 | 十三 | 恋三 |
| 797 | よろつ代をちきりそめつるしるしにはかつかつけふのくれそひさしき よろつよを ちきりそめつる しるしには かつかつけふの くれそひさしき | 院御製 | 十三 | 恋三 |
| 798 | けさとはぬつらさに物はおもひしれわれもさこそはうらみかねしか けさとはぬ つらさにものは おもひしれ われもさこそは うらみかねしか | 院御製 | 十三 | 恋三 |
| 799 | かねてよりおもひしことそふししはのこるはかりなるなけきせんとは かねてより おもひしことそ ふししはの こるはかりなる なけきせむとは | 待賢門院加賀 | 十三 | 恋三 |
| 800 | 恋しさはあふをかきりとききしかとさてしもいととおもひそひけり こひしさは あふをかきりと ききしかと さてしもいとと おもひそひけり | 前参議教長 | 十三 | 恋三 |
| 801 | よそにしてもときし人にいつしかと袖のしつくをとはるへきかな よそにして もときしひとに いつしかと そてのしつくを とはるへきかな | 左京大夫顕輔 | 十三 | 恋三 |
| 802 | なかからむ心もしらすくろかみのみたれてけさは物をこそおもへ なかからむ こころもしらす くろかみの みたれてけさは ものをこそおもへ | 待賢門院堀川 | 十三 | 恋三 |
| 803 | よひのまもまつに心やなくさむといまこんとたにたのめおかなん よひのまも まつにこころや なくさむと いまこむとたに たのめおかなむ | 上西門院兵衛 | 十三 | 恋三 |
| 804 | そなれ木のそなれそなれてふす苔のまほならすともあひみてしかな そなれきの そなれそなれて ふすこけの まほならすとも あひみてしかな | 待賢門院のあき | 十三 | 恋三 |
| 805 | 人はいさあかぬよとこにととめつるわか心こそわれをまつらめ ひとはいさ あかぬよとこに ととめつる わかこころこそ われをまつらめ | 前右京権大夫頼政 | 十三 | 恋三 |
| 806 | おもへたたいりやらさりしあり明の月よりさきにいてし心を おもへたた いりやらさりし ありあけの つきよりさきに いてしこころを | 権中納言通親 | 十三 | 恋三 |
| 807 | なにはえのあしのかりねの一よゆゑみをつくしてや恋ひわたるへき なにはえの あしのかりねの ひとよゆゑ みをつくしてや こひわたるへき | 皇嘉門院別当 | 十三 | 恋三 |
| 808 | こひこひてあふうれしさをつつむへき袖は涙にくちはてにけり こひこひて あふうれしさを つつむへき そてはなみたに くちはてにけり | 藤原公衡朝臣 | 十三 | 恋三 |
| 809 | 君やそれありしつらさはたれなれはうらみけるさへ今はくやしき きみやそれ ありしつらさは たれなれは うらみけるさへ いまはくやしき | 藤原隆信朝臣 | 十三 | 恋三 |
| 810 | すかたこそねさめのとこにみえすとも契りしことのうつつなりせは すかたこそ ねさめのとこに みえすとも ちきりしことの うつつなりせは | 参議俊憲 | 十三 | 恋三 |
| 811 | あつまやのあさ木のはしらわれなからいつふしなれて恋しかるらん あつまやの あさきのはしら われなから いつふしなれて こひしかるらむ | 前斎院新肥前 | 十三 | 恋三 |
| 812 | つつめともまくらは恋をしりぬらん涙かからぬ夜はしなけれは つつめとも まくらはこひを しりぬらむ なみたかからぬ よはしなけれは | 久我内大臣 | 十三 | 恋三 |
| 813 | 恋すれはもゆるほたるもなくせみもわかみの外の物とやはみる こひすれは もゆるほたるも なくせみも わかみのほかの ものとやはみる | 前中納言雅頼 | 十三 | 恋三 |
| 814 | ひきかけて涙を人につつむまにうらやくちなん夜はの衣は ひきかけて なみたをひとに つつむまに うらやくちなむ よはのころもは | 右大臣 | 十三 | 恋三 |
| 815 | しほたるるいせをのあまの袖たにもほすなるひまはありとこそきけ しほたるる いせをのあまの そてたにも ほすなるひまは ありとこそきけ | 前参議親隆 | 十三 | 恋三 |
| 816 | しはしこそぬるるたもともしほりしか涙にいまはまかせてそみる しはしこそ ぬるるたもとも しほりしか なみたにいまは まかせてそみる | 藤原清輔朝臣 | 十三 | 恋三 |
| 817 | よしさらは涙にくちねから衣ほすも人めをしのふかきりそ よしさらは なみたにくちね からころも ほすもひとめを しのふかきりそ | 顕昭法師 | 十三 | 恋三 |
| 818 | おもひわひさても命はあるものをうきにたへぬは涙なりけり おもひわひ さてもいのちは あるものを うきにたへぬは なみたなりけり | 道因法師 | 十三 | 恋三 |
| 819 | かすならぬみにも心のありかほにひとりも月をなかめつるかな かすならぬ みにもこころの ありかほに ひとりもつきを なかめつるかな | 遊女戸戸 | 十三 | 恋三 |
| 820 | 涙にやくちはてなましから衣袖のひるまとたのめさりせは なみたにや くちはてなまし からころも そてのひるまと たのめさりせは | 中原清重 | 十三 | 恋三 |
| 821 | かれはつるをささかふしをおもふにもすくなかりけるよよのかすかな かれはつる をささかふしを おもふにも すくなかりける よよのかすかな | 藤原成親 | 十三 | 恋三 |
| 822 | わけきつるをささか露のしけけれはあふ道にさへぬるる袖かな わけきつる をささかつゆの しけけれは あふみちにさへ ぬるるそてかな | 藤原伊経 | 十三 | 恋三 |
| 823 | おきてゆく涙のかかる草まくら露しけしとや人のあやめん おきてゆく なみたのかかる くさまくら つゆしけしとや ひとのあやめむ | 読人知らず | 十三 | 恋三 |
| 824 | 涙をもしのふるころのわか袖にあやなく月のやとりぬるかな なみたをも しのふるころの わかそてに あやなくつきの やとりぬるかな | 読人知らず | 十三 | 恋三 |
| 825 | しのひかねいまは我とや名のらまし思ひすつへきけしきならねは しのひかね いまはわれとや なのらまし おもひすつへき けしきならねは | 内大臣 | 十三 | 恋三 |
| 826 | しられてもいとはれぬへきみならすは名をさへ人につつむへしやは しられても いとはれぬへき みならすは なをさへひとに つつむへしやは | 左近中将良経 | 十三 | 恋三 |
| 827 | いつくよりふきくるかせのちらしけんたれもしのふのもりのことのは いつくより ふきくるかせの ちらしけむ たれもしのふの もりのことのは | 左兵衛督隆房 | 十三 | 恋三 |
| 828 | おもひかね夢にみゆやとかへさすはうらさへ袖はぬらささらまし おもひかね ゆめにみゆやと かへさすは うらさへそては ぬらささらまし | 前右京権大夫頼政 | 十三 | 恋三 |
| 829 | くり返しくやしき物は君にしもおもひよりけんしつのをたまき くりかへし くやしきものは きみにしも おもひよりけむ しつのをたまき | 源師光 | 十三 | 恋三 |
| 830 | いとはるるみをうしとてや心さへわれをはなれて君にそふらん いとはるる みをうしとてや こころさへ われをはなれて きみにそふらむ | 藤原隆親 | 十三 | 恋三 |
| 831 | あちきなくいはて心をつくすかなつつむ人めも人のためかは あちきなく いはてこころを つくすかな つつむひとめも ひとのためかは | 源光行 | 十三 | 恋三 |
| 832 | くれなゐにしをれし袖もくちはてぬあらはや人に色もみすへき くれなゐに しをれしそても くちはてぬ あらはやひとに いろもみすへき | 皇太后宮若水 | 十三 | 恋三 |
| 833 | 命こそおのかものからうかりけれあれはそ人をつらしともみる いのちこそ おのかものから うかりけれ あれはそひとを つらしともみる | 皇嘉門院尾張 | 十三 | 恋三 |
| 834 | なにとかやしのふにはあらてふるさとの軒はにしける草の名そうき なにとかや しのふにはあらて ふるさとの のきはにしける くさのなそうき | 右近中将忠良 | 十三 | 恋三 |
| 835 | みし夢のさめぬやかてのうつつにてけふとたのめしくれをまたはや みしゆめの さめぬやかての うつつにて けふとたのめし くれをまたはや | 太皇太后宮小侍従 | 十三 | 恋三 |
| 836 | しるらめやおつる涙の露ともにわかれのとこにきえてこふとは しるらめや おつるなみたの つゆともに わかれのとこに きえてこふとは | 二条院御製 | 十三 | 恋三 |
| 837 | またしらぬ露おく袖をおもひやれかことはかりのとこの涙に またしらぬ つゆおくそてを おもひやれ かことはかりの とこのなみたに | 読人知らず | 十三 | 恋三 |
| 838 | かへりつるなこりのそらをなかむれはなくさめかたき有明の月 かへりつる なこりのそらを なかむれは なくさめかたき ありあけのつき | 摂政前右大臣 | 十三 | 恋三 |
| 839 | わするなよよよの契をすかはらやふしみのさとの有明の空 わするなよ よよのちきりを すかはらや ふしみのさとの ありあけのそら | 皇太后宮大夫俊成 | 十三 | 恋三 |
| 840 | いかにしてよるの心をなくさめむひるはなかめにさてもくらしつ いかにして よるのこころを なくさめむ ひるはなかめに さてもくらしつ | 和泉式部 | 十四 | 恋四 |
| 841 | これもみなさそなむかしの契そとおもふものからあさましきかな これもみな さそなむかしの ちきりそと おもふものから あさましきかな | 和泉式部 | 十四 | 恋四 |
| 842 | よそにては中中さてもありにしをうたて物おもふ昨日けふかな よそにては なかなかさても ありにしを うたてものおもふ きのふけふかな | 花山院御製 | 十四 | 恋四 |
| 843 | おもひいててたれをか人のたつねましうきにたへたる命ならすは おもひいてて たれをかひとの たつねまし うきにたへたる いのちならすは | 小式部 | 十四 | 恋四 |
| 844 | まつとてもかはかりこそはあらましかおもひもかけぬ秋の夕くれ まつとても かはかりこそは あらましか おもひもかけぬ あきのゆふくれ | 和泉式部 | 十四 | 恋四 |
| 845 | ほとふれは人はわすれてやみぬらん契りしことをなほたのむかな ほとふれは ひとはわすれて やみぬらむ ちきりしことを なほたのむかな | 和泉式部 | 十四 | 恋四 |
| 846 | たけのはに玉ぬく露にあらねともまた夜をこめておきにけるかな たけのはに たまぬくつゆに あらねとも またよをこめて おきにけるかな | 藤原実方朝臣 | 十四 | 恋四 |
| 847 | このまよりひれふる袖をよそにみていかかはすへきまつらさよ姫 このまより ひれふるそてを よそにみて いかかはすへき まつらさよひめ | 藤原基俊 | 十四 | 恋四 |
| 848 | まふしさすしつをのみにもたへかねてはとふく秋のこゑたてつなり まふしさす しつをのみにも たへかねて はとふくあきの こゑたてつなり | 藤原仲実朝臣 | 十四 | 恋四 |
| 849 | 吹く風にたへぬこすゑの花よりもととめかたきは涙なりけり ふくかせに たへぬこすゑの はなよりも ととめかたきは なみたなりけり | 源雅光 | 十四 | 恋四 |
| 850 | あひみむといひわたりしは行すゑの物おもふことのはしにそ有りける あひみむと いひわたりしは ゆくすゑの ものおもふことの はしにそありける | 大納言成通 | 十四 | 恋四 |
| 851 | 恋ひわひてあはれとはかりうちなけくことよりほかのなくさめそなき こひわひて あはれとはかり うちなけく ことよりほかの なくさめそなき | 伊与三位(藤原敦兼朝臣母) | 十四 | 恋四 |
| 852 | たちかへる人をもなにかうらみまし恋しさをたにととめさりせは たちかへる ひとをもなにか うらみまし こひしさをたに ととめさりせは | 権中納言師時 | 十四 | 恋四 |
| 853 | うつらなくしつやにおふる玉こすけかりにのみきてかへる君かな うつらなく しつやにおふる たまこすけ かりにのみきて かへるきみかな | 藤原道経 | 十四 | 恋四 |
| 854 | わかれてはかたみなりける玉つさをなくさむはかりかきもおかせて わかれては かたみなりける たまつさを なくさむはかり かきもおかせて | 久我内大臣 | 十四 | 恋四 |
| 855 | 我かそての涙やにほの海ならんかりにも人をみるめなけれは わかそての なみたやにほの うみならむ かりにもひとを みるめなけれは | 上西門院兵衛 | 十四 | 恋四 |
| 856 | あつまやのをかやの軒のしのふ草しのひもあへすしける思ひに あつまやの をかやののきの しのふくさ しのひもあへす しけるおもひに | 前参議親隆 | 十四 | 恋四 |
| 857 | 恋をのみしかまのいちにたつ民のたえぬおもひにみをやかへてん こひをのみ しかまのいちに たつたみの たえぬおもひに みをやかへてむ | 皇太后宮大夫俊成 | 十四 | 恋四 |
| 858 | こひをのみすかたの池にみ草ゐてすまてやみなん名こそをしけれ こひをのみ すかたのいけに みくさゐて すまてやみなむ なこそをしけれ | 待賢門院安芸 | 十四 | 恋四 |
| 859 | 露ふかきあさまののらにをかやかるしつのたもともかくはぬれしを つゆふかき あさまののらに をかやかる しつのたもとも かくはぬれしを | 藤原清輔朝臣 | 十四 | 恋四 |
| 860 | あふことはいなさほそえのみをつくしふかきしるしもなきよなりけり あふことは いなさほそえの みをつくし ふかきしるしも なきよなりけり | 藤原清輔朝臣 | 十四 | 恋四 |
| 861 | 人つてはさしもやはともおもふらむみせはや君になれるすかたを ひとつては さしもやはとも おもふらむ みせはやきみに なれるすかたを | 顕昭法師 | 十四 | 恋四 |
| 862 | あさましやさのみはいかにしなのなるきそちのはしのかけわたるらん あさましや さのみはいかに しなのなる きそちのはしの かけわたるらむ | 平実重 | 十四 | 恋四 |
| 863 | 人のうへとおもははいかにもとかましつらきもしらすこふる心を ひとのうへと おもははいかに もとかまし つらきもしらす こふるこころを | 平実重 | 十四 | 恋四 |
| 864 | 契りしももろともにこそちきりしかわすれはわれもわすれましかは ちきりしも もろともにこそ ちきりしか わすれはわれも わすれましかは | 参議為通 | 十四 | 恋四 |
| 865 | 君にのみしたのおもひはかはしまの水の心はあさからなくに きみにのみ したのおもひは かはしまの みつのこころは あさからなくに | 従三位季行 | 十四 | 恋四 |
| 866 | おもひきやとしのつもるはわすられて恋にいのちのたへん物とは おもひきや としのつもるは わすられて こひにいのちの たへむものとは | 院御製 | 十四 | 恋四 |
| 867 | なけきあまりうきみそいまはなつかしき君ゆゑ物をおもふと思へは なけきあまり うきみそいまは なつかしき きみゆゑものを おもふとおもへは | 藤原季通朝臣 | 十四 | 恋四 |
| 868 | 水くきはこれをかきりとかきつめてせきあへぬ物は涙なりけり みつくきは これをかきりと かきつめて せきあへぬものは なみたなりけり | 前右京権大夫頼政 | 十四 | 恋四 |
| 869 | たれもよもまたききそめし鴬の君にのみこそおとしはしむれ たれもよも またききそめし うくひすの きみにのみこそ おとしはしむれ | 二条院御製 | 十四 | 恋四 |
| 870 | 鴬はなへてみやこになれぬらんふるすにねをはわれのみそなく うくひすは なへてみやこに なれぬらむ ふるすにねをは われのみそなく | 読人知らず | 十四 | 恋四 |
| 871 | みせはやなつゆのゆかりの玉かつら心にかけてしのふけしきを みせはやな つゆのゆかりの たまかつら こころにかけて しのふけしきを | 読人知らず | 十四 | 恋四 |
| 872 | あふさかの名をわすれにし中なれとせきやられぬは涙なりけり あふさかの なをわすれにし なかなれと せきやられぬは なみたなりけり | 読人知らず | 十四 | 恋四 |
| 873 | 月まつと人にはいひてなかむれはなくさめかたき夕くれのそら つきまつと ひとにはいひて なかむれは なくさめかたき ゆふくれのそら | 刑部卿範兼 | 十四 | 恋四 |
| 874 | あしのやのかりそめふしは津国のなからへゆけとわすれさりけり あしのやの かりそめふしは つのくにの なからへゆけと わすれさりけり | 藤原為真 | 十四 | 恋四 |
| 875 | しらさりき雲ゐのよそにみし月のかけをたもとにやとすへしとは しらさりき くもゐのよそに みしつきの かけをたもとに やとすへしとは | 西行法師 | 十四 | 恋四 |
| 876 | あふとみしその夜の夢のさめてあれななかきねふりはうかるへけれと あふとみし そのよのゆめの さめてあれな なかきねふりは うかるへけれと | 西行法師 | 十四 | 恋四 |
| 877 | 秋かせのうき人よりもつらきかな恋せよとてはふかさらめとも あきかせの うきひとよりも つらきかな こひせよとては ふかさらめとも | 空人法師 | 十四 | 恋四 |
| 878 | 心さへわれにもあらすなりにけり恋はすかたのかはるのみかは こころさへ われにもあらす なりにけり こひはすかたの かはるのみかは | 源仲綱 | 十四 | 恋四 |
| 879 | まちかねてさよもふけひのうらかせにたのめぬ浪のおとのみそする まちかねて さよもふけひの うらかせに たのめぬなみの おとのみそする | 二条院内侍参河 | 十四 | 恋四 |
| 880 | ひとよとてよかれし床のさむしろにやかてもちりのつもりぬるかな ひとよとて よかれしとこの さむしろに やかてもちりの つもりぬるかな | さぬき | 十四 | 恋四 |
| 881 | なからへてかはる心をみるよりもあふに命をかへてましかは なからへて かはるこころを みるよりも あふにいのちを かへてましかは | 摂政前右大臣 | 十四 | 恋四 |
| 882 | あふ事のありしところしかはらすは心をたにもやらましものを あふことの ありしところし かはらすは こころをたにも やらましものを | 前中納言雅頼 | 十四 | 恋四 |
| 883 | うつりかになにしみにけんさよころもわすれぬつまとなりけるものを うつりかに なにしみにけむ さよころも わすれぬつまと なりけるものを | 権中納言経房 | 十四 | 恋四 |
| 884 | わすれぬやしのふやいかにあはぬまのかたみとききしあけくれの空 わすれぬや しのふやいかに あはぬまの かたみとききし あけくれのそら | 右近中将忠良 | 十四 | 恋四 |
| 885 | おもひかねなほ恋ちにそかへりぬるうらみはすゑもとほらさりけり おもひかね なほこひちにそ かへりぬる うらみはすゑも とほらさりけり | 俊恵法師 | 十四 | 恋四 |
| 886 | みせはやなをしまのあまの袖たにもぬれにそぬれし色はかはらす みせはやな をしまのあまの そてたにも ぬれにそぬれし いろはかはらす | 殷富門院大輔 | 十四 | 恋四 |
| 887 | 山しろのみつののさとにいもをおきていくたひよとに舟よはふらん やましろの みつののさとに いもをおきて いくたひよとに ふねよはふらむ | 前右京権大夫頼政 | 十四 | 恋四 |
| 888 | 人しれすむすひそめてし若草のはなのさかりもすきやしぬらん ひとしれす むすひそめてし わかくさの はなのさかりも すきやしぬらむ | 藤原隆信朝臣 | 十四 | 恋四 |
| 889 | いかなれはなかれはたえぬ中川にあふせのかすのすくなかるらん いかなれは なかれはたえぬ なかかはに あふせのかすの すくなかるらむ | 藤原顕家朝臣 | 十四 | 恋四 |
| 890 | すみなれしさのの中川せたえしてなかれかはるは涙なりけり すみなれし さののなかかは せたえして なかれかはるは なみたなりけり | 源仲綱 | 十四 | 恋四 |
| 891 | いまさらに恋しといふもたのまれすこれも心のかはるとおもへは いまさらに こひしといふも たのまれす これもこころの かはるとおもへは | 二条院讃岐 | 十四 | 恋四 |
| 892 | こひそめし心の色のなになれはおもひかへすにかへらさるらん こひそめし こころのいろの なになれは おもひかへすに かへらさるらむ | 太皇太后宮小侍従 | 十四 | 恋四 |
| 893 | 伊勢しまやいちしのうらのあまたにもかつかぬ袖はぬるるものかは いせしまや いちしのうらの あまたにも かつかぬそては ぬるるものかは | 道因法師 | 十四 | 恋四 |
| 894 | おもひきやうかりし夜はの鳥のねをまつことにしてあかすへしとは おもひきや うかりしよはの とりのねを まつことにして あかすへしとは | 俊恵法師 | 十四 | 恋四 |
| 895 | から衣かへしてはねし夏のよはゆめにもあかて人わかれけり からころも かへしてはねし なつのよは ゆめにもあかて ひとわかれけり | 俊恵法師 | 十四 | 恋四 |
| 896 | みのうさをおもひしらてややみなましあひみぬさきのつらさなりせは みのうさを おもひしらてや やみなまし あひみぬさきの つらさなりせは | 法印静賢 | 十四 | 恋四 |
| 897 | あふことはみをかへてともまつへきをよよをへたてんほとそかなしき あふことは みをかへてとも まつへきを よよをへたてむ ほとそかなしき | 皇太后宮大夫俊成 | 十四 | 恋四 |
| 898 | おもひねの夢になくさむ恋なれはあはねとくれのそらそまたるる おもひねの ゆめになくさむ こひなれは あはねとくれの そらそまたるる | 摂政家丹後 | 十四 | 恋四 |
| 899 | 恋ひわひてうちぬるよひの夢にたにあふとは人のみえはこそあらめ こひわひて うちぬるよひの ゆめにたに あふとはひとの みえはこそあらめ | 民部卿成範 | 十四 | 恋四 |
| 900 | わひつつはなれたに君にとこなれよかはさぬ夜はの枕なりとも わひつつは なれたにきみに とこなれよ かはさぬよはの まくらなりとも | 権大納言実家 | 十四 | 恋四 |
| 901 | なけきつつかはさぬ夜はのつもるには枕もうとくならぬものかは なけきつつ かはさぬよはの つもるには まくらもうとく ならぬものかは | 読人知らず | 十四 | 恋四 |
| 902 | これはみなおもひしことそなれしよりあはれなこりをいかにせんとは これはみな おもひしことそ なれしより あはれなこりを いかにせむとは | 右近中将忠良 | 十四 | 恋四 |
| 903 | しぬとても心をわくる物ならは君にのこしてなほや恋ひまし しぬとても こころをわくる ものならは きみにのこして なほやこひまし | 権中納言通親 | 十四 | 恋四 |
| 904 | うたたねにはかなくさめし夢をたに此世に又はみてややみなん うたたねに はかなくさめし ゆめをたに このよにまたは みてややみなむ | 相模 | 十五 | 恋五 |
| 905 | ねをなけは袖はくちてもうせぬめりなほうきことそつきせさりける ねをなけは そてはくちても うせぬめり なほうきことそ つきせさりける | 和泉式部 | 十五 | 恋五 |
| 906 | ともかくもいははなへてになりぬへしねになきてこそみすへかりけれ ともかくも いははなへてに なりぬへし ねになきてこそ みすへかりけれ | 和泉式部 | 十五 | 恋五 |
| 907 | あり明の月見すひまにおきていにし人のなこりをなかめしものを ありあけの つきみすひまに おきていにし ひとのなこりを なかめしものを | 和泉式部 | 十五 | 恋五 |
| 908 | わするるはうきよのつねとおもふにもみをやるかたのなきそわひぬる わするるは うきよのつねと おもふにも みをやるかたの なきそわひぬる | 紫式部 | 十五 | 恋五 |
| 909 | ちはやふるかものやしろの神もきけ君わすれすはわれもわすれし ちはやふる かものやしろの かみもきけ きみわすれすは われもわすれし | 馬内侍 | 十五 | 恋五 |
| 910 | うたかひし命はかりはありなからちきりし中のたえぬへきかな うたかひし いのちはかりは ありなから ちきりしなかの たえぬへきかな | 大弐三位 | 十五 | 恋五 |
| 911 | かり人はとかめもやせん草しけみあやしき鳥のあとのみたれを かりひとは とかめもやせむ くさしけみ あやしきとりの あとのみたれを | 相模 | 十五 | 恋五 |
| 912 | 山よりもふかきところをたつねみはわか心にそ人はいるへき やまよりも ふかきところを たつねみは わかこころにそ ひとはいるへき | 大納言斉信 | 十五 | 恋五 |
| 913 | いにしへもこえみてしかはあふさかはふみたかふへき中の道かは いにしへも こえみてしかは あふさかは ふみたかふへき なかのみちかは | 藤原経衡 | 十五 | 恋五 |
| 914 | かりにそといはぬさきよりたのまれすたちとまるへき心ならねは かりにそと いはぬさきより たのまれす たちとまるへき こころならねは | 赤染衛門 | 十五 | 恋五 |
| 915 | 人こころなにをたのみてみなせ川せきのふるくひくちはてぬらん ひとこころ なにをたのみて みなせかは せせのふるくひ くちはてぬらむ | 藤原基俊 | 十五 | 恋五 |
| 916 | うらみすはわすれぬ人もありなましおもひしらてそあるへかりける うらみすは わすれぬひとも ありなまし おもひしらてそ あるへかりける | 隆源法師 | 十五 | 恋五 |
| 917 | まことにやみとせもまたてやましろのふしみの里ににひ枕する まことにや みとせもまたて やましろの ふしみのさとに にひまくらする | 中院右大臣 | 十五 | 恋五 |
| 918 | うき人をしのふへしとはおもひきやわか心さへなとかはるらん うきひとを しのふへしとは おもひきや わかこころさへ なとかはるらむ | 待賢門院堀河 | 十五 | 恋五 |
| 919 | うかりけるよよの契を思ふにもつらきはいまのこころのみかは うかりける よよのちきりを おもふにも つらきはいまの こころのみかは | 上西門院兵衛 | 十五 | 恋五 |
| 920 | しるなれはいかに枕のおもふらんちりのみつもるとこのけしきを しるなれは いかにまくらの おもふらむ ちりのみつもる とこのけしきを | 前参議親隆 | 十五 | 恋五 |
| 921 | はかなくもこむよをかねて契るかなふたたひおなし身ともならしを はかなくも こむよをかねて ちきるかな ふたたひおなし みともならしを | 右大臣 | 十五 | 恋五 |
| 922 | おもひいてよ夕の雲もたなひかはこれやなけきにたへぬ煙と おもひいてよ ゆふへのくもも たなひかは これやなけきに たへぬけふりと | 右近中将忠良 | 十五 | 恋五 |
| 923 | 恋ひしなはうかれん玉よしはしたにわかおもふ人のつまにととまれ こひしなは うかれむたまよ しはしたに わかおもふひとの つまにととまれ | 左兵衛督隆房 | 十五 | 恋五 |
| 924 | 君こふとうきぬる玉のさ夜ふけていかなるつまにむすはれぬらん きみこふと うきぬるたまの さよふけて いかなるつまに むすはれぬらむ | 太皇大后宮小侍従 | 十五 | 恋五 |
| 925 | きみこふる心のやみをわひつつは此世はかりとおもはましかは きみこふる こころのやみを わひつつは このよはかりと おもはましかは | 二条院讃岐 | 十五 | 恋五 |
| 926 | かはりゆくけしきをみてもいける身の命をあたにおもひけるかか かはりゆく けしきをみても いけるみの いのちをあたに おもひけるかな | 殷富門院大輔 | 十五 | 恋五 |
| 927 | 君やあらぬわか身やあらぬおほつかなたのめしことのみなかはりぬる きみやあらぬ わかみやあらぬ おほつかな たのめしことの みなかはりぬる | 俊恵法師 | 十五 | 恋五 |
| 928 | 物おもへともかからぬ人もあるものをあはれなりける身のちきりかな ものおもへとも かからぬひとも あるものを あはれなりける みのちきりかな | 西行法師 | 十五 | 恋五 |
| 929 | なけけとて月やは物をおもはするかこちかほなるわか涙かな なけけとて つきやはものを おもはする かこちかほなる わかなみたかな | 西行法師 | 十五 | 恋五 |
| 930 | 久かたの月ゆゑにやは恋ひそめしなかむれはまつぬるるそてかな ひさかたの つきゆゑにやは こひそめし なかむれはまつ ぬるるそてかな | 寂超法師 | 十五 | 恋五 |
| 931 | つらしともうらむるかたそなかりけるうきをいとふは君ひとりかは つらしとも うらむるかたそ なかりける うきをいとふは きみひとりかは | 祐盛法師 | 十五 | 恋五 |
| 932 | おもひしる心のなきをなけくかなうき身ゆゑこそ人もつらけれ おもひしる こころのなきを なけくかな うきみゆゑこそ ひともつらけれ | 藤原隆親 | 十五 | 恋五 |
| 933 | 思ふをもわするる人はさもあらはあれうきをしのはぬ心ともかな おもふをも わするるひとは さもあらはあれ うきをしのはぬ こころともかな | 源有房 | 十五 | 恋五 |
| 934 | はかなくそ後のよまてとちきりけるまたきにたにもかはる心を はかなくそ のちのよまてと ちきりける またきにたにも かはるこころを | 惟宗広言 | 十五 | 恋五 |
| 935 | いとはるるそのゆかりにていかなれは恋はわか身をはなれさるらん いとはるる そのゆかりにて いかなれは こひはわかみを はなれさるらむ | 源仲頼 | 十五 | 恋五 |
| 936 | おもひあまりうちぬるよひのまほろしも浪ちをわけてゆきかよひけり おもひあまり うちぬるよひの まほろしも なみちをわけて ゆきかよひけり | 鴨長明 | 十五 | 恋五 |
| 937 | としふれとうき身はさらにかはらしをつらさもおなしつらさなるらん としふれと うきみはさらに かはらしを つらさもおなし つらさなるらむ | 土御門前斎院中将 | 十五 | 恋五 |
| 938 | なけくまにかかみの影もおとろへぬ契りしことのかはるのみかは なけくまに かかみのかけも おとろへぬ ちきりしことの かはるのみかは | 崇徳院御製 | 十五 | 恋五 |
| 939 | としふれとあはれにたへぬ涙かな恋しき人のかからましかは としふれと あはれにたへぬ なみたかな こひしきひとの かからましかは | 左京大夫顕輔 | 十五 | 恋五 |
| 940 | いまはたたおさふる袖もくちはてて心のままにおつるなみたか いまはたた おさふるそても くちはてて こころのままに おつるなみたか | 藤原季通朝臣 | 十五 | 恋五 |
| 941 | おく山のいはかきぬまのうきぬなはふかき恋ちになにみたれけん おくやまの いはかきぬまの うきぬなは ふかきこひちに なにみたれけむ | 皇太后宮大夫俊成 | 十五 | 恋五 |
| 942 | しきしのふとこたにたへぬ涙にも恋はくちせぬ物にそ有りける しきしのふ とこたにたへぬ なみたにも こひはくちせぬ ものにそありける | 皇太后宮大夫俊成 | 十五 | 恋五 |
| 943 | あさゆふにみるめをかつくあまたにもうらみはたえぬ物とこそきけ あさゆふに みるめをかつく あまたにも うらみはたえぬ ものとこそきけ | 藤原清輔朝臣 | 十五 | 恋五 |
| 944 | なにせんにそらたのめとてうらみけんおもひたえたる暮もありけり なにせむに そらたのめとて うらみけむ おもひたえたる くれもありけり | 上西門院兵衛 | 十五 | 恋五 |
| 945 | なほさりのそらたのめとてまちし夜のくるしかりしそいまは恋しき なほさりの そらたのめとて まちしよの くるしかりしそ いまはこひしき | 殷富門院大輔 | 十五 | 恋五 |
| 946 | をしみかねけにいひしらぬ別かな月もいまはのあり明のそら をしみかね けにしひしらぬ わかれかな つきもいまはの ありあけのそら | 摂政前右大臣 | 十五 | 恋五 |
| 947 | 恋ひわふる心はそらにうきぬれと涙のそこに身はしつむかな こひわふる こころはそらに うきぬれと なみたのそこに みはしつむかな | 右近大将実房 | 十五 | 恋五 |
| 948 | おもひかねこゆるせきちに夜をふかみやこゑの鳥にねをそそへつる おもひかね こゆるせきちに よをふかみ やこゑのとりに ねをそそへつる | 前中納言雅頼 | 十五 | 恋五 |
| 949 | 世にしらぬ秋の別にうちそへて人やりならす物そかなしき よにしらぬ あきのわかれに うちそへて ひとやりならす ものそかなしき | 権中納言通親 | 十五 | 恋五 |
| 950 | 契りしにあらすなるとのはまちとりあとたにみせぬうらみをそする ちきりしに あらすなるとの はまちとり あとたにみせぬ うらみをそする | 藤原経家朝臣 | 十五 | 恋五 |
| 951 | しかはかり契りし中もかはりけるこのよに人をたのみけるかな しかはかり ちきりしなかも かはりける このよにひとを たのみけるかな | 藤原定家 | 十五 | 恋五 |
| 952 | 秋の夜を物おもふことのかきりとはひとりねさめの枕にそしる あきのよを ものおもふことの かきりとは ひとりねさめの まくらにそしる | 顕昭法師 | 十五 | 恋五 |
| 953 | よしさらは君に心はつくしてん又も恋しき人もこそあれ よしさらは きみにこころは つくしてむ またもこひしき ひともこそあれ | 前参議教長 | 十五 | 恋五 |
| 954 | なき人をおもひ出てたる夕くれはうらみしことそくやしかりける なきひとを おもひいてたる ゆふくれは うらみしことそ くやしかりける | 仁和寺後入道法親王(覚性) | 十五 | 恋五 |
| 955 | これをみよむつ田のよとにさてさしてしをれししつのあさ衣かは これをみよ むつたのよとに さてさして しをれししつの あさころもかは | 源俊頼朝臣 | 十五 | 恋五 |
| 956 | ささめかるあれ田のさはにたつたみも身のためにこそ袖はぬるらめ ささめかる あれたのさはに たつたみも みのためにこそ そてもぬるらめ | 源俊頼朝臣 | 十五 | 恋五 |
| 957 | ささのはにあられふる夜のさむけきにひとりはねなん物とやはおもふ ささのはに あられふるよの さむけきに ひとりはねなむ ものとやはおもふ | 馬内侍 | 十五 | 恋五 |
| 958 | うらむへき心はかりはあるものをなきになしてもとはぬ君かな うらむへき こころはかりは あるものを なきになしても とはぬきみかな | 和泉式部 | 十五 | 恋五 |
| 959 | かそへしる人なかりせはおく山のたにの松とやとしをつままし かそへしる ひとなかりせは おくやまの たにのまつとや としをつままし | 法成寺入道前太政大臣 | 十六 | 雑上 |
| 960 | ふえ竹のよふかきこゑそきこゆなるきしの松かせふきやそふらん ふえたけの よふかきこゑそ きこゆなる みねのまつかせ ふきやそふらむ | 大納言斉信 | 十六 | 雑上 |
| 961 | うはこほりあはにむすへるひもなれはかさす日かけにゆるふはかりを うはこほり あはにむすへる ひもなれは かさすひかけに ゆるむはかりそ | 皇后宮清少納言 | 十六 | 雑上 |
| 962 | たかさとの春のたよりにうくひすの霞にとつるやとをとふらん たかさとの はるのたよりに うくひすの かすみにとつる やとをとふらむ | 紫式部 | 十六 | 雑上 |
| 963 | いもとねておきゆくあさの道よりも中中もののおもはしきかな いもとねて おきゆくあさの みちよりも なかなかものの おもはしきかな | 藤原道信朝臣 | 十六 | 雑上 |
| 964 | 春のよの夕はかりなるたまくらにかひなくたたん名こそをしけれ はるのよの ゆめはかりなる たまくらに かひなくたたむ なこそをしけれ | 周防内侍 | 十六 | 雑上 |
| 965 | 契ありてはるの夜ふかきたまくらをいかかかひなき夢になすへき ちきりありて はるのよふかき たまくらを いかかかひなき ゆめになすへき | 大納言忠家 | 十六 | 雑上 |
| 966 | いかにしてすきにしかたをすくしけんくらしわつらふ昨日けふかな いかにして すきにしかたを すくしけむ くらしわつらふ きのふけふかな | 皇后宮定子 | 十六 | 雑上 |
| 967 | 雲のうへもくらしかねける春の日をところからともなかめつるかな くものうへも くらしかねける はるのひを ところからとも なかめつるかな | 清少納言 | 十六 | 雑上 |
| 968 | あひみむとおもひしことをたかふれはつらきかたにもさためつるかな あひみむと おもひしことを たかふれは つらきかたにも さためつるかな | 選子内親王 | 十六 | 雑上 |
| 969 | みそきせしかもの川なみたちかへりはやくみしせに袖はぬれきや みそきせし かものかはなみ たちかへり はやくみしせに そてはぬれきや | 大斎院中将 | 十六 | 雑上 |
| 970 | ちはやふるいつきの宮のたひねにはあふひそ草の枕なりけり ちはやふる いつきのみやの たひねには あふひそくさの まくらなりけり | 藤原実方朝臣 | 十六 | 雑上 |
| 971 | かをるかによそふるよりはほとときすきかはやおなしこゑやしたると かをるかに よそふるよりは ほとときす きかはやおなし こゑやしたると | 和泉式部 | 十六 | 雑上 |
| 972 | 昨日まてみたらし河にせしみそきしかのうら浪たちそかはれる きのふまて みたらしかはに せしみそき しかのうらなみ たちそかはれる | 八条前太政大臣 | 十六 | 雑上 |
| 973 | みたらしやかけたえはつる心ちしてしかの浪ちに袖そぬれこし みたらしや かけたえはつる ここちして しかのなみちに そてそぬれこし | 式子内親王 | 十六 | 雑上 |
| 974 | やとせまて手ならしたりしあつさ弓かへるをみるにねそなかれける やとせまて てならしたりし あつさゆみ かへるをみるに ねそなかれける | 大宮前太政大臣 | 十六 | 雑上 |
| 975 | なにかそれおもひすつへきあつさ弓又ひきかへす時もありなん なにかそれ おもひすつへき あつさゆみ またひきかへす ときもありなむ | 中院右大臣 | 十六 | 雑上 |
| 976 | きのふみししのふもちすりたれならん心のほとそかきりしられぬ きのふみし しのふもちすり たれならむ こころのほとそ かきりしられぬ | 左京大夫顕輔 | 十六 | 雑上 |
| 977 | 露しけきよもきかなかの虫のねをおほろけにてや人のたつねん つゆしけき よもきかなかの むしのねを おほろけにてや ひとのたつねむ | 紫式部 | 十六 | 雑上 |
| 978 | 人しれぬおほうち山のやまもりはこかくれてのみ月をみるかな ひとしれぬ おほうちやまの やまもりは こかくれてのみ つきをみるかな | 前右京権大夫頼政 | 十六 | 雑上 |
| 979 | 秋をへて光をませとおもひしにおもはぬ月のかけにもあるかな あきをへて ひかりをませと おもひしに おもはぬつきの かけにもあるかな | 権中納言実綱 | 十六 | 雑上 |
| 980 | とふ人におもひよそへてみる月のくもるはかへる心ちこそすれ とふひとに おもひよそへて みるつきの くもるはかへる ここちこそすれ | 仁和寺後入道法親王(覚性) | 十六 | 雑上 |
| 981 | ささ浪やくにつみかみのうらさひてふるき都に月ひとりすむ ささなみや くにつみかみの うらさひて ふるきみやこに つきひとりすむ | 法性寺入道前太政大臣 | 十六 | 雑上 |
| 982 | あまの川空ゆく月はひとつにてやとらぬ水のいかてなからん あまのかは そらゆくつきは ひとつにて やとらぬみつの いかてなからむ | 法性寺入道前太政大臣 | 十六 | 雑上 |
| 983 | ひとりゐて月をなかむる秋のよはなにことをかはおもひのこさん ひとりゐて つきをなかむる あきのよは なにことをかは おもひのこさむ | 中務卿具平親王 | 十六 | 雑上 |
| 984 | 物おもはぬ人もやこよひなかむらんねられぬままに月をみるかな ものおもはぬ ひともやこよひ なかむらむ ねられぬままに つきをみるかな | 赤染衛門 | 十六 | 雑上 |
| 985 | なかめつつむかしも月はみしものをかくやは袖のひまなかるへき なかめつつ むかしもつきは みしものを かくやはそての ひまなかるへき | 相模 | 十六 | 雑上 |
| 986 | ひとりのみあはれなるかと我ならぬ人にこよひの月をみせはや ひとりのみ あはれなるかと われならぬ ひとにこよひの つきをみせはや | 和泉式部 | 十六 | 雑上 |
| 987 | かくはかりうき世の中のおもひ出てにみよともすめる夜はの月かな かくはかり うきよのなかの おもひいてに みよともすめる よはのつきかな | 久我内大臣 | 十六 | 雑上 |
| 988 | すみわひて身をかくすへき山さとにあまりくまなき夜はの月かな すみわひて みをかくすへき やまさとに あまりくまなき よはのつきかな | 皇太后宮大夫俊成 | 十六 | 雑上 |
| 989 | はりまかたすまの月夜めそらさえてゑしまかさきに雪ふりにけり はりまかた すまのつきよめ そらさえて ゑしまかさきに ゆきふりにけり | 前参議親隆 | 十六 | 雑上 |
| 990 | さよちとりふけひのうらにおとつれてゑしまかいそに月かたふきぬ さよちとり ふけひのうらに おとつれて ゑしまかいそに つきかたふきぬ | 藤原家基 | 十六 | 雑上 |
| 991 | いかたおろすきよたき川にすむ月はさをにさはらぬ氷なりけり いかたおろす きよたきかはに すむつきは さをにさはらぬ こほりなりけり | 俊恵法師 | 十六 | 雑上 |
| 992 | あまのはらすめるけしきはのとかにてはやくも月の西へゆくかな あまのはら すめるけしきは のとかにて はやくもつきの にしへゆくかな | 賀茂成保 | 十六 | 雑上 |
| 993 | さひしさにあはれもいととまさりけりひとりそ月はみるへかりける さひしさに あはれもいとと まさりけり ひとりそつきは みるへかりける | 顕昭法師 | 十六 | 雑上 |
| 994 | いまよりはふけ行くまてに月はみしそのこととなく涙おちけり いまよりは ふけゆくまてに つきはみし そのこととなく なみたおちけり | 藤原清輔朝臣 | 十六 | 雑上 |
| 995 | もろともにみし人いかになりにけん月はむかしにかはらさりけり もろともに みしひといかに なりにけむ つきはむかしに かはらさりけり | 登蓮法師 | 十六 | 雑上 |
| 996 | あかなくに又もこのよにめくりこはおもかはりすな山のはの月 あかなくに またもこのよに めくりこは おもかはりすな やまのはのつき | 法印静賢 | 十六 | 雑上 |
| 997 | はかなくもわかよのふけをしらすしていさよふ月をまちわたるかな はかなくも わかよのふけを しらすして いさよふつきを まちわたるかな | 源仲正 | 十六 | 雑上 |
| 998 | さきたちし人はやみにやまよふらんいつまて我も月をなかめん さきたちし ひとはやみにや まよふらむ いつまてわれも つきをなかめむ | 源仲綱 | 十六 | 雑上 |
| 999 | のこりなくわかよふけぬとおもふにもかたふく月にすむ心かな のこりなく わかよふけぬと おもふにも かたふくつきに すむこころかな | 待賢門院堀河 | 十六 | 雑上 |
| 1000 | うき雲のかかるほとたにあるものをかくれなはてそあり明の月 うきくもの かかるほとたに あるものを かくれなはてそ ありあけのつき | 近衛院御製 | 十六 | 雑上 |
| 1001 | このまもるあり明の月のおくらすはひとりや山のみねを出てまし このまもる ありあけのつきの おくらすは ひとりややまの みねをいてまし | 仁和寺後入道法親王(覚性) | 十六 | 雑上 |
| 1002 | ことのねを雪にしらふときこゆなり月さゆる夜のみねの松かせ ことのねを ゆきにしらふと きこゆなり つきさゆるよの みねのまつかせ | 道性法親王 | 十六 | 雑上 |
| 1003 | あかていらんなこりをいととおもへとやかたふくままにすめる月かな あかていらむ なこりをいとと おもへとや かたふくままに すめるつきかな | 権中納言長方 | 十六 | 雑上 |
| 1004 | いかにせんさらてうきよはなくさますたのみし月も涙おちけり いかにせむ さらてうきよは なくさます たのみしつきも なみたおちけり | 藤原定家 | 十六 | 雑上 |
| 1005 | 山ふかき松のあらしを身にしめてたれかねさめに月をみるらん やまふかき まつのあらしを みにしめて たれかねさめに つきをみるらむ | 藤原家隆 | 十六 | 雑上 |
| 1006 | まつほとはいとと心そなくさまぬをはすて山のあり明の月 まつほとは いととこころそ なくさまぬ をはすてやまの ありあけのつき | 八条院六条 | 十六 | 雑上 |
| 1007 | よをいとふ心は月をしたへはや山のはにのみおもひいるらん よをいとふ こころはつきを したへはや やまのはにのみ おもひいるらむ | 法印実修 | 十六 | 雑上 |
| 1008 | さひしさも月みるほとはなくさみぬいりなんのちをとふ人もかな さひしさも つきみるほとは なくさみぬ いりなむのちを とふひともかな | 藤原隆親 | 十六 | 雑上 |
| 1009 | 霜さゆるにはのこのはをふみわけて月はみるやととふ人もかな しもさゆる にはのこのはを ふみわけて つきはみるやと とふひともかな | 西行法師 | 十六 | 雑上 |
| 1010 | すみなれしやとをはいてて西へゆく月をしたひて山にこそいれ すみなれし やとをはいてて にしへゆく つきをしたひて やまにこそいれ | 平実重 | 十六 | 雑上 |
| 1011 | ふるさとのいたゐのし水みくさゐて月さへすます成りにけるかな ふるさとの いたゐのしみつ みくさゐて つきさへすます なりにけるかな | 俊恵法師 | 十六 | 雑上 |
| 1012 | さもこそはかけととむへき世ならねとあとなき水にやとる月かな さもこそは かけととむへき よならねと あとなきみつに やとるつきかな | 藤原家基 | 十六 | 雑上 |
| 1013 | なにとなくなかむるそてのかわかぬは月のかつらの露やおくらん なにとなく なかむるそての かわかぬは つきのかつらの つゆやおくらむ | 藤原親盛 | 十六 | 雑上 |
| 1014 | ましはふくやとのあられに夢さめてあり明かたの月をみるかな ましはふく やとのあられに ゆめさめて ありあけかたの つきをみるかな | 大江公景 | 十六 | 雑上 |
| 1015 | あし曳の山のはちかくすむとてもまたてやはみるあり明の月 あしひきの やまのはちかく すむとても またてやはみる ありあけのつき | 静蓮法師 | 十六 | 雑上 |
| 1016 | もろともに秋をやしのふ霜かれのをきのうははをてらす月かけ もろともに あきをやしのふ しもかれの をきのうははを てらすつきかけ | 紀康宗 | 十六 | 雑上 |
| 1017 | ますけおふる山した水にやとる夜は月さへ草のいほりをそさす ますけおふる やましたみつに やとるよは つきさへくさの いほりをそさす | 法眼長真 | 十六 | 雑上 |
| 1018 | ふかきよの露ふきむすふこからしにそらさえのほる山のはの月 ふかきよの つゆふきむすふ こからしに そらさえのほる やまのはのつき | 藤原為忠朝臣 | 十六 | 雑上 |
| 1019 | 山かせにまやのあしふきあれにけり枕にやとる夜はの月影 やまかせに まやのあしふき あれにけり まくらにやとる よはのつきかけ | 覚延法師 | 十六 | 雑上 |
| 1020 | やまふかみたれ又かかるすまひしてま木のはわくる月をみるらん やまふかみ たれまたかかる すまひして まきのはわくる つきをみるらむ | 法印慈円 | 十六 | 雑上 |
| 1021 | 月影のいりぬるあとにおもふかなまよはむやみのゆくすゑの空 つきかけの いりぬるあとに おもふかな まよはむやみの ゆくすゑのそら | 法印慈円 | 十六 | 雑上 |
| 1022 | 此世にて六そちはなれぬ秋の月しての山ちもおもかはりすな このよにて むそちはなれぬ あきのつき してのやまちも おもかはりすな | 俊恵法師 | 十六 | 雑上 |
| 1023 | こむよには心のうちにあらはさんあかてやみぬる月のひかりを こむよには こころのうちに あらはさむ あかてやみぬる つきのひかりを | 西行法師 | 十六 | 雑上 |
| 1024 | いかなれはしつみなからにとしをへてよよの雲ゐの月をみつらん いかなれは しつみなからに としをへて よよのくもゐの つきをみつらむ | 皇太后宮大夫俊成 | 十六 | 雑上 |
| 1025 | からくににしつみし人もわかことくみよまてあはぬなけきをそせし からくにに しつみしひとも わかことく みよまてあはぬ なけきをそせし | 藤原基優 | 十六 | 雑上 |
| 1026 | 契りおきしさせもか露をいのちにてあはれことしの秋もいぬめり ちきりおきし させもかつゆを いのちにて あはれことしの あきもいぬめり | 藤原基優 | 十六 | 雑上 |
| 1027 | よのなかのありしにもあらすなりゆけは涙さへこそ色かはりけれ よのなかの ありしにもあらす なりゆけは なみたさへこそ いろかはりけれ | 源俊頼朝臣 | 十六 | 雑上 |
| 1028 | すききにし四そちの春のゆめのよはうきよりほかのおもひいてそなき すききにし よそちのはるの ゆめのよは うきよりほかの おもひいてそなき | 覚審法師 | 十六 | 雑上 |
| 1029 | はかなしなうき身なからもすきぬへき此世をさヘもしのひかぬらん はかなしな うきみなからも すきぬへき このよをさへも しのひかぬらむ | 経因法師 | 十六 | 雑上 |
| 1030 | ゆくすゑをおもへはかなしつの国のなからのはしも名はのこりけり ゆくすゑを おもへはかなし つのくにの なからのはしも なはのこりけり | 源俊頼朝臣 | 十六 | 雑上 |
| 1031 | なにこともかはりゆくめる世の中にむかしなからのはしはしらかな なにことも かはりゆくめる よのなかに むかしなからの はしはしらかな | 道命法師 | 十六 | 雑上 |
| 1032 | けふみれはなからのはしはあともなしむかしありきとききわたれとも けふみれは なからのはしは あともなし むかしありきと ききわたれとも | 道因法師 | 十六 | 雑上 |
| 1033 | 人こころあらすなれともすみよしの松のけしきはかはらさりけり ひとこころ あらすなれとも すみよしの まつのけしきは かはらさりけり | 津守景基 | 十六 | 雑上 |
| 1034 | しら雲にまかひやせましよしの山おちくるたきのおとせさりせは しらくもに まかひやせまし よしのやま おちくるたきの おとせさりせは | 中納言経忠 | 十六 | 雑上 |
| 1035 | たきのおとはたえてひさしく成りぬれとなこそなかれて猶きこえけれ たきのおとは たえてひさしく なりぬれと なこそなかれて なほきこえけれ | 前大納言公任 | 十六 | 雑上 |
| 1036 | ぬけはちるぬかねはみたるあし引の山よりおつるたきのしら玉 ぬけはちる ぬかねはみたる あしひきの やまよりおつる たきのしらたま | 藤原長能 | 十六 | 雑上 |
| 1037 | 水の色のたたしら雲とみゆるかなたれさらしけんぬのひきのたき みつのいろの たたしらくもと みゆるかな たれさらしけむ ぬのひきのたき | 六条右大臣 | 十六 | 雑上 |
| 1038 | あしたつにのりてかよへるやとなれはあとたに人はみえぬなりけり あしたつに のりてかよへる やとなれは あとたにひとは みえぬなりけり | 能因法師 | 十六 | 雑上 |
| 1039 | 山人のむかしのあとをきてみれはむなしきゆかをはらふ谷かせ やまひとの むかしのあとを きてみれは むなしきゆかを はらふたにかせ | 藤原清輔朝臣 | 十六 | 雑上 |
| 1040 | おとにのみききしはことのかすならて名よりもたかきぬのひきの滝 おとにのみ ききしはことの かすならて なよりもたかき ぬのひきのたき | 藤原良清 | 十六 | 雑上 |
| 1041 | たえすたつむろのやしまの煙かないかにつきせぬおもひなるらん たえすたつ むろのやしまの けふりかな いかにつきせぬ おもひなるらむ | 藤原顕方 | 十六 | 雑上 |
| 1042 | かつらきやわたしもはてぬものゆゑにくめのいははしこけおひにけり かつらきや わたしもはてぬ ものゆゑに くめのいははし こけおひにけり | 大納言師頼 | 十六 | 雑上 |
| 1043 | いはおろすかたこそなけれいせの海のしほせにかかるあまのつり舟 いはおろす かたこそなけれ いせのうみの しほせにかかる あまのつりふね | 権中納言俊忠 | 十六 | 雑上 |
| 1044 | 玉もかるいらこかさきのいはねまついく代まてにかとしのへぬらん たまもかる いらこかさきの いはねまつ いくよまてにか としのへぬらむ | 修埋大夫顕季 | 十六 | 雑上 |
| 1045 | しほみては野しまかさきのさゆりはに浪こすかせのふかぬ日そなき しほみては のしまかさきの さゆりはに なみこすかせの ふかぬひそなき | 源俊頼朝臣 | 十六 | 雑上 |
| 1046 | けふこそはみやこのかたの山のはもみえすなるをのおきに出てぬれ けふこそは みやこのかたの やまのはも みえすなるをの おきにいてぬれ | 権大納言実家 | 十六 | 雑上 |
| 1047 | はりまかたすまのはれまにみわたせは浪は雲ゐのものにそありける はりまかた すまのはれまに みわたせは なみはくもゐの ものにそありける | 権中納言実宗 | 十六 | 雑上 |
| 1048 | はるはるとおまへのおきをみわたせはくもゐにまかふあまのつり舟 はるはると おまへのおきを みわたせは くもゐにまかふ あまのつりふね | 右衛門督頼実 | 十六 | 雑上 |
| 1049 | なにはかたしほちはるかにみわたせは霞にうかふおきのつり舟 なにはかた しほちはるかに みわたせは かすみにうかふ おきのつりふね | 円玄法師 | 十六 | 雑上 |
| 1050 | 春かすみゑしまかさきをこめつれは浪のかくともみえぬけさかな はるかすみ ゑしまかさきを こめつれは なみのかくとも みえぬけさかな | 藤原重綱 | 十六 | 雑上 |
| 1051 | ゆくとしは浪とともにやかへるらんおもかはりせぬわかの浦かな ゆくとしは なみとともにや かへるらむ おもかはりせぬ わかのうらかな | 祝部宿禰成仲 | 十六 | 雑上 |
| 1052 | 心あらはにほひをそへよさくら花のちの春をはいつかみるへき こころあらは にほひをそへよ さくらはな のちのはるをは いつかみるへき | 鳥羽院御製 | 十七 | 雑中 |
| 1053 | はかなさをうらみもはてしさくら花うき世はたれも心ならねは はかなさを うらみもはてし さくらはな うきよはたれも こころならねは | 仁和寺後入道法親王(覚性) | 十七 | 雑中 |
| 1054 | やともやとはなもむかしににほへともぬしなき色はさひしかりけり やともやと はなもむかしに にほへとも ぬしなきいろは さひしかりけり | 僧正尋範 | 十七 | 雑中 |
| 1055 | いにしへにかはらさりけり山さくら花は我をはいかかみるらん いにしへに かはらさりけり やまさくら はなはわれをは いかかみるらむ | 前中納言基長 | 十七 | 雑中 |
| 1056 | 雲のうへの春こそさらにわすられね花はかすにもおもひ出てしを くものうへの はるこそさらに わすられね はなはかすにも おもひいてしを | 皇太后宮大夫俊成 | 十七 | 雑中 |
| 1057 | あまたたひゆきあふさかのせき水に今はかきりのかけそかなしき あまたたひ ゆきあふさかの せきみつに いまはかきりの かけそかなしき | 東三条院 | 十七 | 雑中 |
| 1058 | いまはとていりなん後そおもほゆる山ちをふかみとふ人もなし いまはとて いりなむのちそ おもほゆる やまちをふかみ とふひともなし | 前大納言公任 | 十七 | 雑中 |
| 1059 | うき世をはみねのかすみやへたつらんなほ山さとはすみよかりけり うきよをは みねのかすみや へたつらむ なほやまさとは すみよかりけり | 前大納言公任 | 十七 | 雑中 |
| 1060 | 花さかぬたにのそこにもすまなくにふかくも物をおもふ春かな はなさかぬ たにのそこにも すまなくに ふかくもものを おもふはるかな | 和泉式部 | 十七 | 雑中 |
| 1061 | たにのとをとちやはてつる鴬のまつにおとせて春のくれぬる たにのとを とちやはてつる うくひすの まつにおとせて はるのくれぬる | 法成寺入道前太政大臣 | 十七 | 雑中 |
| 1062 | かくてたになほあはれなるおく山に君こぬよよをおもひしらなん かくてたに なほあはれなる おくやまに きみこぬよよを おもひしらなむ | 道命法師 | 十七 | 雑中 |
| 1063 | としことに涙の川にうかへともみはなけられぬ物にそありける としことに なみたのかはに うかへとも みはなけられぬ ものにそありける | 大江公資 | 十七 | 雑中 |
| 1064 | おもふことなくてや春をすくさましうき世へたつるかすみなりせは おもふこと なくてやはるを すくさまし うきよへたつる かすみなりせは | 源仲正 | 十七 | 雑中 |
| 1065 | ちるをみてかへる心やさくら花むかしにかはるしるしなるらん ちるをみて かへるこころや さくらはな むかしにかはる しるしなるらむ | 西行法師 | 十七 | 雑中 |
| 1066 | はなにそむ心のいかてのこりけんすてはててきとおもふわか身に はなにそむ こころのいかて のこりけむ すてはててきと おもふわかみに | 西行法師 | 十七 | 雑中 |
| 1067 | ほとけにはさくらの花をたてまつれわかのちのよを人とふらはは ほとけには さくらのはなを たてまつれ わかのちのよを ひととふらはは | 西行法師 | 十七 | 雑中 |
| 1068 | この春そおもひはかへすさくら花むなしき色にそめしこころを このはるそ おもひはかへす さくらはな むなしきいろに そめしこころを | 寂然法師 | 十七 | 雑中 |
| 1069 | よのなかをつねなき物とおもはすはいかてか花のちるにたへまし よのなかを つねなきものと おもはすは いかてかはなの ちるにたへまし | 寂然法師 | 十七 | 雑中 |
| 1070 | かくはかりうき世のすゑにいかにしてはるはさくらのなほにほふらん かくはかり うきよのすゑに いかにして はるはさくらの なほにほふらむ | 読人不知 | 十七 | 雑中 |
| 1071 | ふりにけりむかしをしらはさくら花ちりのすゑをもあはれとはみよ ふりにけり むかしをしらは さくらはな ちりのすゑをも あはれとはみよ | 皇太后宮大夫俊成 | 十七 | 雑中 |
| 1072 | 山さくら花をあるしとおもはすは人をまつへきしはのいほかは やまさくら はなをあるしと おもはすは ひとをまつへき しはのいほかは | 源定宗朝臣 | 十七 | 雑中 |
| 1073 | いつくにてかせをも世をもうらみましよしののおくも花はちるなり いつくにて かせをもよをも うらみまし よしののおくも はなはちるなり | 藤原定家 | 十七 | 雑中 |
| 1074 | ふかくおもふことしかなははこむ世にも花みる身とやならんとすらん ふかくおもふ ことしかなはは こむよにも はなみるみとや ならむとすらむ | 源季広 | 十七 | 雑中 |
| 1075 | 老かよにやとにさくらをうつしうゑてなほこころみに花をまつかな おいかよに やとにさくらを うつしうゑて なほこころみに はなをまつかな | 源師教朝臣 | 十七 | 雑中 |
| 1076 | くらゐ山はなをまつこそひさしけれはるの宮こにとしはへしかと くらゐやま はなをまつこそ ひさしけれ はるのみやこに としはへしかと | 権中納言実守 | 十七 | 雑中 |
| 1077 | かすか山まつにたのみをかくるかなふちのすゑはのかすならねとも かすかやま まつにたのみを かくるかな ふちのすゑはの かすならねとも | 右兵衛督公行 | 十七 | 雑中 |
| 1078 | 物おもふ心や身にもさきたちてうき世をいてんしるへなるへき ものおもふ こころやみにも さきたちて うきよをいてむ しるへなるへき | 前左衛門督公光 | 十七 | 雑中 |
| 1079 | かすならてとしへぬる身はいまさらに世をうしとたにおもはさりけり かすならて としへぬるみは いまさらに よをうしとたに おもはさりけり | 俊恵法師 | 十七 | 雑中 |
| 1080 | いつとても身のうきことはかはらねとむかしはおいをなけきやはせし いつとても みのうきことは かはらねと むかしはおいを なけきやはせし | 道因法師 | 十七 | 雑中 |
| 1081 | いにしへもそこにしつみし身なれともなほ恋しきはしら川のみつ いにしへも そこにしつみし みなれとも なほこひしきは しらかはのみつ | 藤原家基(法名素覚) | 十七 | 雑中 |
| 1082 | あはれてふ人もなき身をうしとてもわれさへいかかいとひはつへき あはれてふ ひともなきみを うしとても われさへいかか いとひはつへき | 藤原盛方朝臣 | 十七 | 雑中 |
| 1083 | かすならぬ身をうき雲のはれぬかなさすかに家のかせはふけとも かすならぬ みをうきくもの はれぬかな さすかにいへの かせはふけとも | 中原師尚 | 十七 | 雑中 |
| 1084 | おもひやれとよにあまれるともし火のかかけかねたる心ほそさを おもひやれ とよにあまれる ともしひの かかけかねたる こころほそさを | 大江匡範 | 十七 | 雑中 |
| 1085 | よのうさをおもひしのふと人もみよかくてふるやの軒のけしきを よのうさを おもひしのふと ひともみよ かくてふるやの のきのけしきを | 藤原公重朝臣 | 十七 | 雑中 |
| 1086 | ひく人もなくてすてたるあつさ弓心つよきもかひなかりけり ひくひとも なくてすてたる あつさゆみ こころつよきも かひなかりけり | 菅原是忠 | 十七 | 雑中 |
| 1087 | いかてわれひまゆくこまを引きとめてむかしにかへる道をたつねん いかてわれ ひまゆくこまを ひきとめて むかしにかへる みちをたつねむ | 二条院参川内侍 | 十七 | 雑中 |
| 1088 | 今はたたいけらぬ物にみをなしてうまれぬのちの世にもふるかな いまはたた いけらぬものに みをなして うまれぬのちの よにもふるかな | 源師光 | 十七 | 雑中 |
| 1089 | いかにせむいせのはまをきみかくれておもはぬいその浪にくちなは いかにせむ いせのはまをき みかくれて おもはぬいその なみにくちなは | 源俊重 | 十七 | 雑中 |
| 1090 | ま木のとをみ山おろしにたたかれてとふにつけてもぬるる袖かな まきのとを みやまおろしに たたかれて とふにつけても ぬるるそてかな | 源俊頼朝臣 | 十七 | 雑中 |
| 1091 | をやま国のいほにたくひのありなしにたつ煙もや雲となるらん をやまたの いほにたくひの ありなしに たつけふりもや くもとなるらむ | 橘盛長 | 十七 | 雑中 |
| 1092 | 山さとのしはをりをりにたつ煙人まれなりとそらにしるかな やまさとの しはをりをりに たつけふり ひとまれなりと そらにしるかな | 二条太皇大后宮肥後 | 十七 | 雑中 |
| 1093 | 秋はつるかれののむしのこゑたえはありやなしやを人のとへかし あきはつる かれののむしの こゑたえは ありやなしやを ひとのとへかし | 藤原基俊 | 十七 | 雑中 |
| 1094 | この世にはすむへきほとやつきぬらんよのつねならす物のかなしき このよには すむへきほとや つきぬらむ よのつねならす もののかなしき | 藤原道信朝臣 | 十七 | 雑中 |
| 1095 | いのちあらはいかさまにせんよをしらぬむしたに秋はなきにこそなけ いのちあらは いかさまにせむ よをしらぬ むしたにあきは なきにこそなけ | 和泉式部 | 十七 | 雑中 |
| 1096 | かすならて心に身をはまかせねと身にしたかふは心なりけり かすならて こころにみをは まかせねと みにしたかふは こころなりけり | 紫式部 | 十七 | 雑中 |
| 1097 | あはれともたれかはわれをおもひいてむある世にたにもとふ人もなし あはれとも たれかはわれを おもひいてむ あるよにたにも とふひともなし | 藤原兼房朝臣 | 十七 | 雑中 |
| 1098 | ふるさとのいたまのかせにねさめしてたにのあらしをおもひこそやれ ふるさとの いたまのかせに ねさめして たにのあらしを おもひこそやれ | 中納言定頼 | 十七 | 雑中 |
| 1099 | たにかせの身にしむことに古郷のこのもとをこそおもひやりつれ たにかせの みにしむことに ふるさとの このもとをこそ おもひやりつれ | 前大納言公任 | 十七 | 雑中 |
| 1100 | いにしへはおもひかけきやとりかはしかくきん物とのりの衣を いにしへは おもひかけきや とりかはし かくきむものと のりのころもを | 法成寺入道前太政大臣 | 十七 | 雑中 |
| 1101 | おなしとし契しあれは君かきるのりの衣をたちおくれめや おなしとし ちきりしあれは きみかきる のりのころもを たちおくれめや | 入道大納言公任 | 十七 | 雑中 |
| 1102 | むかしみし松のこすゑはそれなからむくらのかとをさしてけるかな むかしみし まつのこすゑは それなから むくらのかとを さしてけるかな | 弁乳母 | 十七 | 雑中 |
| 1103 | 山さとのかけひの水のこほれるはおときくよりもさひしかりけり やまさとの かけひのみつの こほれるは おときくよりも さひしかりけり | 輔仁のみこ | 十七 | 雑中 |
| 1104 | やまさとのさひしきやとのすみかにもかけひの水のとくるをそまつ やまさとの さひしきやとの すみかにも かけひのみつの とくるをそまつ | 聡子内親王 | 十七 | 雑中 |
| 1105 | このもとにかきあつめたることのはをわかれし秋のかたみとそみる このもとに かきあつめたる ことのはを わかれしあきの かたみとそみる | 太皇大后宮 | 十七 | 雑中 |
| 1106 | このもとはかくことのはをみるたひにたのみしかけのなきそかなしき このもとは かくことのはを みるたひに たのみしかけの なきそかなしき | 大納言実家 | 十七 | 雑中 |
| 1107 | あとたえてよをのかるへき道なれやいはさへこけの衣きてけり あとたえて よをのかるへき みちなれや いはさへこけの ころもきてけり | 仁和寺法親王(守覚) | 十七 | 雑中 |
| 1108 | 思ひいてのあらは心もとまりなんいとひやすきはうき世なりけり おもひいての あらはこころも とまりなむ いとひやすきは うきよなりけり | 仁和寺法親王(守覚) | 十七 | 雑中 |
| 1109 | やとりするいはやのとこのこけむしろいくよになりぬねこそいられね やとりする いはやのとこの こけむしろ いくよになりぬ ねこそいられね | 前大僧正覚忠 | 十七 | 雑中 |
| 1110 | 身のほとをしらすと人やおもふらんかくうきなからとしをへぬれは みのほとを しらすとひとや おもふらむ かくうきなから としをへぬれは | 大納言宗家 | 十七 | 雑中 |
| 1111 | そむかはやまことの道はしらすともうき世をいとふしるしはかりに そむかはや まことのみちは しらすとも うきよをいとふ しるしはかりに | 右近中将忠良 | 十七 | 雑中 |
| 1112 | そま川におろすいかたのうきなからすきゆく物は我か身なりけり そまかはに おろすいかたの うきなから すきゆくものは わかみなりけり | 二条太皇太后宮別当 | 十七 | 雑中 |
| 1113 | おのつからあれはあるよになからへてをしむと人にみえぬへきかな おのつから あれはあるよに なからへて をしむとひとに みえぬへきかな | 藤原定家 | 十七 | 雑中 |
| 1114 | うしとてもいとひもはてぬよのなかを中中なににおもひしりけん うしとても いとひもはてぬ よのなかを なかなかなにに おもひしりけむ | 摂政家丹後 | 十七 | 雑中 |
| 1115 | のほるへき道にそまとふくらゐ山これよりおくのしるへなけれは のほるへき みちにそまとふ くらゐやま これよりおくの しるへなけれは | 法印倫円 | 十七 | 雑中 |
| 1116 | もろ人の花さくはるをよそにみてなほしくるるはしひしはのそて もろひとの はなさくはるを よそにみて なほしくるるは しひしはのそて | 中納言長方 | 十七 | 雑中 |
| 1117 | うきせにもうれしきせにもさきにたつ涙はおなし涙なりけり うきせにも うれしきせにも さきにたつ なみたはおなし なみたなりけり | 藤原顕方 | 十七 | 雑中 |
| 1118 | このせにもしつむときくは涙川なかれしよりもなほまさりけり このせにも しつむときけは なみたかは なかれしよりも なほまさりけり | 前左兵衛督惟方 | 十七 | 雑中 |
| 1119 | かくはかりうき身なれともすてはてむとおもふになれはかなしかりけり かくはかり うきみなれとも すてはてむと おもふになれは かなしかりけり | 空人法師 | 十七 | 雑中 |
| 1120 | おもひきやしかのうら浪たちかへり又あふ身ともならむものとは おもひきや しかのうらなみ たちかへり またあふみとも ならむものとは | 平康頼 | 十七 | 雑中 |
| 1121 | かくはかりうきよのなかをしのひてもまつへきことのすゑにあるかは かくはかり うきよのなかを しのひても まつへきことの すゑにあるかは | 登蓮法師 | 十七 | 雑中 |
| 1122 | おもひかねあくかれいててゆくみちはあゆく草はに露そこほるる おもひかね あくかれいてて ゆくみちは あゆくくさはに つゆそこほるる | 覚禅法師 | 十七 | 雑中 |
| 1123 | 夢とのみこの世のことのみゆるかなさむへきほとはいつとなけれと ゆめとのみ このよのことの みゆるかな さむへきほとは いつとなけれと | 権僧正永縁 | 十七 | 雑中 |
| 1124 | この世をは雲のはやしにかとてして煙とならん夕をそまつ このよをは くものはやしに かとてして けふりとならむ ゆふへをそまつ | 良暹法師 | 十七 | 雑中 |
| 1125 | うきことのまとろむほとはわすられてさむれは夢の心ちこそすれ うきことの まとろむほとは わすられて さむれはゆめの ここちこそすれ | 読人知らず | 十七 | 雑中 |
| 1126 | いつくとも身をやるかたのしられねはうしとみつつもなからふるかな いつくとも みをやるかたの しられねは うしとみつつも なからふるかな | 紫式部 | 十七 | 雑中 |
| 1127 | うき夢はなこりまてこそかなしけれ此世ののちもなほやなけかん うきゆめは なこりまてこそ かなしけれ このよののちも なほやなけかむ | 皇太后宮大夫俊成 | 十七 | 雑中 |
| 1128 | うつつをもうつつといかかさたむへき夢にも夢をみすはこそあらめ うつつをも うつつといかか さたむへき ゆめにもゆめを みすはこそあらめ | 藤原季通朝臣 | 十七 | 雑中 |
| 1129 | いとひてもなほしのはるるわか身かな二たひくへき此世ならねは いとひても なほしのはるる わかみかな ふたたひくへき このよならねは | 藤原季通朝臣 | 十七 | 雑中 |
| 1130 | これや夢いつれかうつつはかなさをおもひわかてもすきぬへきかな これやゆめ いつれかうつつ はかなさを おもひわかても すきぬへきかな | 上西門院兵衛 | 十七 | 雑中 |
| 1131 | あすしらぬみむろのきしのねなし草なにあたし世におひはしめけん あすしらぬ みむろのきしの ねなしくさ なにあたしよに おひはしめけむ | 花薗左大臣家小大進 | 十七 | 雑中 |
| 1132 | をしからぬ命そさらにをしまるる君かみやこにかへりくるまて をしからぬ いのちそさらに をしまるる きみかみやこに かへりくるまて | 前大納言成通 | 十七 | 雑中 |
| 1133 | うき世をはすてて入りにし山なれときみかとふにやいてんとすらん うきよをは すてていりにし やまなれと きみかとふにや いてむとすらむ | 前大僧正覚忠 | 十七 | 雑中 |
| 1134 | いはそそく水よりほかにおとせねは心ひとつをすましてそきく いはそそく みつよりほかに おとせねは こころひとつに すましてそきく | 仁和寺法親王(守覚) | 十七 | 雑中 |
| 1135 | たれもみな露の身そかしとおもふにも心とまりし草のいほかな たれもみな つゆのみそかしと おもふにも こころとまりし くさのいほかな | 権大納言実国 | 十七 | 雑中 |
| 1136 | なほさりにかへるたもとはかはらねと心はかりそすみそめのそて なほさりに かへるたもとは かはらねと こころはかりそ すみそめのそて | 藤原公衡朝臣 | 十七 | 雑中 |
| 1137 | おほけなくうき世のたみにおほふかなわかたつそまにすみそめのそて おほけなく うきよのたみに おほふかな わかたつそまに すみそめのそて | 法印慈円 | 十七 | 雑中 |
| 1138 | さひしさをうきよにかへてしのはすはひとりきくへき松のかせかは さひしさを うきよにかへて しのはすは ひとりきくへき まつのかせかは | 寂蓮法師 | 十七 | 雑中 |
| 1139 | つくつくとおもへはかなしあかつきのねさめも夢をみるにそ有りける つくつくと おもへはかなし あかつきの ねさめもゆめを みるにそありける | 殷富門院大輔 | 十七 | 雑中 |
| 1140 | まとろみてさてもやみなはいかかせんねさめそあらぬ命なりける まとろみて さてもやみなは いかかせむ ねさめそあらぬ いのちなりける | 西住法師 | 十七 | 雑中 |
| 1141 | さきたつをみるはなほこそかなしけれおくれはつへきこのよならねと さきたつを みるはなほこそ かなしけれ おくれはつへき このよならねと | 六条院宣旨 | 十七 | 雑中 |
| 1142 | いまはとてかきなすことのはてのをに心ほそくもなりまさるかな いまはとて かきなすことの はてのをの こころほそくも なりまさるかな | 二条太皇大后宮式部 | 十七 | 雑中 |
| 1143 | おほゐ川となせのたきに身をなけてはやくと人にいはせてしかな おほゐかは となせのたきに みをなけて はやくとひとに いはせてしかな | 空人法師 | 十七 | 雑中 |
| 1144 | とりへ山きみたつぬともくちはててこけのしたにはこたへさらまし とりへやま きみたつぬとも くちはてて こけのしたには こたへさらまし | 大江公景 | 十七 | 雑中 |
| 1145 | わけわひていとひし庭のよもきふもかれぬとおもふはあはれなりけり わけわひて いとひしにはの よもきふも かれぬとおもふは あはれなりけり | 法眼兼覚 | 十七 | 雑中 |
| 1146 | 世のなかのうきはいまこそうれしけれおもひしらすはいとはましやは よのなかの うきはいまこそ うれしけれ おもひしらすは いとはましやは | 寂蓮法師 | 十七 | 雑中 |
| 1147 | よをそむき草のいほりにすみ染のころもの色はかへるものかは よをそむき くさのいほりに すみそめの ころものいろは かへるものかは | 覚俊上人 | 十七 | 雑中 |
| 1148 | おもひやれならはぬ山にすみ染の袖につゆおく秋のけしきを おもひやれ ならはぬやまに すみそめの そてにつゆおく あきのけしきを | 源通清 | 十七 | 雑中 |
| 1149 | あかつきのあらしにたくふかねのおとを心のそこにこたへてそきく あかつきの あらしにたくふ かねのおとを こころのそこに こたへてそきく | 西行法師 | 十七 | 雑中 |
| 1150 | いつくにか身をかくさましいとひいててうきよにふかき山なかりせは いつくにか みをかくさまし いとひいてて うきよにふかき やまなかりせは | 西行法師 | 十七 | 雑中 |
| 1151 | 世のなかよみちこそなけれおもひいる山のおくにもしかそなくなる よのなかよ みちこそなけれ おもひいる やまのおくにも しかそなくなる | 皇太后宮大夫俊成 | 十七 | 雑中 |
| 1152 | おもふことあり明かたのしかのねはなほ山ふかく家ゐせよとや おもふこと ありあけかたの しかのねは なほやまふかく いへゐせよとや | 藤原良清 | 十七 | 雑中 |
| 1153 | みる夢のすきにしかたをさそひきてさむる枕もむかしなりせは みるゆめの すきにしかたを さそひきて さむるまくらも むかしなりせは | 藤原宗隆 | 十七 | 雑中 |
| 1154 | はつせ山いりあひのかねをきくたひに昔のとほくなるそかなしき はつせやま いりあひのかねを きくたひに むかしのとほく なるそかなしき | 藤原有家朝臣 | 十七 | 雑中 |
| 1155 | ちりつもるこけのしたにもさくら花をしむ心やなほのこるらん ちりつもる こけのしたにも さくらはな をしむこころや なほのこるらむ | 権中納言通親 | 十七 | 雑中 |
| 1156 | うれしさをかへすかへすもつつむへきこけのたもとのせはくも有るかな うれしさを かへすかへすも つつむへき こけのたもとの せはくもあるかな | 入道前中納言雅兼 | 十七 | 雑中 |
| 1157 | うれしさをよその袖まてつつむかなたちかへりぬるあまのはころも うれしさを よそのそてまて つつむかな たちかへりぬる あまのはころも | 藤原季経朝臣 | 十七 | 雑中 |
| 1158 | あしたつの雲ちまよひしとしくれて霞をさへやへたてはつへき あしたつの くもちまよひし としくれて かすみをさへや へたてはつへき | 皇太后宮大夫俊成 | 十七 | 雑中 |
| 1159 | あしたつはかすみをわけてかへるなりまよひし雲ちけふやはるらん あしたつは かすみをわけて かへるなり まよひしくもち けふやはるらむ | 藤原定長朝臣 | 十七 | 雑中 |
| 1160 | もかみ川せせのいはかとわきかへりおもふこころはおほかれと行かたもなくせかれつつそこのみくつとなることはもにすむ虫のわれからとおもひしらすはなけれともいはてはえこそなきさなるかたわれ舟のうつもれてひく人もなきなけきすと浪のたちゐにあふけともむなしき空はみとりにていふこともなきかなしさにねをのみなけはからころもおさふる袖もくちはてぬなにことにかはあはれともおもはん人にあふみなるうちいてのはまのうちいてつついふともたれかささかにのいかさまにてもかきつかんことをはのきにふくかせのはけしきころとしりなからうはの空にもをしふへきあつさのそまにみや木ひきみかきかはらにせりつみしむかしをよそにききしかとわか身のうへになりはてぬさすかに御代のはしめより雲のうへにはかよへともなにはのことも久かたの月のかつらしをられねはうけらか花のさきなからひらけぬことのいふせさによもの山へにあくかれてこのもかのもにたちましりうつふしそめのあさころも花のたもとにぬきかへて後のよをたにとおもへともおもふ人人ほたしにてゆくへきかたもまとはれぬかかるうき身のつれもなくへにける年をかそふれはいつつのとをになりにけりいま行すゑはいなつまのひかりのまにもさためなしたとへはひとりなからへてすきにしはかりすくすとも夢にゆめみる心ちしてひまゆく駒にことならしさらにもいはしふゆかれのをはなかすゑの露なれはあらしをたにもまたすしてもとのしつくとなりはてんほとをはいつとしりてかはくれにとたにもしつむへきかくのみつねにあらそひてなほふるさとにすみのえのしほにたたよふうつせかひうつし心もうせはててあるにもあらぬよのなかに又なにことをみくまののうらのはまゆふかさねつつうきにたヘたるためしにはなるをの松のつれつれといたつらことをかきつめてあはれしれらん行すゑの人のためにはおのつからしのはれぬへき身なれともはかなきことも雲とりのあやにかなはぬくせなれはこれもさこそはみなしくりくち葉かしたにうつもれめそれにつけてもつのくにのいく田のもりのいくたひかあまのたくなはくり返し心にそはぬ身をうらむらん もかみかは せせのいはかと わきかへり おもふこころは おほかれと ゆくかたもなく せかれつつ そこのみくつと なることは もにすむむしの われからと おもひしらすは なけれとも いはてはえこそ なきさなる かたわれふねの うつもれて ひくひともなき なけきすと なみのたちゐに あふけとも むなしきそらは みとりにて いふこともなき かなしさに ねをのみなけは からころも おさふるそても くちはてぬ なにことにかは あはれとも おもはむひとに あふみなる うちいてのはまの うちいてつつ いふともたれか ささかにの いかさまにても かきつかむ ことをはのきに ふくかせの はけしきころと しりなから うはのそらにも をしふへき あつさのそまに みやきひき みかきかはらに せりつみし むかしをよそに ききしかと わかみのうへに なりはてぬ さかすにみよの はしめより くものうへには かよへとも なにはのことも ひさかたの つきのかつらし をられねは うけらかはなの さきなから ひらけぬことの いふせさに よものやまへに あくかれて このもかのもに たちましり うつふしそめの あさころも はなのたもとに ぬきかへて のちのよをたにと おもへとも おもふひとひと ほたしにて ゆくへきかたも まとはれぬ かかるうきみの つれもなく へにけるとしを かそふれは いつつのとをに なりにけり いまゆくすゑは いなつまの ひかりのまにも さためなし たとへはひとり なからへて すきにしはかり すくすとも ゆめにゆめみる ここちして ひまゆくこまに ことならし さらにもいはし ふゆかれの をはなかすゑの つゆなれは あらしをたにも またすして もとのしつくと なりはてむ ほとをはいつと しりてかは くれにとたにも しつむへき かくのみつねに あらそひて なほふるさとに すみのえの しほにたたよふ うつせかひ うつしこころも うせはてて あるにもあらぬ よのなかに またなにことを みくまのの うらのはまゆふ かさねつつ うきにたへたる ためしには なるをのまつの つれつれと いたつらことを かきつめて あはれしれらむ ゆくすゑの ひとのためには おのつから しのはれぬへき みなれとも はかなきことも くもとりの あやにかなはぬ くせなれは これもさこそは みなしくり くちはかしたに うつもれめ それにつけても つのくにの いくたのもりの いくたひか あまのたくなは くりかへし こころにそはぬ みをうらむらむ | 源俊頼朝臣 | 十八 | 雑下 |
| 1161 | よのなかはうき身にそへるかけなれやおもひすつれとはなれさりけり よのなかは うきみにそへる かけなれや おもひすつれと はなれさりけり | 源俊頼朝臣 | 十八 | 雑下 |
| 1162 | しきしまや大和のうたのつたはりをきけははるかに久かたのあまつ神世にはしまりてみそもしあまりひともしはいつもの宮のや雲よりおこりけるとそしるすなるそれより後はもも草のことのはしけくちりちりに風につけつつきこゆれとちかきためしにほりかはのなかれをくみてささ浪のよりくる人にあつらへてつたなきことははまちとりあとをすゑまてととめしとおもひなからもつのくにのなにはのうらのなにとなくふねのさすかに此ことをしのひならひしなこりにてよの人ききははつかしのもりもやせんとおもへともこころにもあらすかきつらねつる しきしまや やまとのうたの つたはりを きけははるかに ひさかたの あまつかみよに はしまりて みそもしあまり ひともしは いつものみやの やくもより おこりけるとそ しるすなる それよりのちは ももくさの ことのはしけく ちりちりに かせにつけつつ きこゆれと ちかきためしに ほりかはの なかれをくみて ささなみの よりくるひとに あつらへて つたなきことは はまちとり あとをすゑまて ととめしと おもひなからも つのくにの なにはのうらの なにとなく ふねのさすかに このことを しのひならひし なこりにて よのひとききは はつかしの もりもやせむと おもへとも こころにもあらす かきつらねつる | 崇徳院御製 | 十八 | 雑下 |
| 1163 | ときしらぬ谷のむもれ木くちはててむかしの春の恋しさになにのあやめもわかすのみかはらぬ月のかけみてもしくれにぬるる袖のうらにしほたれまさるあまころもあはれをかけてとふ人もなみにたたよふつり舟のこきはなれにし世なれとも君に心をかけしよりしけきうれへもわすれくさわすれかほにてすみのえの松のちとせのはるはるとこすゑはるかにさかゆへきときはのかけをたのむにもなくさのはまのなくさみてふるのやしろのそのかみに色ふかからてわすれにしもみちのしたはのこるやとおいその杜にたつぬれといまはあらしにたくひつつしもかれかれにおとろへてかきあつめたる水くきにあさき心のかくれなくなかれての名ををし鳥のうきためしにやならんとすらん ときしらぬ たにのうもれき くちはてて むかしのはるの こひしさに なにのあやめも わかすのみ かはらぬつきの かけみても しくれにぬるる そてのうらに しほたれまさる あまころも あはれをかけて とふひとも なみにたたよふ つりふねの こきはなれにし よなれとも きみにこころを かけしより しけきうれへも わすれくさ わすれかほにて すみのえの まつのちとせの はるはると こすゑはるかに さかゆへき ときはのかけを たのむにも なくさのはまの なくさみて ふるのやしろの そのかみに いろふかからて わすれにし もみちのしたは のこるやと おいそのもりに たつぬれと いまはあらしに たくひつつ しもかれかれに おとろへて かきあつめたる みつくきに あさきこころの かくれなく なかれてのなを をしとりの うきためしにや ならむとすらむ | 待賢門院堀河 | 十八 | 雑下 |
| 1164 | あつまちのやへの霞をわけきてもきみにあはねはなほへたてたる心ちこそすれ あつまちの やへのかすみを わけきても きみにあはねは なほへたてたる ここちこそすれ | 源仲正 | 十八 | 雑下 |
| 1165 | かきたえしままのつきはしふみみれはへたてたるかすみもはれてむかへるかこと かきたえし ままのつきはし ふみみれは へたてたる かすみもはれて むかへるかこと | 源俊頼朝臣 | 十八 | 雑下 |
| 1166 | あつまちののしまかさきのはまかせに我かひもゆひしいもかかほのみおもかけにみゆ あつまちの のしまかさきの はまかせに わかひもゆひし いもかかほのみ おもかけにみゆ | 左京大夫顕輔 | 十八 | 雑下 |
| 1167 | こまなめていさみにゆかんたつた川しら浪よするきしのあたりを こまなへて いさみにゆかむ たつたかは しらなみよする きしのあたりを | 源雅重朝臣 | 十八 | 雑下 |
| 1168 | なにとなく物そかなしきあきかせのみにしむよはのたひのねさめは なにとなく ものそかなしき あきかせの みにしむよはの たひのねさめは | 仁上法師 | 十八 | 雑下 |
| 1169 | 夜のほとにかりそめ人やきたりけんよとのみこものけさみたれたる よのほとに かりそめひとや きたりけむ よとのみこもの けさみたれたる | いつみしきふ | 十八 | 雑下 |
| 1170 | あとたえてとふへき人もおもほえすたれかはけさの雪をわけこん あとたえて とふへきひとも おもほえす たれかはけさの ゆきをわけこむ | 中納言定頼 | 十八 | 雑下 |
| 1171 | さかきははもみちもせしを神かきのからくれなゐにみえわたるかな さかきはは もみちもせしを かみかきの からくれなゐに みえわたるかな | 大弐三位 | 十八 | 雑下 |
| 1172 | いけもふりつつみくつれて水もなしむへかつまたに鳥のゐさらん いけもふり つつみくつれて みつもなし うへかつまたに とりもゐさらむ | 二条太皇大后宮肥後 | 十八 | 雑下 |
| 1173 | わかこまをしはしとかるかやましろのこはたのさとにありとこたへよ わかこまを しはしとかるか やましろの こはたのさとに ありとこたへよ | 源俊頼朝臣 | 十八 | 雑下 |
| 1174 | みくら山ま木のやたててすむたみはとしをつむともくちしとそ思ふ みくらやま まきのやたてて すむたみは としをつむとも くちしとそおもふ | 源俊頼朝臣 | 十八 | 雑下 |
| 1175 | よとともに心をかけてたのめともわれからかみのかたきしるしか よとともに こころをかけて たのめとも われからかみの かたきしるしか | 源俊頼朝臣 | 十八 | 雑下 |
| 1176 | 秋ののにたれをさそはむ行きかへりひとりははきをみるかひもなし あきののに たれをさそはむ ゆきかへり ひとりははきを みるかひもなし | 刑部卿頼輔母 | 十八 | 雑下 |
| 1177 | あきは霧きりすきぬれは雪ふりてはるるまもなきみ山へのさと あきはきり きりすきぬれは ゆきふりて はるるまもなき みやまへのさと | 待賢門院堀川 | 十八 | 雑下 |
| 1178 | いなり山しるしのすきの年ふりてみつのみやしろ神さひにけり いなりやま しるしのすきの としふりて みつのみやしろ かみさひにけり | 僧都有慶 | 十八 | 雑下 |
| 1179 | 名にしおははつねはゆるきのもりにしもいかてかさきのいはやすくぬる なにしおはは つねはゆるきの もりにしも いかてかさきの いはやすくぬる | 登蓮法師 | 十八 | 雑下 |
| 1180 | あやしくも花のあたりにふせるかなをらはとかむる人やあるとて あやしくも はなのあたりに ふせるかな をらはとかめむ ひとやあるとて | 道命法師 | 十八 | 雑下 |
| 1181 | うの花よいてことことしかけしまの浪もさこそはいはをこえしか うのはなよ いてことことし かけしまの なみもさこそは いはをこえしか | 源俊頼朝臣 | 十八 | 雑下 |
| 1182 | けふかくるたもとにねさせあやめ草うきはわか身にありとしらすや けふかくる たもとにねさせ あやめくさ うきはわかみに ありとしらすや | 道因法師 | 十八 | 雑下 |
| 1183 | ともししてはこねの山にあけにけりふたよりみよりあふとせしまに ともしして はこねのやまに あけにけり ふたよりみより あふとせしまに | 橘俊綱朝臣 | 十八 | 雑下 |
| 1184 | 夏のうちははたかくれてもあらすしておりたちにけるむしのこゑかな なつのうちは はたかくれても あらすして おりたちにける むしのこゑかな | 江侍従 | 十八 | 雑下 |
| 1185 | あきくれは秋のけしきもみえけるは時ならぬ身となににいふらん あきくれは あきのけしきも みえけるは ときならぬみと なににいふらむ | 輔仁のみこ | 十八 | 雑下 |
| 1186 | あさ露を日たけてみれはあともなしはきのうらはに物やとはまし あさつゆを ひたけてみれは あともなし はきのうらはに ものやとはまし | 藤原為頼朝臣 | 十八 | 雑下 |
| 1187 | つはなおひしをののしはふのあさ露をぬきちらしける玉かとそみる つはなおひし をののしはふの あさつゆを ぬきちらしける たまかとそみる | 花薗左大臣家小大進 | 十八 | 雑下 |
| 1188 | おちにきとかたらはかたれをみなへしこよひは花のかけにやとらん おちにきと かたらはかたれ をみなへし こよひははなの かけにやとらむ | 僧都範玄 | 十八 | 雑下 |
| 1189 | くれの秋ことにさやけき月かけはとよにあまりてみよとなりけり くれのあき ことにさやけき つきかけは とよにあまりて みよとなりけり | 賀茂政平 | 十八 | 雑下 |
| 1190 | いたひさしさすやかややの時雨こそおとしおとせぬかたはわくなれ いたひさし さすやかややの しくれこそ おとしおとせぬ かたはわくなれ | 顕昭法師 | 十八 | 雑下 |
| 1191 | ふえ竹のあなあさましのよの中やありしやふしのかきりなるらん ふえたけの あなあさましの よのなかや ありしやふしの かきりなるらむ | 藤原基俊 | 十八 | 雑下 |
| 1192 | したひくる恋のやつこのたひにても身のくせなれやゆふととろきは したひくる こひのやつこの たひにても みのくせなれや ゆふととろきは | 源俊頼朝臣 | 十八 | 雑下 |
| 1193 | あふことのなけきのつもるくるしさをおへかし人のこりはつるまて あふことの なけきのつもる くるしさを おへかしひとの こりはつるまて | 待賢門院堀河 | 十八 | 雑下 |
| 1194 | 人のあしをつむにてしりぬわかかたへふみおこせよとおもふなるへし ひとのあしを つむにてしりぬ わかかたへ ふみおこせよと おもふなるへし | 良喜法師 | 十八 | 雑下 |
| 1195 | おそろしやきそのかけちのまろ木はしふみみるたひにおちぬへきかな おそろしや きそのかけちの まろきはし ふみみるたひに おちぬへきかな | 空人法師 | 十八 | 雑下 |
| 1196 | ふえ竹のこちくとなににおもひけんとなりにおとはせしにそ有りける ふえたけの こちくとなにに おもひけむ となりにおとは せしにそありける | 心覚法師 | 十八 | 雑下 |
| 1197 | やつはしのわたりにけふもとまるかなここにすむへきみかはとおもへと やつはしの わたりにけふも とまるかな ここにすむへき みかはとおもへと | 道因法師 | 十八 | 雑下 |
| 1198 | つらしとてさてはよもわれ山からすかしらはしろくなる世なりとも つらしとて さてはよもわれ やまからす かしらはしろく なるよなりとも | 安性法師(俗名時元) | 十八 | 雑下 |
| 1199 | かみにおけるもしはまことのもしなれはうたもよみちをたすけさらめや かみにおける もしはまことの もしなれは うたもよみちを たすけさらめや | 源俊頼朝臣 | 十八 | 雑下 |
| 1200 | けふも又むまのかひこそふきつなれひつしのあゆみちかつきぬらん けふもまた うまのかひこそ ふきつなれ ひつしのあゆみ ちかつきぬらむ | 赤染衛門 | 十八 | 雑下 |
| 1201 | こくらくははるけきほととききしかとつとめていたるところなりけり こくらくは はるけきほとと ききしかと つとめていたる ところなりけり | 空也上人 | 十八 | 雑下 |
| 1202 | ここにきえかしこにむすふ水のあわのうきよにめくる身にこそ有りけれ ここにきえ かしこにむすふ みつのあわの うきよにめくる みにこそありけれ | 前大納言公任 | 十九 | 釈教 |
| 1203 | さためなき身はうき雲によそへつつはてはそれにそなりはてぬへき さためなき みはうきくもに よそへつつ はてはそれにそ なりはてぬへき | 前大納言公任 | 十九 | 釈教 |
| 1204 | 世の中はみなほとけなりおしなへていつれのものとわくそはかなき よのなかは みなほとけなり おしなへて いつれのものと わくそはかなき | 花山院御製 | 十九 | 釈教 |
| 1205 | おほそらの雨はわきてもそそかねとうるふ草木はおのかしなしな おほそらの あめはわきても そそかねと うるふくさきは おのかしなしな | 僧都源信 | 十九 | 釈教 |
| 1206 | もとめてもかかるはちすの露をおきてうきよに又はかへるものかは もとめても かかるはちすの つゆをおきて うきよにまたは かへるものかは | 清少納言 | 十九 | 釈教 |
| 1207 | 月かけのつねにすむなる山のはをへたつる雲のなからましかは つきかけの つねにすむなる やまのはを へたつるくもの なからましかは | 藤原国房 | 十九 | 釈教 |
| 1208 | いる月をみるとや人はおもふらん心をかけてにしにむかへは いるつきを みるとやひとは おもふらむ こころをかけて にしにむかへは | 堀川入道左大臣 | 十九 | 釈教 |
| 1209 | たききつき煙もすみてさりにけんこれやなこりとみるそかなしき たききつき けふりもすみて さりにけむ これやなこりと みるそかなしき | 瞻西上人 | 十九 | 釈教 |
| 1210 | 夢さめんその暁をまつほとのやみをもてらせのりのともし火 ゆめさめむ そのあかつきを まつほとの やみをもてらせ のりのともしひ | 藤原敦家朝臣 | 十九 | 釈教 |
| 1211 | よをてらすほとけのしるしありけれはまたともし火もきえぬなりけり よをてらす ほとけのしるし ありけれは またともしひも きえぬなりけり | 前大僧正覚忠 | 十九 | 釈教 |
| 1212 | みるままに涙そおつるかきりなき命にかはるすかたとおもへは みるままに なみたそおつる かきりなき いのちにかはる すかたとおもへは | 前大僧正覚忠 | 十九 | 釈教 |
| 1213 | ちとせまてむすひし水も露はかりわか身のためとおもひやはせし ちとせまて むすひしみつも つゆはかり わかみのためと おもひやはせし | 僧都覚雅 | 十九 | 釈教 |
| 1214 | うれしくそ名をたもつたにあたならぬみのりの花にみをむすひける うれしくそ なをたもつたに あたならぬ みのりのはなに みをむすひける | 前大僧正快修 | 十九 | 釈教 |
| 1215 | わひ人の心のうちをよそなからしるやさとりのひかりなるらん わひひとの こころのうちを よそなから しるやさとりの ひかりなるらむ | 源俊頼朝臣 | 十九 | 釈教 |
| 1216 | ちかひをはちひろのうみにたとふなり露もたのまはかすにいりなん ちかひをは ちひろのうみに たとふなり つゆもたのまは かすにいりなむ | 崇徳院御製 | 十九 | 釈教 |
| 1217 | はかなくそみよのほとけとおもひけるわかみひとつにありとしらすて はかなくそ みよのほとけと おもひける わかみひとつに ありとしらすて | 前参議教長 | 十九 | 釈教 |
| 1218 | てる月の心の水にすみぬれはやかてこの身にひかりをそさす てるつきの こころのみつに すみぬれは やかてこのみに ひかりをそさす | 前参議教長 | 十九 | 釈教 |
| 1219 | かへりてもいりそわつらふまきのとをまとひいてにし心ならひに かへりても いりそわつらふ まきのとを まとひいてにし こころならひに | 前大僧正覚忠 | 十九 | 釈教 |
| 1220 | ふる雪はたにのとほそをうつむともみよのほとけのひやてらすらん ふるゆきは たにのとほそを うつむとも みよのほとけの ひやてらすらむ | 崇徳院御製 | 十九 | 釈教 |
| 1221 | てらすなるみよのほとけのあさひにはふる雪よりもつみやきゆらん てらすなる みよのほとけの あさひには ふるゆきよりも つみやきゆらむ | 仁和寺後入道法親王(覚性) | 十九 | 釈教 |
| 1222 | ふるさとをひとりわかるるゆふへにもおくるは月のかけとこそきけ ふるさとを ひとりわかるる ゆふへにも おくるはつきの かけとこそきけ | 式子内親王 | 十九 | 釈教 |
| 1223 | 人ことにかはるはゆめのまとひにてさむれはおなしこころなりけり ひとことに かはるはゆめの まとひにて さむれはおなし こころなりけり | 摂政前右大臣 | 十九 | 釈教 |
| 1224 | すめはみゆにこれはかくるさためなきこのみや水にやとる月かけ すめはみゆ にこれはかくる さためなき このみやみつに やとるつきかけ | 宮内卿永範 | 十九 | 釈教 |
| 1225 | いととしくむかしのあとやたえなんとおもふもかなしけさのしら雪 いととしく むかしのあとや たえなむと おみふもかなし けさのしらゆき | 法印慈円 | 十九 | 釈教 |
| 1226 | 君か名そなほあらはれんふる雪にむかしのあとはうつもれぬとも きみかなそ なほあらはれむ ふるゆきに むかしのあとは うつもれぬとも | 尊円法師 | 十九 | 釈教 |
| 1227 | ひとりのみくるしきうみをわたるとやそこをさとらぬ人はみるらん ひとりのみ くるしきうみを わたるとや そこをさとらぬ ひとはみるらむ | 左近中将良経 | 十九 | 釈教 |
| 1228 | くれ竹のむなしととけることのははみよの仏のははとこそきけ くれたけの むなしととける ことのはは みよのほとけの ははとこそきけ | 藤原隆信朝臣 | 十九 | 釈教 |
| 1229 | むなしきも色なるものとさとれとやはるのみそらのみとりなるらん むなしきも いろなるものと さとれとや はるのみそらの みとりなるらむ | 摂政家丹後 | 十九 | 釈教 |
| 1230 | なかき夜もむなしき物としりぬれははやくあけぬる心ちこそすれ なかきよも むなしきものと しりぬれは はやくあけぬる ここちこそすれ | 前中納言師仲 | 十九 | 釈教 |
| 1231 | わしの山月をいりぬとみる人はくらきにまよふ心なりけり わしのやま つきをいりぬと みるひとは くらきにまよふ こころなりけり | 西行法師 | 十九 | 釈教 |
| 1232 | いさきよきいけにかけこそうかひぬれしつみやせんとおもふわかみを いさきよき いけにかけこそ うかひぬれ しつみやせむと おもふわかみを | 神祇伯顕仲 | 十九 | 釈教 |
| 1233 | くちはつる袖にはいかかつつまましむなしととけるみのりならすは くちはつる そてにはいかか つつままし むなしととける みのりならすは | 寂超法師 | 十九 | 釈教 |
| 1234 | みるほとはゆめも夢ともしられねはうつつもいまはうつつとおもはし みるほとは ゆめもゆめとも しられねは うつつもいまは うつつとおもはし | 藤原資隆朝臣 | 十九 | 釈教 |
| 1235 | おとろかぬわか心こそうかりけれはかなき世をは夢とみなから おとろかぬ わかこころこそ うかりけれ はかなきよをは ゆめとみなから | 登蓮法師 | 十九 | 釈教 |
| 1236 | 暁をたかのの山にまつほとやこけのしたにもあり明の月 あかつきを たかののやまに まつほとや こけのしたにも ありあけのつき | 寂蓮法師 | 十九 | 釈教 |
| 1237 | おもひとくこころひとつになりぬれはこほりも水もへたてさりけり おもひとく こころひとつに なりぬれは こほりもみつも へたてさりけり | 式子内親王家中将 | 十九 | 釈教 |
| 1238 | たのもしきちかひは春にあらねともかれにしえたも花そさきける たのもしき ちかひははるに あらねとも かれにしえたも はなそさきける | 前大納言時忠 | 十九 | 釈教 |
| 1239 | 春ことになけきしものをのりのにはちるかうれしき花もありけり はることに なけきしものを のりのには ちるかうれしき はなもありけり | 藤原伊綱 | 十九 | 釈教 |
| 1240 | みくさのみしけきにこりとみしかともさても月すむえにこそ有りけれ みくさのみ しけきにこりと みしかとも さてもつきすむ えにこそありけれ | 左京大夫季能 | 十九 | 釈教 |
| 1241 | むさしののほりかねの井もあるものをうれしく水のちかつきにける むさしのの ほりかねのゐも あるものを うれしくみつの ちかつきにける | 皇太后宮大夫俊成 | 十九 | 釈教 |
| 1242 | たに水をむすへはうつるかけのみやちとせをおくる友となりけん たにみつを むすへはうつる かけのみや ちとせをおくる ともとなりけむ | 顕昭法師 | 十九 | 釈教 |
| 1243 | くちはててあやふくみえしをはたたのいたたのはしもいまわたすなり くちはてて あやふくみえし をはたたの いたたのはしも いまわたすなり | 法橋泰覚 | 十九 | 釈教 |
| 1244 | うらみけるけしきやそらにみえつらんをはすて山をてらす月かけ うらみける けしきやそらに みえつらむ をはすてやまを てらすつきかけ | 藤原敦仲 | 十九 | 釈教 |
| 1245 | 日のひかり月のかけとそてらしけるくらき心のやみはれよとて ひのひかり つきのかけとそ てらしける くらきこころの やみはれよとて | 蓮上法師(俗名成実) | 十九 | 釈教 |
| 1246 | さらにまた花そふりしくわしの山のりのむしろのくれかたのそら さらにまた はなそふりしく わしのやま のりのむしろの くれかたのそら | 皇太后宮大夫俊成 | 十九 | 釈教 |
| 1247 | まちいてていかにうれしくおもほえんはつかあまりの山のはの月 まちいてて いかにうれしく おもほえむ はつかあまりの やまのはのつき | 中原有安 | 十九 | 釈教 |
| 1248 | あさまたきみのりのにはにふる雪はそらより花のちるかとそみる あさまたき みのりのにはに ふるゆきは そらよりはなの ちるかとそみる | 中原清重 | 十九 | 釈教 |
| 1249 | もち月の雲かくれけんいにしへのあはれをけふのそらにしるかな もちつきの くもかくれけむ いにしへの あはれをけふの そらにしるかな | 恵章法師 | 十九 | 釈教 |
| 1250 | きよくすむ心のそこをかかみにてやかてそうつる色もすかたも きよくすむ こころのそこを かかみにて やかてそうつる いろもすかたも | 俊秀法師 | 十九 | 釈教 |
| 1251 | けふりたにしはしたなひけ鳥へ山たちわかれにしかたみともみん けふりたに しはしたなひけ とりへやま たちわかれにし かたみともみむ | 寂然法師 | 十九 | 釈教 |
| 1252 | とりのねも浪のおとにそかよふなるおなし御のりをとけはなりけり とりのねも なみのおとにそ かよふなる おなしみのりを きけはなりけり | 平康頼 | 十九 | 釈教 |
| 1253 | よをすくふあとはむかしにかはらねとはしめたてけん時をしそ思ふ よをすくふ あとはむかしに かはらねと はしめたてけむ ときをしそおもふ | 藤原定長朝臣 | 十九 | 釈教 |
| 1254 | つねならぬためしは夜はのけふりにてきえぬなこりをみるそうれしき つねならぬ ためしはよはの けふりにて きえぬなこりを みるそうれしき | 天台座主明雲 | 十九 | 釈教 |
| 1255 | みな人をわたさむとおもふ心こそ極楽へゆくしるへなりけれ みなひとを わたさむとおもふ こころこそ こくらくへゆく しるへなりけれ | 律師永観 | 十九 | 釈教 |
| 1256 | みかさ山さしてきにけりいそのかみふるきみゆきのあとをたつねて みかさやま さしてきにけり いそのかみ ふるきみゆきの あとをたつねて | 上東門院 | 二十 | 神祇 |
| 1257 | すみよしのなみも心をよせけれはむへそみきはにたちまさりける すみよしの なみもこころを よせけれは うへそみきはに たちまさりける | 大納言経輔 | 二十 | 神祇 |
| 1258 | おもふことくみてかなふる神なれはしほやにあとをたるるなりけり おもふこと くみてかなふる かみなれは しほやにあとを たるるなりけり | 後三条内大臣 | 二十 | 神祇 |
| 1259 | みちのへのちりに光をやはらけて神もほとけのなのるなりけり みちのへの ちりにひかりを やはらけて かみもほとけの なのるなりけり | 崇徳院御製 | 二十 | 神祇 |
| 1260 | あめのしたのとけかれとやさかきはをみかさの山にさしはしめけん あめのした のとけかれとや さかきはを みかさのやまに さしはしめけむ | 藤原清輔朝臣 | 二十 | 神祇 |
| 1261 | 神世よりつもりのうらにみやゐしてへぬらんとしのかきりしらすも かみよより つもりのうらに みやゐして へぬらむとしの かきりしらすも | 大納言隆季 | 二十 | 神祇 |
| 1262 | かそふれはやとせへにけりあはれわかしつみしことはきのふと思ふに かそふれは やとせへにけり あはれわか しつみしことは きのふとおもふに | 右おほいまうちきみ | 二十 | 神祇 |
| 1263 | いたつらにふりぬる身をもすみよしの松はさりともあはれしるらん いたつらに ふりぬるみをも すみよしの まつはさりとも あはれしるらむ | 皇太后宮大夫俊成 | 二十 | 神祇 |
| 1264 | ふりにける松ものいははとひてましむかしもかくやすみのえの月 ふりにける まつものいはは とひてまし むかしもかくや すみのえのつき | 右大臣 | 二十 | 神祇 |
| 1265 | すみよしのまつのゆきあひのひまよりも月さえぬれは霜はおきけり すみよしの まつのゆきあひの ひまよりも つきさえぬれは しもはおきけり | 俊恵法師 | 二十 | 神祇 |
| 1266 | おしなへて雪のしらゆふかけてけりいつれさか木のこすゑなるらん おしなへて ゆきのしらゆふ かけてけり いつれさかきの こすゑなるらむ | 権大納言実国 | 二十 | 神祇 |
| 1267 | めつらしくみゆきをみわの神ならはしるしありまのいてゆなるへし めつらしく みゆきをみわの かみならは しるしありまの いてゆなるへし | 按察使資賢 | 二十 | 神祇 |
| 1268 | うれしくも神のちかひをしるへにて心をおこす門にいりぬる うれしくも かみのちかひを しるへにて こころをおこす かとにいりぬる | 権中納言経房 | 二十 | 神祇 |
| 1269 | すきかえをかすみこむれとみわの山神のしるしはかくれさりけり すきかえを かすみこむれと みわのやま かみのしるしは かくれさりけり | 僧都範玄 | 二十 | 神祇 |
| 1270 | いままてになとしつむらんきふねかはかはかりはやき神をたのむを いままてに なとしつむらむ きふねかは かはかりはやき かみをたのむを | 平実重 | 二十 | 神祇 |
| 1271 | さりともとたのみそかくるゆふたすきわかかたをかの神と思へは さりともと たのみそかくる ゆふたすき わかかたをかの かみとおもへは | 賀茂政平 | 二十 | 神祇 |
| 1272 | さりともとたのむ心は神さひてひさしくなりぬかものみつかき さりともと たのむこころは かみさひて ひさしくなりぬ かものみつかき | 式子内親王 | 二十 | 神祇 |
| 1273 | 君をいのるねかひをそらにみてたまへわけいかつちの神ならはかみ きみをいのる ねかひをそらに みてたまへ わけいかつちの かみならはかみ | 賀茂重保 | 二十 | 神祇 |
| 1274 | きふね川たまちるせせのいは浪に氷をくたく秋のよの月 きふねかは たまちるせせの いはなみに こほりをくたく あきのよのつき | 皇太后宮大夫俊成 | 二十 | 神祇 |
| 1275 | わかたのむ日よしのかけはおく山のしはの戸まてもさささらめやは わかたのむ ひよしのかけは おくやまの しはのとまても さささらめやは | 法印慈円 | 二十 | 神祇 |
| 1276 | いつとなくわしのたかねにすむ月のひかりをやとすしかのからさき いつとなく わしのたかねに すむつきの ひかりをやとす しかのからさき | 法橋性憲 | 二十 | 神祇 |
| 1277 | みゆきするたかねのかたに雲はれてそらにひよしのしるしをそみる みゆきする たかねのかたに くもはれて そらにひよしの しるしをそみる | 中原師尚 | 二十 | 神祇 |
| 1278 | ふかくいりて神ちのおくをたつぬれは又うへもなきみねの松かせ ふかくいりて かみちのおくを たつぬれは またうへもなき みねのまつかせ | 西行法師 | 二十 | 神祇 |
| 1279 | 月よみの神してらさはあた雲のかかるうきよもはれさらめやは つきよみの かみしてらさは あたくもの かかるうきよも はれさらめやは | 大中臣為定 | 二十 | 神祇 |
| 1280 | いはし水きよきなかれのたえせねはやとる月さへくまなかりけり いはしみつ きよきなかれの たえせねは やとるつきさへ くまなかりけり | 能蓮法師 | 二十 | 神祇 |
| 1281 | ときはなる神なひ山のさかきはをさしてそいのるよろつよのため ときはなる かみなひやまの さかきはを さしてそいのる よろつよのため | 藤原義忠朝臣 | 二十 | 神祇 |
| 1282 | うこきなく千代をそいのるいはや山とるさか木はの色かへすして うこきなく ちよをそいのる いはややま とるさかきはの いろかへすして | 藤原経衡 | 二十 | 神祇 |
| 1283 | いにしへの神の御代よりもろかみのいのるいはひはきみかよのため いにしへの かみのみよより もろかみの いのるいはひは きみかよのため | 前中納言匡房 | 二十 | 神祇 |
| 1284 | 神うくるとよのあかりにゆふそののひかけかつらそはへまさりける かみうくる とよのあかりに ゆふそのの ひかけかつらそ はへまさりける | 宮内卿永範 | 二十 | 神祇 |
| 1285 | すへらきをやほよろつよの神もみなときはにまもる山の名そこれ すめらきを やほよろつよの かみもみな ときはにまもる やまのなそこれ | 宮内卿永範 | 二十 | 神祇 |
| 1286 | みしめゆふかたにとりかけ神なひの山のさかきをかさしにそする みしまゆふ かたにとりかけ かみなひの やまのさかきを かさしにそする | 権中納言兼光 | 二十 | 神祇 |
| 1287 | もろ神の心にいまそかなふらし君をやちよといのるよことは もろかみの こころにいまそ かなふらし きみをやちよと いのるよことは | 藤原季経朝臣 | 二十 | 神祇 |
| 1288 | 千とせ山神のよませるさかきはのさかえまさるはきみかためとか ちとせやま かみのよませる さかきはの さかえまさるは きみかためとか | 藤原光範朝臣 | 二十 | 神祇 |
| 1289 | 暁になりやしぬらん月影のきよきかはらにちとりなくなり あかつきに なりやしぬらむ つきかけの きよきかはらに ちとりなくなり | 右大臣 | 他 | 異本歌 |
| 1290 | 君すめはここも雲ゐの月なれとなほ恋しきは宮こなりけり きみすめは ここもくもゐの つきなれと なほこひしきは みやこなりけり | 左馬頭行盛 | 他 | 異本歌 |
※読人(作者)についてはできる限り正確に整えておりますが、誤りもある可能性があります。ご了承ください。
※御製歌は〇〇院としています。〇〇天皇の歌となります。
※円位法師は西行法師に統一しています。
※作者検索をしたいときは、藤原、源といったいわゆる氏を除いた名のみで検索することをおすすめいたします。
※濁点につきましては原文通り加えておりません。時間的余裕があれば書き加えてまいります。