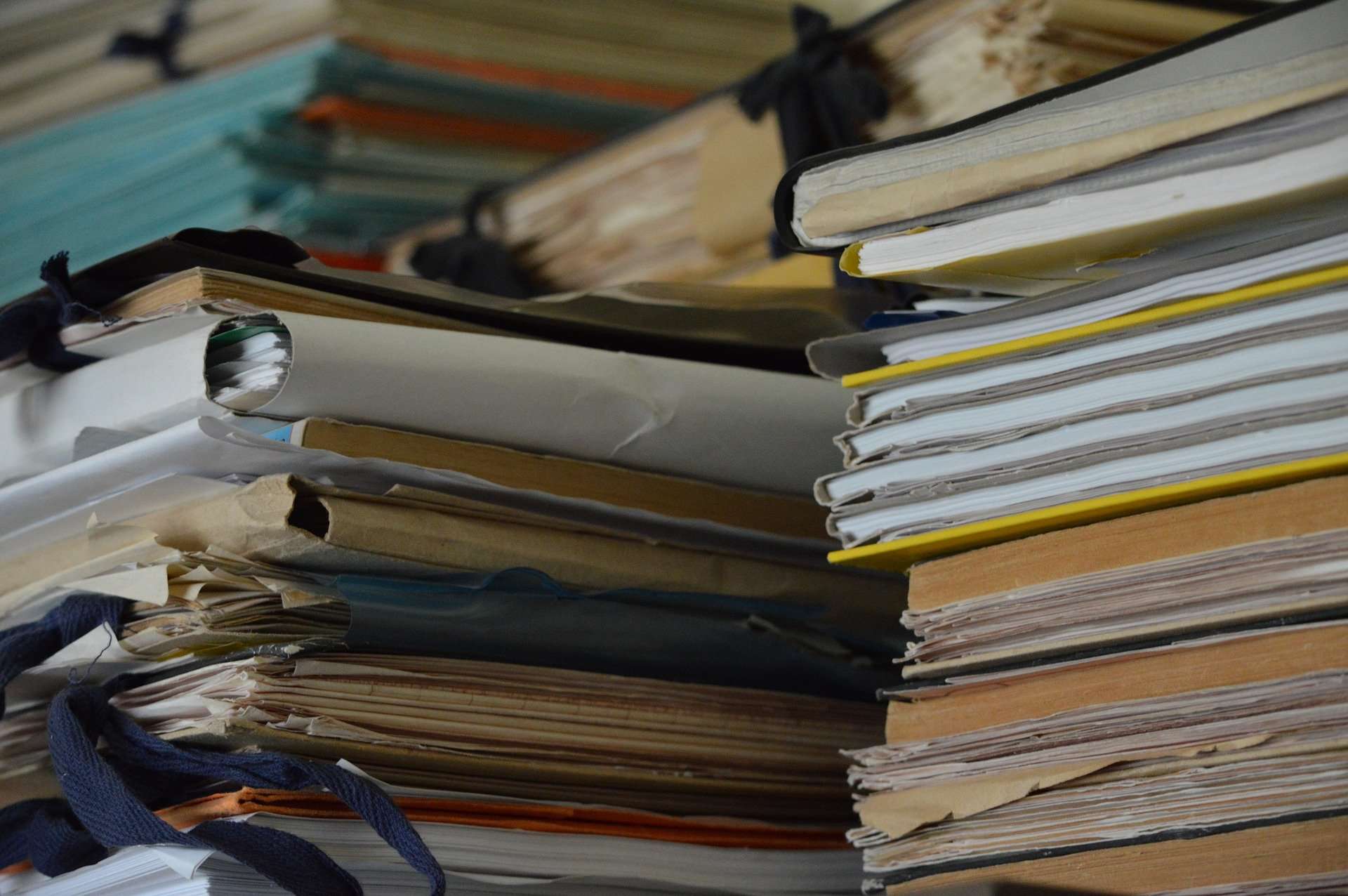このページは、宅建業法における報酬に関するまとめです。他の項目、法令については以下のページから確認してください。報酬は計算方法が覚えにくいため、苦手な人も多い。そのうえ、出題されても1点分。苦手な人は飛ばしてしまうことも戦略の一つです。
| 宅建士試験対策 | 宅建業法のゴロ合わせ |
報酬のきまり
法定の報酬以外、請求してはならない(依頼による広告費、承諾をした特別費を除く)
売買・交換における報酬の限度額
1.建物は課税されるが、土地は非課税
よって、本体価格 = 建物売買価格‐消費税 + 土地売買価格
※建物に課税された消費税分を減額する
※交換取引では、資産価値の高額なほうの価格を用いる
2.本体価格に応じた速算式で報酬額を求める
|
本体価格 |
速算式 |
|
|
400万円超 |
3% + 6万円 |
|
|
400万円以下 |
4% + 2万円 |
同意あれば現地調査費を加えることができる |
|
200万円以下 |
5% |
3.消費税を適用
課税業者なら10%、免税業者なら4%を加算する
報酬上限計算の流れ表
|
取引 |
→ |
売買 |
→ |
代理 |
→ |
売主から計2倍(承諾で買主からも) |
① |
||
|
媒介 |
→ |
1倍(そのまま)を双方がそれぞれから ※媒介が1業者であるときは、双方から、計2倍 |
② |
||||||
|
混在 |
→ |
双方の、別々で計算すること、ただし、計2倍 |
③ |
||||||
|
→ |
賃借 |
→ |
居住 |
→ |
権利金 |
無関係 |
一方から0.5ヵ月分が(合計1ヵ月) 承諾によって一方から1カ月ともできる |
④ |
|
|
非居住 宅地 |
→ |
無し |
計1カ月分 |
|
|||||
|
有り |
権利金額を売買代金とみなし、 各々から売買として計算 <売買計算式> |
⑤ |
|||||||
※承諾は媒介契約時に得ること
※権利金とは返還されない金銭をいう
※取引形態を第一に確認し、賃借であれば居住かそうでないかと権利金があるかを確認する
支払の時期
報酬上限に関する練習問題
【①売買代理契約】甲所有の宅地を代金5000万円で乙が買う代理契約
甲 → A →5000万円→ B ← 乙
5000万の宅地、5000万円×3%+6万円=156万円 ×2×1.1 ⇒ 343万2000円
Aは甲から343万2000円、Bは乙から報酬無し ※合計で343万2000円を超えないこと
※売買の代理であるから、売主であるAから2倍の額(承諾あれば買主のBからも可)
【②売買媒介契約】甲所有の倉庫を5500万円(税込み)で乙が買う媒介契約
甲 → A →5500万円→ B ← 乙
宅地ではない。よって計算するうえで、5500万円の消費税分を減じて計算する
5000万円の倉庫、5000万円×3%+6万円=156万円 ×1.1 ⇒ 171万6000円
Aは甲から171万6000円、Bは乙から171万6000円
※売買の媒介であるから双方が双方から、1倍の額を受け取る(合計で2倍になっている)
【③交換代理媒介契約】甲所有の2700万円の宅地、乙所有の5000万円の宅地の交換契約
甲 → A(代理) →5000万円→ B(媒介) ← 乙
代理と媒介が混在している場合、計算には高額な価格を用いる
Aは、(5000万円×3%+6万円)×2×1.1=343万2000円
Bは、(5000万円×3%+6万円) ×1.1=171万6000円 ※AとBの合計は2倍以内
※合計で343万2000円以内であるが、Bからは171万6000円が上限であるということ
※交換の代理・媒介混在であるから、高額の乙宅地とし、各々別々に計算し、計2倍以内
【④賃借媒介契約】貸主甲の居住用建物を1カ月当たりの借賃10万円で乙が借りる賃借媒介契約
★2つの業者のパターン
甲 → A →10万円→ B ← 乙
各々0.5ヵ月 Aは甲から5万5000円、Bは乙から5万5000円が上限 合計1カ月分
※5万5000円=10万円×0.5×1.1
※居住用賃借であるから双方各々から0.5カ月が上限となる
★1つの業者のパターン
甲 → A 10万円 → 乙
各々0.5カ月(5万5000円ずつ)であるが承諾あれば甲が11万円、乙は0円とできる
※賃借の居住用であるから0.5であるが、承諾あるから一方から1カ月分
【⑤賃借媒介契約】甲所有の宅地を権利金800万円、借賃40万円とする賃借の媒介契約
甲 → A 40万円(権利金800万円) → 乙
宅地の賃借であるから権利金を用いる。800万円×3%+6万円=30万円
※宅地に消費税は課されない!
甲及び乙のそれぞれから30万円(計60万円)を受領することができる。
※賃借の宅地の媒介であるから権利金を用い、売買式として貸主から計2倍
権利金がある非居住宅地は、権利金を用いて売買式として計算する